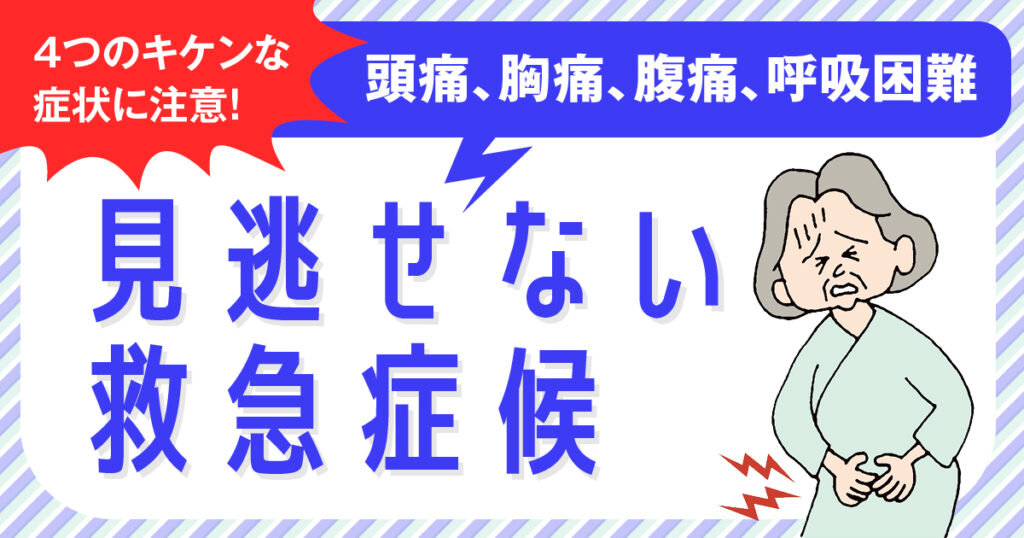患者さんの訴えから重大な疾患を見きわめて、すぐに対応するには?今回は腹痛の訴えがあったときのアセスメントの流れを紹介します。キラーディジーズを見落とさないためのポイントをおさえましょう。
●大動脈瘤破裂
●消化管穿孔
●急性胆管炎
●急性腸間膜虚血
ABCD評価から、緊急性の高さを判断
急激に発症した腹痛のなかで、緊急手術を含む迅速な対応を要する腹部疾患群のことを「急性腹症」といいます1。そのなかでも危険な疾患が、冒頭で挙げた4つの疾患であり、急な腹痛ではこれらの疾患を疑ってのアセスメントが必要です。
腹痛を訴えた場合は、まずABCD(A:気道、B:呼吸、C:循環、D:意識)の評価をします(【第1回】参照)。ABCDの異常があれば、緊急性の高い疾患を想定します。なかでも、超緊急として大動脈瘤破裂のほかに、急性心筋梗塞(【第8回】)、肺血栓塞栓症(【第10回】)、大動脈解離(【第9回】)でも腹痛を訴えるケースがあります。これらの疾患は、分単位で症状が悪化するため、その特徴をとらえ、ただちに対応する必要があります。
急性腹症を疑い、腹部をアセスメント
次に、緊急性の高い疾患を見逃さないように、問診・視診・打診・触診と随伴症状の確認を行います。聴診は、急性腹症では有用な情報となることは少なく、腸閉塞時の異常な腸雑音が参考になる程度です。亢進や低下といった表現は主観的であり、アセスメントの判断材料には不向きです。急性腹症を疑う場合は、聴診に時間をかけるべきではありません。
腹痛の訴えがあったときのアセスメントの流れ
1 問診と、身体所見のアセスメントを行う
●問診では、OPQRSTT 法(【第6回】・表1参照)を参考に情報収集をする。
●身体所見では、可能な限り剣状突起から鼠径部まで露出して進める。その際、患者さんの右側に立つことが推奨される(図1)1。
この記事は会員限定記事です。