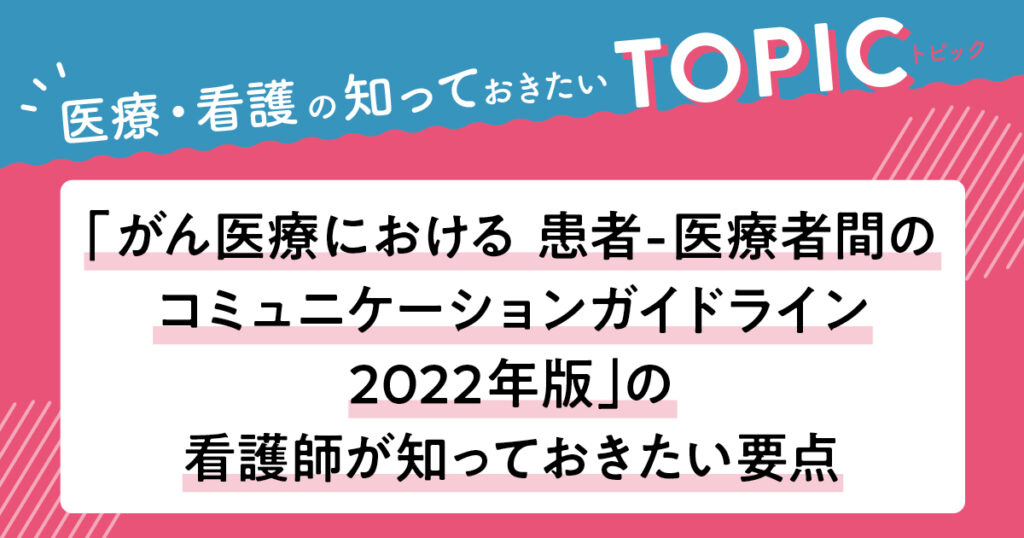『がん医療における 患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン 2022年版』は、疾患や治療に関する患者さんからの質問に答える場面や、患者さんに大切なことを伝える場面で役立ちます。看護師が知っておきたい要点を紹介します。
今回のガイドライン作成の背景
●患者さんは、「医師の説明」「医師や看護師の態度や言葉づかい」など医療者とのコミュニケーションに不満を感じている
●医療者は、「患者さんに苦痛を与えてしまう懸念」「患者さんが感情的になることへの心配」「コミュニケーション研修機会の不足」などから、患者さんとのコミュニケーションに不安がある
●コミュニケーションの問題は、患者さんの満足感や精神的苦痛、治療アドヒアランス、医師の燃え尽きに関係する
●がん医療におけるコミュニケーションに悩む患者さん・医療者のために、『がん医療における 患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン 2022年版』が発刊された
個別性の高い「コミュニケーション」の指針をガイドラインとして集約
医療におけるガイドラインとは、健康に関する重要な課題について医療者や患者さんの意思決定を助けるため、エビデンス(これまでに行われた研究の検証結果)を評価したうえで「最適」と考えられる推奨を提示する文書です。
がん領域でも、がん種別の診療ガイドラインが意思決定に使用されています。今回、『がん医療における 患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン2022年版』を作成するにあたり、私たちはある問題に直面しました。それは、「コミュニケーション」という個別性の高い(人によって好みが分かれる)ものを、「最適」を提示するガイドラインに落とし込む難しさです。
また、がん医療でのコミュニケーションの研究はエビデンスが少ないことも予想されました。そのため、従来のコミュニケーションガイドラインは専門家の意見(エキスパートコンセンサス)に基づくものでした。
ただ、専門家が推奨するコミュニケーションが患者さんの意向に必ずしも沿っていないことが先行研究で明らかとなり、少ないエビデンスでも、現在の知見をまとめて臨床に届けることが重要だと考え、ガイドライン作成に臨みました。ガイドラインの主な内容を表1に示します1。
表1『がん医療における 患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン 2022年版』の主な内容
総論
●患者-医療者間コミュニケーション
●がん医療におけるコミュニケーション
●特定の対象(高齢者、子ども)のコミュニケーション
●アドバンス・ケア・プランニング
臨床疑問(7問)
■患者-医療者間の対話促進
●臨床疑問1.がん患者が質問促進リストを使用することは推奨されるか?
▶推奨の強さ:1(強い)
●臨床疑問2.がん患者に意思決定ガイド(Decision Aids)を使用することは推奨されるか?
▶推奨の強さ:1(強い)(早期がん)
2(弱い)(進行がん、終末期がん)
■医療者対象コミュニケーション技術研修
●臨床疑問3.医師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修(CST)を受けることは推奨されるか?
▶推奨の強さ:2(弱い)
●臨床疑問4.看護師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修(CST)を受けることは推奨されるか?
▶推奨の強さ:2(弱い)
■面接特定場面のコミュニケーション
●臨床疑問5.根治不能のがん患者に対して抗がん治療の話をするのに、「根治不能である」ことを患者が認識できるようはっきりと伝えることは推奨されるか?
▶推奨の強さ:2(弱い)
●臨床疑問6.抗がん治療を継続することが推奨できない患者に対して、今後抗がん治療を行わないことを伝える際に「もし、状況が変われば治療ができるかもしれない」と伝えることは推奨されるか?
▶推奨の強さ:2(弱い)
●臨床疑問7.進行・再発がん患者に、予測される余命を伝えることは推奨されるか?
▶推奨の強さ:2(弱い)
*「推奨の強さ」について
・「推奨の強さ:1(強い)」は、臨床疑問の内容について実施する/しないことを「推奨」するもので、「推奨の強さ:2(弱い)」は「提案」するもの。「重大なアウトカム(医療の成果・結果)に関するエビデンスの確実性(強さ)」「益と害のバランス」「患者の価値観・希望」「コスト・臨床応用性」などの基準を考慮して決定されている。
(文献1を参考に作成)
ガイドライン使用時の注意点とねらい
●本ガイドラインは画一的なコミュニケーションを推奨するものではない
●患者さんの価値観や意向を尊重したコミュニケーションを行うなかで、状況や場面に応じて本ガイドラインの推奨や会話例が活用されることを意図している
7つの臨床疑問からよりよいコミュニケーションのあり方を検証
ガイドラインでは7つの臨床疑問(CQ)*1を取り上げました(表1)1。臨床疑問1・2は患者さんを支援するコミュニケーションプログラム、臨床疑問3・4は医療者を対象としたコミュニケーション技術研修プログラム、臨床疑問5・6・7は臨床で医療者が悩む面談場面のコミュニケーションについてのものです。
臨床疑問1~4は、エビデンスがある程度蓄積されている領域でした。なかでも、臨床疑問1の「質問促
進リストの使用」は強く推奨されます。質問促進リストとは、病状や治療、治療中の生活などに関する質問例をあらかじめ記載したリストです(表2)2。
* 1【CQ】clinical question:臨床疑問。臨床のなかで見いだされ、ガイドラインで取り上げることが決定した重要な課題について、疑問文のかたちで表現したもの。
表2 質問促進リストのパンフレットに掲載されている質問例(一部)
診断について
1診断名は何ですか?
2 病期(病気の進み具合)は?
病状について
3 私はどこが悪いのですか?/どのくらい深刻ですか?
4 がんはどこにあるのですか?
5 それはどの検査でわかったのですか?
症状について
6 今後どんな症状が起こりえますか?
7 今後起こりえる症状に対する治療にはどんなものがありますか?
検査について
8 もっと検査する必要はありますか?
9 もしそうならその検査は痛いですか?
10 それで何がわかるのですか?
(文献2より引用)
このリストを使うときは、患者さんは医師との面談の前に尋ねたい質問に印をつけ、記載されていない質問を書き込むなどして面談に臨みます。重要な話し合いの前に患者さんに渡すだけのシンプルな介入ですが、有用性が評価されており、質問数を増やすこと、患者さんの精神的苦痛を強めないことが確認されています。国立がん研究センターがん情報サービスのホームページから無料で入手できるので、すぐに使うことができます。
質問促進リストの入手方法
●国立がん研究センターがん情報サービスのホームページにアクセス
https://ganjoho.jp/public/index.html
↓
●「診断と治療」→「治療にあたって」にアクセス
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/dia_tre_diagnosis/index.html
↓
●「冊子『重要な面談にのぞまれる患者さんとご家族へ』」にアクセス
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/dia_tre_diagnosis/question_prompt_sheet.html
↓
●ページに記載されているリンクから、「重要な面談にのぞまれる患者さんとご家族へ」をダウンロード!
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/psychiatry/psychiatry_panfu.pdf
看護師がコミュニケーション技術研修(CST)を受けることの大きなメリット
●看護師がCSTを受講することは、患者さんの精神的苦痛の改善につながる
●看護師がCSTを受講することは、看護師のコミュニケーションに関する患者さんの満足度を向上させる
コミュニケーション技術研修プログラム(CST)の効果とは?
もう1つ、『エキスパートナース』読者の皆さんに提案したいこととして、臨床疑問4で解説されている「看護師対象のコミュニケーション技術研修プログラム(CST*2)」の受講があります。看護師がコミュニケーション技術研修を受講することは、患者さんの精神的苦痛の改善につながること、看護師のコミュニケーションに関する患者さんの満足度を向上させることが確認されました。
現在、国内で受講可能なCSTの研修会は、国立がん研究センターが開催する“公開がん看護研修「コミュニケーションスキル」”です。患者さんの感情表出を促進するためのコミュニケーションスキル、「NURSE*3」の習得をめざす研修会で、年2回開催されています。2025年度の詳細は、国立がん研究センターのホームページに掲載予定です。現在看護師が受講可能なCST研修会が限られており、受講資格も限定されているため、今後は多くの看護師がCSTを受講できるような取り組みが求められています。
*2【CST】communication skills training
*3【NURSE】naming:命名、understanding:理解、respecting:承認、supporting:支持、exploring:探索 の 5 つの要素の頭文字をとった、看護師のためのコミュニケーションスキルの名称。
実践に応用できる、さまざまな会話例も掲載
臨床疑問5~7(特定の面談場面でのコミュニケーション技術)はエビデンスが乏しいものの、臨床においてとても大事なコミュニケーションとして、現在の知見だけでなく、医療者が悩む場面のさまざまなコミュニケーション例(会話例)を掲載しています。具体的な言葉かけや注意点を示し、実臨床で使用しやすいかたちにまとめています(下記)。ぜひ、本ガイドラインを手にとって、目の前の患者さんにとっての「最適」なコミュニケーションを考えてもらえればと思います。
ガイドラインで取り上げている医療者と患者さんのコミュニケーション例の一部
臨床疑問5・会話例①(患者さんのがんが“根治不能”だと伝える場面)
(患者さんからの質問から会話開始、腫瘍医が患者さんの病状理解について確認)
患者:病状の説明をいただいたときに、転移もあるとのことでしたが、最近は有効な薬も出てきているとのことですので、100%ではないでしょうが、何とか治すことができればと思っています。
腫瘍医:なるほど、(少し沈黙)少しがっかりなさるかもしれませんが、がんを消し去ることは非常に難しいです。けれども、最近の医療の進歩によって、もし検査であなたに合った治療法がみつかれば、治療を続けることによって年単位で治療を続けながら暮らしている方も増えてきています。
科学的な視点と患者さんの視点の両方から、事実を伝える事象とともに「時間軸の要素」を考慮しながら、根治不能であることをどのようにはっきり伝えていけばよいか考えていく姿勢が重要かもしれません。
(文献1を参考に作成)
臨床疑問7・“I”messageを使い、患者の希望を支え心配ごとを一緒に考えていく言い方(患者さんに余命の話をする場面)
医療者:私としても、本当に○○さんがよい状態で長く過ごしていかれるといいなと思っています。同時に、個人的に少し心配なこととして、数カ月より先は見通しにくいかもしれないということがあり、そのような場合にも備えておいたほうがいいかもしれません。
“I”messageは、「私」を主語にして望みや懸念を伝える方法です。患者さんの希望を支えつつ、医療者も同じ方向を向きながら心配ごとを一緒に考えていく工夫の1つとして、日常診療でも使われています。
(文献1を参考に作成)
- 1.日本サイコオンコロジー学会,日本がんサポーティブケア学会編:がん医療における 患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン 2022年版.金原出版,東京,2022.
2.国立がん研究センター東病院 臨床開発センター 精神腫瘍学開発部:重要な面談にのぞまれる患者さんとご家族へ ─聞きたいことをきちんと聞くために─.
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/psychiatry/psychiatry_panfu.pdf(2025.2.13アクセス)
※この記事は『エキスパートナース』2023年4月号の記事を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。