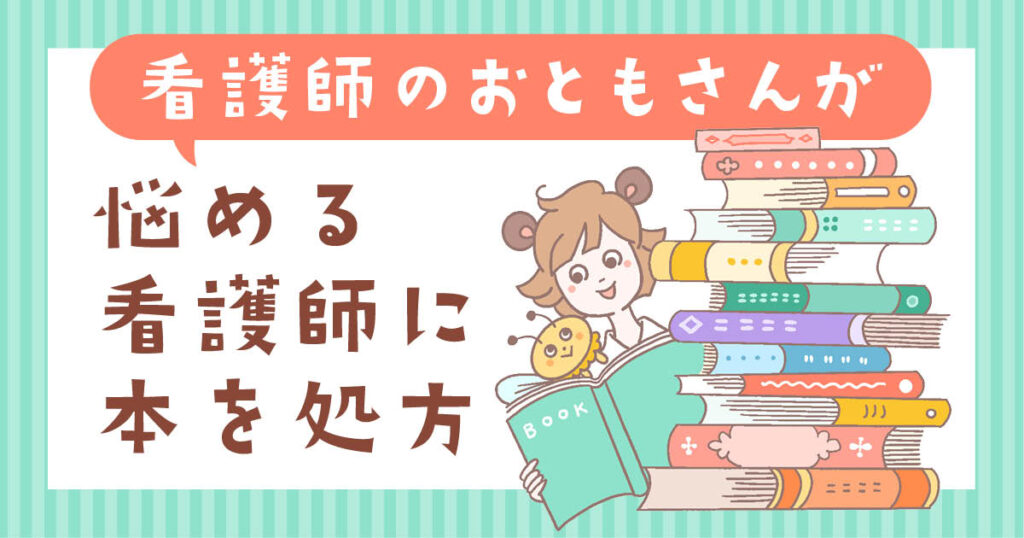本が大好きな看護師のおともさんが、“あなた”に寄り添った本を紹介するブックセラピー企画。看護師さんのさまざまなお悩みに合わせて、相談者にぴったりな書籍を教えてくれます。「救急外来での帰宅支援」に悩んでいるナースへのおすすめ本とは?
看護師のおともかんごしのおとも
救急外来部門・シミュレーションセンターで主任を務める看護師。実家も今の家も、本だけで丸々1部屋を使ってしまっているほどの本好き。@99emergencycall
はじめまして、急性期病院で働く看護師です。おともさんと同じく救急で働いています。入院まではいかなくても、頻回受診される患者さんの支援が日々難しいなと感じています。退院調整の本は読んだのですが、今の現状と少し違うかなと思い、しっくりくるものがなかなかありません。救急からの在宅支援の参考になる本があれば、ぜひ教えていただきたいです。
入院も帰宅も難しい患者のディスポジション
白石 今回は救急外来での帰宅支援というのでしょうか、そのお悩みですね。
看護師のおとも
これはまさに『ディスポジション(Disposition)』の話ですね。ディスポジションは日本語だと『転帰』という言い方になって、看護師にはこちらのほうがなじみがあるかもしれません。簡単に言うと「この患者さんをどうするか」という話です。帰宅するか、入院するか。
医師とはよく「この患者さんのディスポジション、どうするの?」とディスカッションをします。「今はまだ痛みが強いので、もうちょっと様子を見て。症状の改善があれば帰そうと思います。でも、改善していなければ造影CTを撮って入院を考慮したいです」といったように、今後の方針を決めるんです。今回のお悩みは、最初から入院ではないケースの扱いについてですね。
白石 なるほど。入院までは必要ないけれど、頻回受診やそのまま帰宅するには難しいケースについての対応ですね。
看護師のおとも
そうです。これはいわゆる社会的な問題が絡んでくるケースが多いんです。最近救急でよくあるなと思うケースを挙げると、例えば腰椎圧迫骨折の患者さんがいたとします。入院してもできることは安静にして鎮痛剤を飲むくらいでメリットがないのですが、「帰りましょう」と言っても、患者さんは「動けない」と訴えます。
さらに「ご家族は?」と聞くと「いません、ひとり暮らしです」、「立てますか?」「立てません」、「食事はどうしていますか?」「いつも自分で買い物しています」、「食事を用意してくれる人はいますか?」「いません」……。
これでは「帰ったらどうするの」という状況になります。他にも入院するほどの病状ではないけれど、「施設で見るのはちょっと……なんとかなりませんか」「いや、でもうちもベッド満床で……」といった、微妙なケースがよくあるんです。
白石 わぁ……たしかに難しい問題ですね。そういったケースに対応するための本はあるんでしょうか。
看護師のおとも
おそらく質問してくださった看護師さんは、退院支援や退院調整の本を読まれたんだと思うんです。ケアマネジャーに連絡する方法とか、ソーシャルワーカーに連絡して調整する方法などについての本だと思いますが、「入院するほどではないけれど帰宅も難しい」という状況には合わなかったんでしょうね。
この「入院するほどではないけれど帰宅も難しい」というピンポイントの内容に対応できる看護の本は、僕の知る限り存在しないんじゃないでしょうか。帰宅した場合の簡単なフォローアップの伝え方や、入院・転院支援のための介入方法を紹介する本が中心で、「入院にも転院にもならない人をどうするか」という内容はあまりないんです。
医師向けの本から学べる視点をヒントに
看護師のおとも
そこでおすすめは、医師向けの本を参考にすることです。救急の医師はこういったケースも含めてマネジメントする手法を学んでいるので、彼らの視点から考え方のヒントを得ることができます。
まず1つ目は『救急外来でコミュニケーションに困ったとき読む本』です。勤務先に置いてあるので今は手元にないんですが、コミュニケーションに難渋するようなさまざまなケースが紹介されています。

救急外来でコミュニケーションに困ったとき読む本
舩越拓 編著
中外医学社
A5判
5,280円(税込)
白石 どのようなケースが取り上げられているんですか。
看護師のおとも
例えば「症状が完全に消えていないのに帰宅させていいの?~救急外来から自宅療養につなげる時に~」という章があります。また、「帰宅時の注意をうまく伝える方法と工夫」や「慢性症状が解決できない~困っているのはわかるけど~」といったものもあります。
基本的に「患者さんを帰す」ことが前提ですが、患者さんや家族が困るだろうなというときに、医師たちがどのように工夫して伝えているのか、どのように考えているのかがわかります。その他にも、怒っている家族への対処法や、救急外来でスタッフが怒りを感じたときにどうやって冷静さを取り戻すか、ACPの話、治療をどこまで行うかといった内容も含まれています。
白石 医師向けの本とのことですが、タイトルが少しポップな印象がありますね。
看護師のおとも
表紙のデザインもポップに見えるかもしれませんが、中身はけっこうガチですよ。非常に実践的な内容です。おそらく相談者さんが求めていることに一番近い内容が書かれているのは、この本じゃないかなぁと思います。
安全に帰宅させるための医学的な考え方
看護師のおとも
もう1冊おすすめしたいのが『帰してはいけない外来患者』です。これも医師向けの本ですが、非常に参考になります。
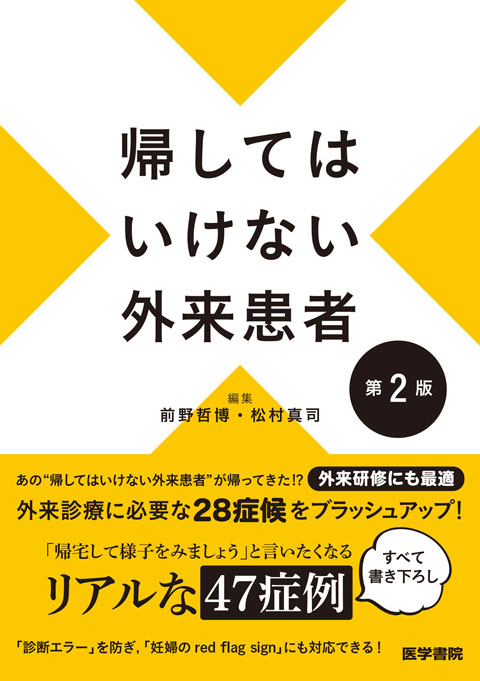
帰してはいけない外来患者 第2版
前野哲博、松村真司 著
医学書院
A5判
4,180円(税込)
白石 そもそも帰して大丈夫なのか?っていうタイトルですね。
看護師のおとも
いかにも危なそうなタイトルでしょう(笑)。内容としては、体重減少や咽頭痛、倦怠感など、救急外来でよく見られる主訴に対して、診断をどう進めるか、見逃してはいけない疾患は何か、絶対に外してはいけないポイントは何かという、医師向けの考え方が書かれています。
白石 なるほど。安全に帰宅させるために、見逃してはいけない症状や疾患をしっかり把握することも重要なんですね。
看護師のおとも
そうなんです。初版が出たのは2012年で、ちょうど僕が今の救急外来に転職した年。この本を買ったのは、当時は人手が少なく教えてくれる先輩もいなくて、もっと知識をつけておかないと、何か見逃したらマジでやばいという危機感があったからです。救急外来のトリアージや医師の診察の横で「自分でも何か気づけるように」「絶対見逃さないように」と思って買いました。
白石 たしかに、頻回受診の患者さんだと「いつものちょっと厄介な患者さんが来ちゃったよ」と、何か見過ごしてしまう可能性がありそうです。
看護師のおとも
そういったバイアスがかかることで、本当に重要な症状を見逃してしまう可能性もあります。「またいつもの胸痛か」と思ったら、じつは心電図でST上昇があったというケースは0ではないですからね。
看護師視点からのソーシャルケア連載も参考に
看護師のおとも
本の紹介とは少しずれるのですが、看護師視点での情報としては、医学書院の『医学界新聞』で以前連載されていた『めざせ「ソーシャルナース」! 社会的入院を看護する』という全20回の連載もおすすめです。「社会的入院を看護する」というテーマで、医師が書いたものです。
社会的入院に対応する際の考え方から始まり、家族の介護状況や治療・療養場所の考え方、家族に対する看護師の役割などが書かれていて、最後はバーンアウトしないための医療者の心のケアについても触れています。
白石 私も読んだことがあります!無料で読めるのはすごいなぁと驚きました!
看護師のおとも
実際、救急外来に勤務する看護師のなかには、超急性期をやりたい、人を助けたい、ドラマ的な劇的救命をしたい、そういうカタルシスを求める人たちも少なくないと思います。でも現実には、そういうドラマチックな場面が日々起きるはずもなく、よくあるコモンディジーズの話としては、入院が必要ないけれど帰る手段にも困っている患者さんや、社会的入院が必要な患者さんのケースのほうが多いんです。そういう意味で、この連載は非常に参考になると思います。
今回、看護師のおともさんが紹介してくれた本
『救急外来でコミュニケーションに困ったとき読む本』
『帰してはいけない外来患者 第2版』
『医学界新聞 めざせ「ソーシャルナース」! 社会的入院を看護する』※web記事
日々、患者さんに寄り添うあなたにも、やさしく寄り添うものがあってほしい。今回紹介した本たちが、そんなあなたの心の“おとも”になれることを願っています。
看護師のおともさんに、「悩みに合う本を教えてほしい」という方を募集中。
下記URLよりご応募ください。
※掲載の有無はエキスパートナース編集部で判断し、掲載有無の結果は事前にご連絡はいたしません。
https://questant.jp/q/book_therapy_otomo
※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。