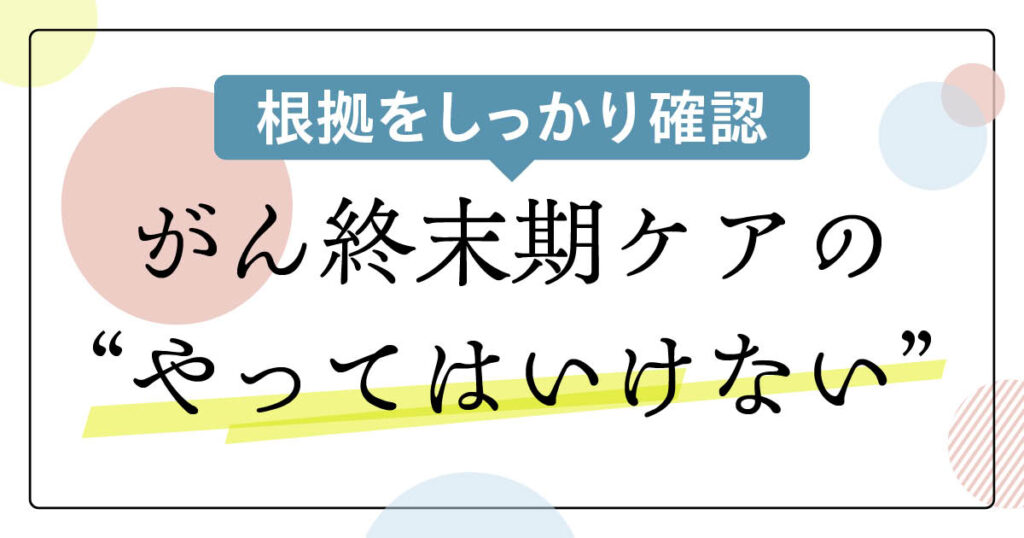がん終末期では経口摂取がなくても排便コントロールが必要です。便秘は食欲不振や嘔吐、せん妄の誘因になります。便秘の原因や排便アセスメントのポイントをわかりやすく解説します。
「がん終末期ケアの“やってはいけない”」の連載まとめはこちら
経口摂取していなくても、排便コントロールを怠ってはいけない
〈理由〉食べていなくても便秘は起こり、食欲不振や悪心・嘔吐、せん妄などの誘因になるから
便秘はがん患者さんにおいて高頻度に起こり、患者さんのQOLを低下させ、場合によっては痛みよりも大きな苦痛を引き起こす可能性があります。
しかし、医療者は、「食べていないから便が出なくても大丈夫」と便秘を過小評価してしまう傾向にあります。食事がとれないときでも、腸からの分泌物、粘膜表面の落屑、腸内細菌などのため、排泄は起こります。
便秘を見過ごし放置しておくと、食欲不振、悪心・嘔吐、 腹痛(疝痛)、 排尿困難、 尿失禁、 せん妄の誘因となってしまいます。
便秘の定義とは?
便秘の定義を、表11に示します。
表1 便秘の定義
●便秘とは、患者の主観的な感覚で、便が長いあいだ腸管内に停滞したために、水分が減少して硬い状態(宿便)になり、排便に困難を伴う状態を指す
●2~3日に1回しか排便がなくても、便の硬さが普通であり、排便に困難を感じないときには便秘とは考えられない
●逆に、毎日少量の排便があっても、それが硬く、排便に努力と苦痛を伴い、腹部膨満感などの不快症状を伴うものは便秘と考えられる
(文献1より引用)
排便のアセスメント方法は?
終末期では75%のがん患者さんに便秘がみられ、便秘の予防や何らかの排便処置が必要となっています2。
排便習慣は個人差が大きく、客観的評価だけでは不十分であり、患者さんの主観的体験に基づいて便秘の評価をしていくことが必要です。排便のアセスメント(表2)をして便秘の予防に努めることや、下剤を適切に使用することが大切です。
表2 排便のアセスメント
1)患者に確認すること(主観的体験)
●それまでの排便習慣や最終排便の日時
●排便状態(回数、便の硬さ)
●排便時の仏痛や便失禁の有無
●血液や粘液を伴うか否か
●排便に有用な要因はあるかの確認
2)治療など医学的な背景(客観的評価)
●病態
●現在使用している薬剤
●下剤の種類や量などの使用状況
●坐薬や浣腸の使用状況や頻度
(文献2を参考に作成)
がん終末期の便秘の原因は?
この記事は会員限定記事です。