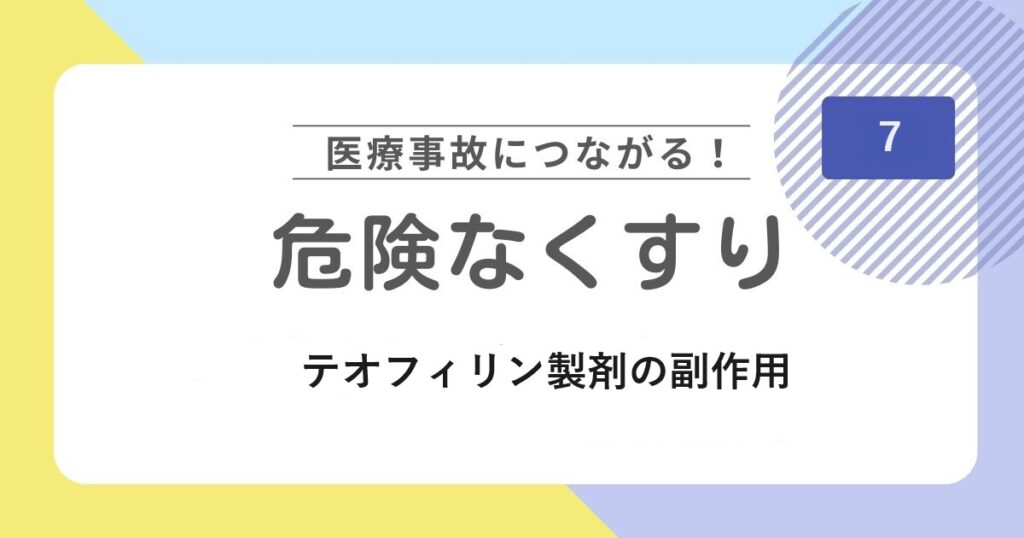医療事故につながる可能性のある危険な薬に注意!今回はハイリスク薬の1つである、テオフィリン製剤を取り上げます。けいれん、意識障害、不眠などのリスクや、使用時の注意点、正しい使い方を解説します。
テオフィリン製剤の危険性とは?
テオフィリン製剤は気管支拡張作用をもつ薬剤で、気管支喘息や気管支炎に使用されます。
テオフィリンは、もともと植物由来の成分であり、カカオ豆やお茶の中にわずかに含まれています。お茶やコーヒーに含まれているカフェインやカカオ豆に含まれているテオブロミンは、テオフィリンと化学構造からみると骨格が類似しています(キサンチン誘導体と呼ばれる、いわば兄弟みたいな存在)。
類似した骨格があると、似たような作用が生じます。カフェインが眠気防止になるということはご承知のことと思いますが、テオフィリンも同じような中枢神経興奮作用をもっているということです。
薬理的には少しずつ作用の程度が異なっており、中枢神経興奮作用はカフェインが最も強いですが、気管支拡張作用はテオフィリンが最も強力です1。
しかしカフェイン同様、中枢神経興奮作用を有するため、過量投与によりけいれん、意識障害、不眠などのリスクがあります。また、ほかにも胃酸分泌亢進作用により消化性潰瘍による消化管出血の副作用もあります。
テオフィリン製剤を使用する際の注意点は?
テオフィリンの代謝は一般的には一定ですが、症例によっては投与量の変化によって血中濃度が大きく変動することもあります。その結果、上述の中枢神経興奮作用により、けいれん、意識障害などの重大な副作用が起きる可能性があるため、過量投与はもちろん、小児、高齢者には注意が必要です。
なかでも、2歳未満の熱性けいれんやてんかんなどのけいれん性疾患のある患者さんには特に注意が必要です。安全に治療できる血中濃度の範囲内の投与量を定めるため、薬物血中濃度モニタリング(TDM)も推奨されています。
以下に、薬物血中濃度に影響を与えないよう注意したい点について解説します。
1)テオフィリン製剤の代謝に影響する薬剤の併用に注意する
胃潰瘍などに用いられるシメチジン(タガメット®)や抗菌薬のエリスロマイシン(エリスロシン®)などの併用により、テオフィリン製剤を代謝する酵素であるチトクロームP-450が阻害されます。それによりテオフィリン製剤の代謝も抑制されるため、血中濃度が上昇する可能性があります。
2)徐放製剤をすりつぶして使用しない
テオドール®、テオロング®、ユニフィル®LA、ユニコン®といった、テオフィリン製剤の内服薬の多くは、顆粒剤やドライシロップ剤も含め徐放製剤(剤の有効成分を徐々に放出し、血中濃度が一定に保てるよう設計された薬剤)です。
したがって、経管投与の際や嚥下困難な患者さんに対して投与する際に安易にすりつぶしたりすると徐放のしくみが破壊され、血中濃度の上昇が起こる可能性があるため、注意が必要です。
3)アミノフィリンの注射薬から経口薬に変更する際は、成分量の換算に注意する
テオフィリン製剤の1つとしてアミノフィリン注射液(ネオフィリン®、キョーフィリン®)がありますが、アミノフィリンは、水に溶けにくいテオフィリンを溶解させるために溶解補助剤としてエチレンジアミンを一定量加えたものです。
したがって、アミノフィリン注射液から経口のテオフィリンに切り替える際は、薬効を示さないエチレンジアミン相当分を差し引き、アミノフィリン250mg=テオフィリン200mgに換算して投与しなければなりません。
この記事は会員限定記事です。