退院後、以前入居していた施設に戻る予定の患者さん。生活上で注意すべきポイントを施設スタッフにうまく引き継ぐため、退院支援における多職種連携のポイントを考えていきます。
退院して施設に戻る患者さん。施設への注意点を円滑に伝えるには?
●80歳代後半・女性
●発熱があり、痰の量が増えたことで外来受診。誤嚥性肺炎の診断で入院となった。
●既往に高血圧、右変形性股関節症(10年前に人工骨頭置換術を施行)。
●半年前にも誤嚥性肺炎で3週間ほど入院した経緯がある。入院前は有料老人ホームに入所。認知機能に問題はなく、施設では杖歩行で身のまわりのことはできていた。
●夫とは死別しており、子どもはいない。家族は10歳年下の妹がいるが、県外在住のため、入院時と退院時に訪れる程度。
●入院から1週間は抗菌薬投与・酸素投与にて治療を行った。ベッド上安静にて、リハビリは病室内で行い、見守りありでポータブルトイレを使用。食事はきざみ食にとろみをつけたもので、言語聴覚士(ST)が介入している。
●2週間が経ち、肺炎所見に改善がみられていたが、治療に伴いベッド上安静が続いた。そのため、現段階で杖歩行はできず、歩行器でようやく移動できるレベル。
●もともと問題がなかった認知機能にも低下が見られており、ナースコールを押さずに歩行器で歩こうとする場面があるため、センサーマットを必要としている。さらに、食事をとったことや薬を飲んだことを忘れる場面も出てきている。
●今後はもともと入所していた有料老人ホームへと退院予定で、トイレは歩行器を使用しつつ自立してできなければならず、服薬管理も自己にて行う必要がある。また食事や飲み物についても、個別対応が必要になるが、施設側にお願いをしても断られる状況になっている。
※事例は、メディッコメンバーの経験に基づいて設定した架空のものです。

たみお
たみお
理学療法士(PT)、11年目。慢性期病院での外来リハビリテーションを経験し、現在は訪問リハビリテーションに従事している。

みややん
みややん
言語聴覚士(ST)、11年目。急性期、回復期病院での勤務経験を経て、現在は訪問事業所で勤務。病院と在宅とでの立ち振る舞いの違いを肌で感じている。

かなこ
かなこ
看護師、11年目。内科病棟での勤務経験ののち、現在は手術室看護師として勤務している。
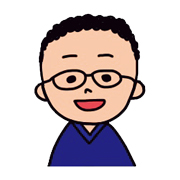
おぬ
おぬ
社会人経験を経て看護師になり、10年目。精神科では7年目。脳外科、回復期リハビリテーション病棟、在宅看護を経験し、現在は精神科救急病棟で勤務。

ぽりまー
ぽりまー
薬剤師、6年目。3年間、薬局薬剤師を経験後、現在は医療系メディアの編集部に勤務。前職で職場間・職域間の連携に問題意識をもったのをきっかけにメディッコに入った。
メディッコメンバーの視点
たみお(理学療法士) 今回のように、離床したくてもできずにADL能力が低下してしまう患者さんは、現場でもよく見ますね。
誤嚥性肺炎を繰り返すたびに運動機能は低下してしまうので、今後も繰り返さないように施設と連携をとっていきたいところですが、認知機能の低下も見られているため難しい症例だと思います。
みややん(言語聴覚士) 年齢と既往からみて、今後も誤嚥性肺炎を繰り返す可能性が高いケースですよね。施設(有料老人ホーム)では食事形態がある程度決まっていますし、食事介助の方法や注意点を細かく伝えても、施設内で周知しきれないことが多いと思います。施設のマンパワーや特色も、こちらで理解する必要がありますね。
かなこ(看護師) 施設に戻ることになったとき、病院での対応をそのまま引き継ぐことが難しいケースは過去に何度もありました。施設には施設の事情があるので、病院が一方的に意見するのではなく、双方で話し合い、患者さんにとっての最良を見つけていけるとよいですね。
おぬ(看護師) 施設にもよりますが、僕の経験でも入院を経てADLと認知機能が低下してしまい、再入所が難しくなり、別の施設を探すところからスタートするケースがありました。
また、退院後は服薬の自己管理が求められますが、今のままだと飲み忘れが多くなりそうなので、それにどう対応していくかも課題です。
入院中にけがなどをしないよう十分注意して、これ以上ADLが低下しないよう気をつけなければいけませんね。
ぽりまー(薬剤師) そうですね。確かにこの患者さんは、認知機能の低下による服薬管理での懸念があります。
一方で、既往は高血圧と右変形性股関節症(人工骨頭置換術によって治療)のみで、高齢なこともあり、退院後の定期処方は服薬回数も種類もそんなに多くなさそうな印象です。考えられるのは、降圧薬と鎮痛薬、便秘薬あたりでしょうか。
また、患者さんが睡眠薬を服用している場合、それが認知機能に影響を与えることもあります。看護師さんには、患者さんに睡眠薬を渡す際、薬剤の種類と用量、飲んだ日付と時間を記録しておいてもらえると、薬剤師としてはとても助かります。
入院前には認知機能に問題がなかったということなので、認知機能の低下はもしかしたら一時的なものかもしれないですよね。患者さんの現状をしっかり評価したうえで、施設と相談できるとよいのかなと思いました。
それぞれの職種が解決に向けてできること
みややん(言語聴覚士) 誤嚥性肺炎を繰り返さないために、STとしては食事形態やとろみのつけ方、食事姿勢などを検討する必要がありますね。そう考えると、退院してからも注意してもらいたいことはたくさんあります。
しかし、施設に対してあまり多くの注意点を伝えても、「対応しきれない」と門前払いをされてしまうこともあります。そのため「これくらいなら守れそう」と思ってもらえるように、相手の立場に立った申し送りが必要だと思います。
例えば、STからは「使用するスプーンは小さいものにしてほしい」「水分には必ずとろみをつけるようにする」「食事中は食事に集中できるように、話しかけるのではなく見守るようにする」と伝えるなどでしょうか。
また、施設側のスタッフとして介護士さんや助手さんが対応することもあるため、他職種に通じにくい専門用語などは使わないように気をつけるとよいです。常日ごろから、自分たちが使っている言葉が一般的に伝わる言葉かどうかを考えながら、こちらの考えがなるべくストレートに伝わるよう、工夫できるとよいと思います。
たみお(理学療法士) この患者さんは、まだ入院前の歩行能力まで改善しておらず認知機能も低下しているため、このままの状態で施設に帰るとなると、転倒リスクが高いと考えざるをえません。
PTとしては、退院前に施設と相談して、転倒しにくいような環境設定を提案することが多いです。例えば、次のよなうものです。
●「歩行器を使いましょう」などのわかりやすい張り紙を目に入りやすいところに設置する
●トイレまでの道順を床にテープで示す
それでもリスクが高そうな場合は、伝い歩きができるように家具の配置を調整するなどの工夫も提案します。個別に状態を把握してから提案することを考えるので、このような事例で退院支援に困っている場合は、気軽にPTに相談してほしいです。
また、入院中から環境設定を施設に近づけておくと、患者さんが施設に戻ってからも新しい環境になじみやすいと思います。退院を見越して先手を打っておくことも重要ですね。
……とはいっても、施設ごとに居室の形状やマンパワーが違います。情報をケアマネジャーや施設職員などから幅広くリサーチして、実現可能な対策を考えることもPTの腕の見せどころです。
かなこ(看護師) このあとすぐに退院というわけではないと思うので、退院可能な時期の目安を医師とともに確認したうえで、他職種と相談する必要があると思います。
例えば、医師や薬剤師さんとは「内服は1日1回だけで大丈夫か」「1回だけなら自己管理が可能か」などを確認します。トイレの自立に関しては、PTさんとADLの状況を確認しましょう。ほかにも「病棟内で認知機能が低下していても、トイレとハッキリ書いてあれば行くことが可能なのか」など、施設での生活に合わせるようなかたちで、どこまでできそうかをそれぞれに確認します。
実際の様子についてはケアマネジャーさんや施設ともやりとりをし、その状況をふまえて施設で受け入れるために何ができるか、患者さんにとってどうするのがよいのか、本人も含めてすり合わせていけるとよいのではないかなと思います。
ぽりまー(薬剤師) 服薬管理でいうと、誤嚥性肺炎の治療中はほぼ看護師さん主体で行っていたかと思いますが、回復後は退院を見据えた管理方法にシフトしていく必要があります。ただ、急に切り替えるのは難しいですよね。
まずは、受動的な服薬から主体的な服薬に向けて、前向きになれるよう習慣づけの練習ができるとよいのではないでしょうか。病院から施設に移る際、意外とハードルになるのが、調剤方法の違いです。
今回の患者さんは、もしかしたら入院前はPTPシートから服薬できていたかもしれませんが、入院中はほとんどの場合、一包化されていますし、認知機能を考慮すると退院後も一包化を継続するほうが現実的です。なので、施設や、施設の担当薬局に一包化の際の調剤ルール(日付の有無、服用時間に応じた色分けなど)を確認すると、実践的な服薬管理の練習ができると思います。
もちろん、看護師さんだけで抱え込まず、調剤ルールについてはぜひ薬剤師に相談してみてください!病院にはたくさん薬剤師がいるので、こういう相談に喜んで乗ってくれる薬剤師がきっといるはずです。
おぬ(看護師) やっぱり、施設との情報共有が大切かなと思います。そのためにはMSWと連携し、現在の患者さんの状態を伝えます。そして、どこまでなら施設側で対応可能か、担当のケアマネジャーさんと再検討し、そのうえで、現在の施設で対応が難しいのであれば、別の施設を探す選択肢もあると思います。
日々、患者さんと接している看護師だからこそ、患者さんの情報をいっぱいもっているので、どんどん情報共有していったほうがよいですね。このまま元の施設に戻るとしても、日常生活の援助や服薬管理に関しては訪問看護を導入し、服薬状況を確認できる体制が必要です。
また、10歳年下の妹が県外にいるとのことですが、身内がこの方しかいない場合は、施設の決定や今後についてどれぐらいかかわってくれるかもポイントになるかと思います。いろいろな社会資源を活用すれば、患者さんがよりよい生活を送れると思うので、そのためにも情報共有と連携が必要ですね。
*
それぞれの病院の事情があるように、施設にもさまざまな事情があることが伺えます。それをふまえて、お互いにベストではなくともベターなところはどこなのか、患者さんや家族を含めて話ができるといいですね。
この事例のまとめ
●施設によって事情が違うので、退院にかかわるスタッフみんながもっている情報を集めたうえで、患者さんにとって何が最良なのかを考える。
●他施設との連携では難しい専門用語は使わず、お互いが理解できる言葉を選ぶ。
●安全に、かつ相手方の施設が続けていける方法を伝えていく。
●1人の患者さんに使える時間が限られているのも現実。「何を提案するか」も大事だが、「どう伝えるか」も重要。
この記事は『エキスパートナース』2021年1月号連載を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
以上の解決方法・対処例は、ケースをもとにメディッコメンバーが話し合った一例です。実際の現場では、主治医の指示のもと、それぞれの職種とこまめに連携をとり、進めていってください。







