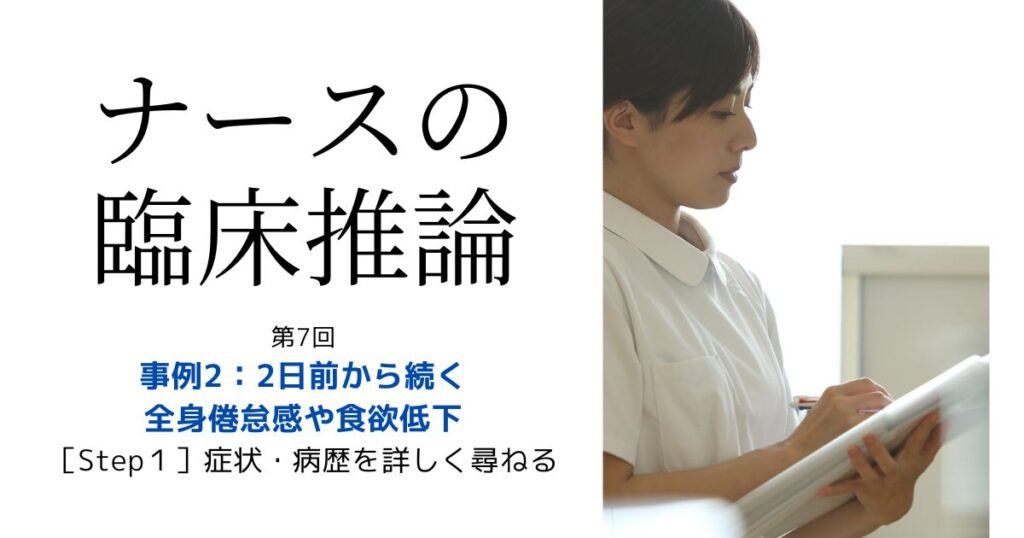患者さんの訴えの裏に隠された疾患を見逃さないために大切な「臨床推論」。どのような思考過程を経て臨床診断を導き出しているのかを考えていきます。今回は全身倦怠感や食欲低下を訴える患者さんの事例を紹介。まずは症状・病歴を詳しく尋ねます。
事例➁2日前から続く全身倦怠感や食欲低下を主訴に受診した女性
Bさん(70代・女性)は、娘夫婦との3人暮らし。ハイキングに行き、帰宅後は変わった様子はなかったが、翌日から食欲が減り、元気もない様子でした。その次の日も元気がなく、朝食・昼食も喉を通らず、昼寝から起きてこないため19時頃に娘が見に行くと失禁していました。最近の活力低下もあり、20時前に夜間外来を受診。全身倦怠感と食欲低下以外に症状はなく、家族は疲れのせいではないかと考えていました。既往は特になし。
その他の情報
●食事、排泄、入浴、買い物など身の回りのことはすべて自分で行える。
●1年前に高齢者検診を受診し、特に異常なし。既往や内服なし。
●受診時、他に明らかな症状(嘔気・嘔吐、便秘、下痢、最近の体重減少、集中力や興味の低下など)はなし。
●甲状腺機能低下症
●大うつ病
●栄養障害(ビタミンB1欠乏)
●副腎不全
●右心不全
●傍腫瘍症候群
●脳腫瘍
●敗血症
●膠原病
第1ステップ 症状・病歴を詳しく尋ねる
症状が発症したときのできごとや様子を確認する
Bさんは特に既往のない70代の女性であり、2日前からの全身倦怠感と食欲低下以外に特異的な訴えはありませんでしたこれだけで鑑別疾患を絞るのは難しいです。
その他にきっかけとなる特異的な病歴や外面の特徴がない場合、何か有用な情報がないか、さらに詳しく病歴を聞く必要があります。
特に注目すべき点として、以下が具体的に知りたい情報であり、これらの質問の答えが患者さんの問題の核心をつくことも多いです。
●発症様式(突然か、急か、数日かけて緩徐に起こったのかなど)
●発症の前後の状況
●起こった場所
●症状に気づいたきっかけは何だったのか
●本人や家族はその症状をどうとらえているか(解釈モデル)
患者さんの全体像を把握するような質問をする
患者さんの訴えをこれまでの人生や生活との関連から考える点で、患者さんの全体像を把握するような質問も効果的です。
Bさんは一見やや元気のない高齢女性といった印象で、こちらが話しかけると返答してくれるものの、受け答えはもうひとつはっきりしませんでした。同居している娘が最初に症状に気づいたきっかけは、2日前の朝、朝食を食べる量が少なかったことでした。
娘によると、普段と今では本人の元気さの度合いがまったく違うといいます。普段は快活で外交的な明るい性格であり、自宅では家族のなかで最もよく話す明るい人柄ということでした。生来、病気や入院などもしたことがなく、12年前に夫を膀胱がんで亡くしたときに寝込んだ以外は、気分が落ち込むこともなかったということです。
この記事は会員限定記事です。