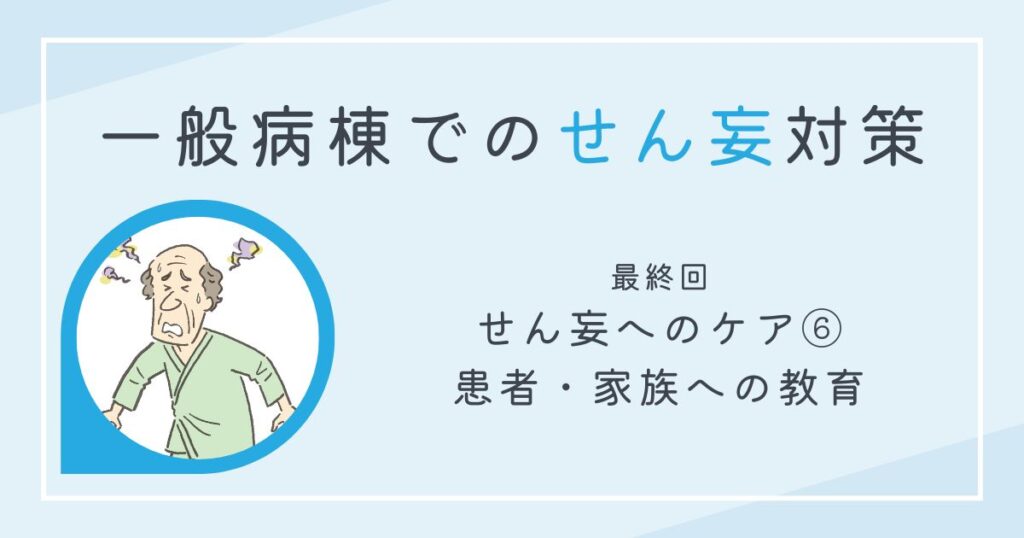せん妄のメカニズムを知れば、効果的な対応・ケアが見えてきます!今回はせん妄患者とその家族への教育と支援について解説。せん妄になりやすい要因や主な症状など、説明のポイントを紹介します。
せん妄が心理的な問題ではないことを、患者・家族に理解してもらう
医療関係者でも理解が難しいところのあるせん妄は、患者さんや家族にとってはより理解しがたいものです。いつもと同じ外見であるのに、不可思議な言動や、幻覚・妄想などで取り乱す姿は家族、そしてせん妄から回復した本人にとって心理的な苦痛になります。
人間は理由や原因を分析する特徴があり、せん妄を含め病気に対して自分の責任と感じ罪悪感を抱いたり、薬や医療者の問題に置き換えるなど、他責的な態度をとったりすることがしばしばあります。
しかし、原因が努力では改善できない身体疾患・外的要因と理解できれば、このような事態は避けられます。HELP1などせん妄予防プログラムでも教育を取り入れており、パンフレットなどでせん妄について患者本人、家族に説明・教育することが効果的です。
家族に説明しておくとよいこと
1)せん妄になりやすい要因(主なリスク)
- 高齢
- 脳卒中
- 認知症やせん妄の既往
- 薬、手術、感染症
※最近の物忘れ、以前の入院での異常な言動の有無も確認
2)せん妄の主な症状(わかりやすく伝える)
- 時間や場所の感覚異常
- 幻覚
- 睡眠リズムの異常
- 落ち着きのなさやイライラ
- つじつまが合わない言動
- 入院や治療を理解できず転倒する
- 点滴を自己抜去してしまう
この記事は会員限定記事です。