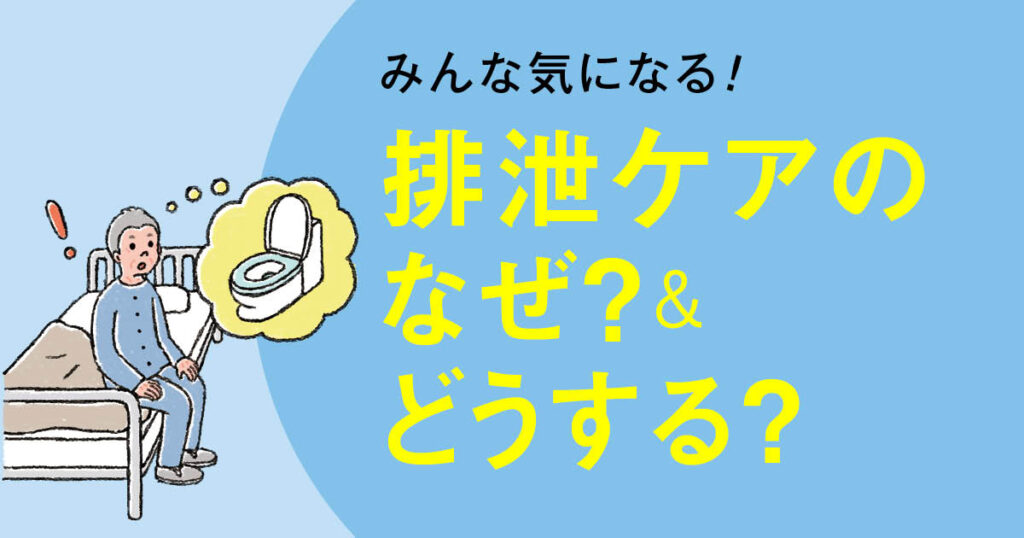腹部の手術前に浣腸が必要なのはなぜ?浣腸の種類、禁忌などの基本を確認しながら、排尿・排便のメカニズムを踏まえて解説します!
腹部の手術前に浣腸が必要なのはなぜ?
●腹部の手術では、術野や手術室の汚染防止、縫合不全や手術部位感染などの合併症を防ぐために浣腸を実施する。
●場合によっては実施しないこともあるため、対象に応じて確認しよう。
手術野の汚染の防止、合併症予防のために浣腸を行う
腹部、特に大腸の手術を行う際には、手術時の操作に伴う感染を予防するために、前処置が行われます。全身麻酔下での手術では、筋弛緩薬の使用によって肛門括約筋も弛緩するため、直腸内に貯留している便が排出してしまいます。
そのため、不意な排泄によって術野や手術室を汚染しないよう、腸管内を空虚にします。具体的な手段として、低残渣食摂取による腸管内容の減量、緩下剤の服用や浣腸による腸管内容の排除が挙げられます。
合併症を予防するために腸管洗浄を実施する
また、縫合不全や手術部位感染(SSI)などの合併症を予防するためにも、腸管内を清浄する腸管洗浄(mechanical preparation)を実施します。
直腸に機械的な刺激を加えることで便の排泄を促す浣腸は、前処置として一般的に行われるものですが、浣腸の手技による腸穿孔、グリセリン液による溶血などの報告もあり、慎重に行うべき看護技術でもあります 1。
整形外科、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺外科などでは、浣腸を施行した場合と術後の合併症について有意差がないとの報告もあり、浣腸を行わないケースが増えてきました。
腹部の手術においても低残渣食の摂取のみで浣腸などは省略する場合があります。 腸管前処置によって生じる頻回の下痢により、術前に体力を消耗してしまう可能性もあります。患者さんに応じた前処置(表1)2の必要性を考慮し、患者さんの理解を得ることが大切です。
表1 腹部手術の術式による腸管前処置の適応

浣腸の基本知識
浣腸とは、直腸に管を通し、腸の蠕動運動を活発にする液体を注入することで腸壁を刺激し、排便を促す方法をいいます。
浣腸の種類
一般的に浣腸といえば、排便を誘発させる目的のものを指しますが、それ以外を目的とした浣腸もあります(下記参照)3。
●排便浣腸…便の排出を促す
●駆風浣腸…排ガスを促す
●保留浣腸…水分を大腸壁から吸収させて補給する
●緩和浣腸…消炎鎮痛作用を目的に腸粘膜に薬物を注入する
●鎮静浣腸…鎮静を目的に麻酔薬や鎮静薬を注入する
●造影剤浣腸…大腸のX線撮影時、バリウムを注入する
浣腸の禁忌
浣腸の禁忌には下記のようなものがあります。
①腸管内出血、腹腔内炎症のある患者。腸管に穿孔またはその恐れのある患者
腸管外漏出による腹膜炎の誘発、腸管蠕動運動亢進作用による症状の増悪、グリセリン液の吸収による
溶血、腎不全を起こす恐れがある
②全身衰弱の強い患者
強制排便によって衰弱状態を悪化させ、ショックを起こす恐れがある
③下部消化管術直後の患者
腸管蠕動運動亢進作用により、腸管縫合部の離開をまねく恐れがある
④悪心・嘔吐または激しい腹痛など、急性腹症が疑われる患者
症状を悪化させる恐れがある
浣腸の種類
排便を誘発するしくみには、主にグリセリン浣腸と高圧浣腸の2つがあります。
グリセリン浣腸は浣腸の第1選択として多く用いられますが、グリセリン禁忌である場合やグリセリン浣腸で腸管洗浄が不十分な場合、S状結腸よりも口側の腸管を洗浄したい場合は、高圧浣腸を選択します。
グリセリン浣腸
少量の薬剤で腸壁を刺激し、蠕動運動を高め、排便を促します。潤滑剤としての作用によって硬便の排出を容易にするため、直腸内の宿便に対応します。
浣腸液には50%グリセリン液を用い、成人では60~ 120mL/回、小児では30~60mL(1~2mL/kg)/回使用します。
グリセリン浣腸では、ディスポーザブル浣腸器を使用します。注入速度は、60mLを使用する場合、15秒以上かけることが望ましいとされています。
高圧浣腸
浣腸液を下行結腸から横行結腸まで注入し、便を排出します。浣腸液には1~2%石けん液、0.9%生理食塩水、微温湯が用いられます。
成人では500~1,000mL/回、小児では250~500mL(10~20mL/kg)/回使用します。薬液量による結腸の到達部位は、150mLでS状結腸、500mLで下行結腸、1,000mLで横行結腸とされています。
高圧浣腸の薬液はイリゲーターに入れて使用します。肛門からイリゲーターの液面までの高さは、40~50cmです。 イリゲーターが高すぎると、注入速度が速くなります。注入速度は、100~200mLを1分以上かけることが望ましいとされています。最近では、ポンプで注入するペリスティーン®アナルイリゲーションシステムが導入されています。
(第1回)
- 1. 内藤知佐子:排便を促す援助.任和子,井川順子,秋山智弥編,京都大学医学部附属病院看護部編集協力,基礎・臨床看護技術 第2版.医学書院,東京,2017:127-137.
2. 清水拓也:下剤処置は“必要最低限”のみ施行する!.立石渉編,ナースができる!「ERAS ®(術後回復能力強化プロトコル)」.エキスパートナース 2015;31(15):75.
3. 山口瑞穂子監修:看護技術 講義・演習ノート 上巻 日常生活援助技術篇.サイオ出版,東京,2006:153.
- 1. 鈴木みずえ,片山はるみ編:なぜ? できる! わかる! 私の基礎看護技術.クオリティケア,東京,2016:103-105.
2. 山口瑞穂子監修:看護技術 講義・演習ノート 上巻 日常生活援助技術篇.サイオ出版,東京,2006.
3. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会編:ストーマ・排泄リハビリテーション学用語集 第4版.金原出版,東京,2020.
4. ストーマリハビリテーション講習会実行委員会編:ストーマリハビリテーション実践と理論.金原出版,東京,2006.
※この記事は『エキスパートナース』2019年9月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。