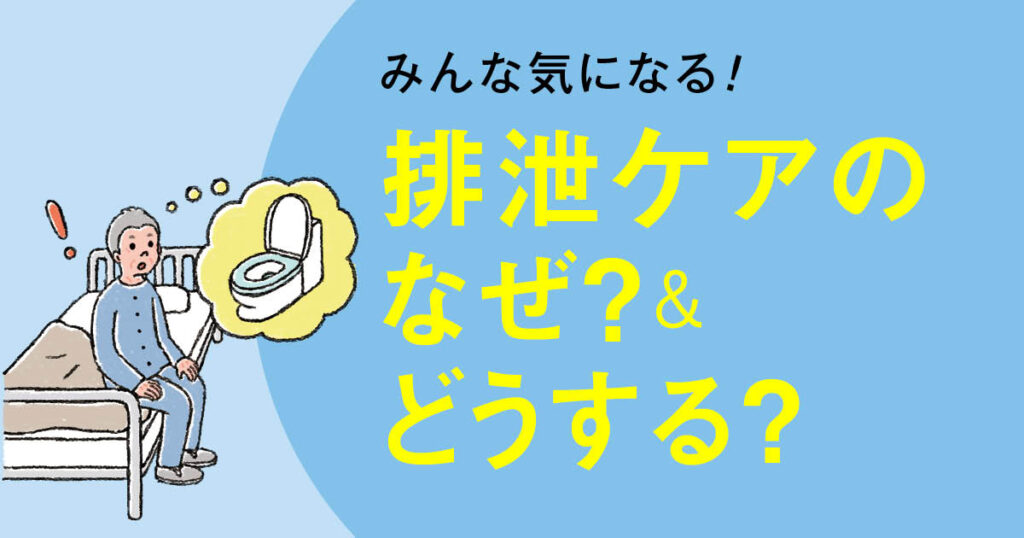看護の基本としてさまざまな場面で実践される排泄ケア。「なぜ」そのようにしているのか、本当に「どうする」のか、排尿・排便のメカニズムを踏まえて解説する全16回の連載です。
【第1回】腹部の手術前に浣腸が必要な理由
〈目次〉
●手術野の汚染の防止、合併症予防のために浣腸を行う
●浣腸の基本を確認しよう
・浣腸の禁忌
・浣腸の種類
【第2回】抗がん薬で便秘・下痢が起こりやすいのはなぜ?
〈目次〉
●便秘・下痢をきたしやすい抗がん薬の種類
●抗がん薬による便秘の原因
●便秘と腸閉塞/イレウスの鑑別に注意しよう
●抗がん薬による下痢の原因とケア
【第3回】オピオイド誘発性便秘(OIC)への対策はどうする?
〈目次〉
●医療用麻薬とオピオイドの違いは?
●オピオイド誘発性便秘(OIC)とは?
●OICに対する便秘対策の注意点は?
1 アセスメントに沿った治療を行う
2 適切な下剤を検討する
3 原疾患による影響を考える
4 オピオイドスイッチングを検討する
●非薬物療法などのケアも行う
【第4回】“3日間、便が出ないと下剤”は本当?
〈目次〉
●「3日間、便が出ないと下剤」といわれる理由は?
●便秘の定義とは?
●便秘の個別対応の方法は?
①便秘の陰に隠れた重大疾患の徴候を見逃さない
②排便回数の減少は便秘の一要素でしかない
③慢性便秘では「排便日誌」が役に立つ
④機能性便秘はタイプを分けて治療する
⑤刺激性下痢の乱用からの離脱を図る
【第5回】便秘の患者さんでX線画像を撮る理由
〈目次〉
●腹単では大腸内の便・ガスの量・形態・存在部位を確認
●便秘のアセスメントに必要な便生成の基礎知識
・結腸運動(ハウストラ形成)
・大蠕動
・大腸を支配する自律神経
・大腸の便貯留機能
●便秘症で腹単を撮影するときは臥位で実施する
●腹単での便は実質性の灰色に見える
●便の貯留のパターンをおさえよう
【第6回】便秘で下剤を使い分けるのはなぜ?
〈目次〉
●機能性便秘の種類による下剤の使い分け
①大腸通過正常型
②大腸通過遅延型
③便排出障害型
●主な下剤の種類と特徴
・新規便秘薬はここに注意!
●便秘治療に用いる外用薬
【第7回】尿道留置カテーテル挿入時に消毒するのはなぜ?
〈目次〉
●尿道留置カテーテルの挿入と細菌感染のリスク
●カテーテル挿入時の消毒・洗浄の方法
①挿入前の陰部洗浄
②尿道留置カテーテル挿入の準備
③尿道留置カテーテルの挿入時の消毒
④尿道留置カテーテルの挿入
⑤蓄尿袋の設置
【第8回】尿道留置カテーテルを早期に外す理由は?
【第9回】肛門括約筋機能が衰えていなくても、便失禁するのはなぜ?
〈目次〉
●便失禁の主な原因
・溢流性便失禁とは?
・漏出性便失禁とは?
●便秘を排除することも便失禁への対策となる
【第10回】排泄アセスメントで用いる代表的なスケールとは?
〈目次〉
●共通のスケールで排泄をアセスメントする重要性
●排泄アセスメントで用いる代表的なスケール
①ブリストルスケール
②King ’s Stool Chart
③IAD 重症度評価スケール:IAD – set
④排尿日誌、排便日誌
⑤ICIQ – SF
【第11回】便・尿失禁で殿部の皮膚が荒れるのはなぜ?
〈目次〉
●便・尿失禁で皮膚が荒れる要因
●皮膚炎が起こるメカニズム
●おむつによる皮膚トラブルに注意
●便・尿失禁に対するスキンケア方法
●失禁に伴う皮膚障害への対応
・スキンケアのポイント
・失禁ケア用品の選び方(洗浄剤の例、撥水性皮膚保護剤の例)
【第12回】排尿アセスメントでの情報収集方法とは?
〈目次〉
●排尿アセスメントでの情報収集のしかたは?
①排尿状態のアセスメント
②排泄動作のアセスメント
③既往歴のアセスメント
④生活環境のアセスメント
⑤影響要因のアセスメント
【第13回】排尿誘導の方法、排尿自立の進め方は?
〈目次〉
●残尿測定はどうして必要なの?
・膀胱用超音波画像診断装置の例
●排尿誘導の具体的な方法は?
・定時トイレ誘導
・排尿習慣化訓練
・排尿自覚刺激行動療法
●排尿自立を促すケア計画のポイント
●排尿自立に向けたケアで注意したい点は?
【第14回】クロストリディオイデス・ディフィシル腸炎で下痢をするのはなぜ?
〈目次〉
●クロストリディオイデス・ディフィシル腸炎とは?
●感染の原因は?
●どうやって治療する?
●ケアにはどんなことが大切?
【第15回】腸内環境のために乳酸菌が大切なのはなぜ?
〈目次〉
●腸内細菌叢の基礎知識
●腸内細菌叢のバランスを改善するには?
●乳酸菌製剤の特徴と使い方
【最終回】排便にとってトイレの高さが大切なのはなぜ?
〈目次〉
●トイレの歴史を紐解いてみよう
●座位姿勢と蹲踞姿勢の直腸-肛門角度の違い
●排便の影響を考えるうえで大切な骨盤付近の6つの筋肉
●姿勢別にみた骨盤にかかる外力
A.立位
B.直立・座位
C.体幹前傾・座位
D.蹲踞位
E.臥位
●便座の低いトイレは蹲踞位のよさを取り入れられる