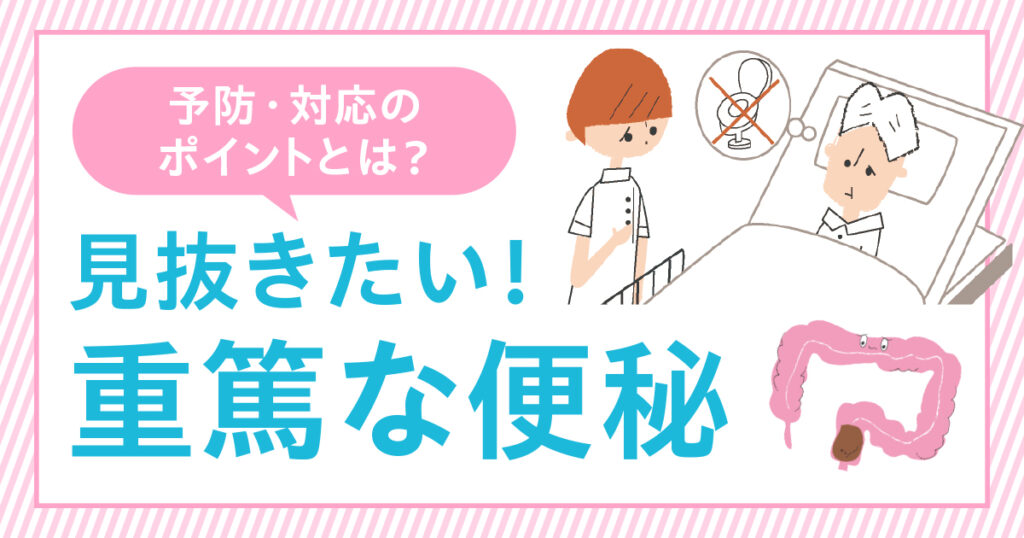便秘には、ときには重篤化する病態が潜んでいることも。今回は、下剤を服用しても便が出ない患者さんへの対応について解説します。
Q. 下剤を投与しても便が出ない場合はどうする?
Answer
●使用している下剤が適切なのか評価しましょう。
●本当に便がたまっているのか確認する必要があります。
下剤の種類と選択
私たちが「下剤」と呼んでいるものには、塩類下剤、膨張性下剤、糖類下剤、刺激性下剤というような分類がされており、それぞれで作用が異なります(表1)。
そのため、例えば下行結腸に便がたまっているのにガス産生により直腸を拡張させる下剤を用いてもその効果は弱いし、直腸にたまった便を出そうとして腸蠕動が亢進すると腹痛や下痢が出現することもあります。
特に、直腸内にたくさんの便が貯留している患者さんに、例えば刺激性下剤を投与しても、その便の脇から少量の液状便が排泄されるだけですっきり感が得られないこともよくあります(溢流性便失禁、第3回図2参照)。
下剤の使用にあたっては、患者さんの排便パターンや消化管機能を考慮して選択することが大切です。
表1 下剤の種類
浸透圧性下剤
〈塩類下剤〉
一般名/薬剤名:酸化マグネシウム/酸化マグネシウム、マグミット®
特徴:腸管内の浸透圧を高めることにより腸管に水分を保持することで便を軟化
※糖類下剤は、腸内細菌の代謝によって浸透圧効果をさらに強める(便秘症に対しては、少量投与を推奨)
適した状態:結腸通過時間遅延型、巨大結腸症
適さない状態:結腸通過時間正常型、腎障害、便失禁を併存
〈糖類下剤〉
一般名/薬剤名:ラクツロース/モニラック®
特徴:腸管内の浸透圧を高めることにより腸管に水分を保持することで便を軟化
※糖類下剤は、腸内細菌の代謝によって浸透圧効果をさらに強める(便秘症に対しては、少量投与を推奨)
適した状態:結腸通過時間正常型、便失禁を併存
適さない状態:結腸通過時間遅延型、糖尿病
禁忌:ガラクトース血症
膨張性下剤
一般名/薬剤名:カルメロースナトリウム/カルメロースナトリウム
特徴:便の量や水分含有量を増すことで膨張
適した状態:食欲正常で食物繊維摂取不足
適さない状態:結腸通過時間遅延型、巨大結腸症
刺激性下剤
一般名/薬剤名:センナ、センノシド、大黄/プルゼニド®、アローゼン®、大黄甘草湯
特徴:大腸の蠕動運動を亢進
適した状態:結腸通過時間遅延型、巨大結腸症
適さない状態:結腸通過時間正常型、大腸メラノーシス
一般名/薬剤名:ピコスルファートナトリウム/ラキソベロン®
特徴:大腸の蠕動運動を亢進
適した状態:結腸通過時間遅延型、巨大結腸症
適さない状態:結腸通過時間正常型
クロライドチャネルアクティベーター
一般名/薬剤名:ルピプロストン/アミティーザ®
特徴:小腸での水分分泌を促進することで便を軟化
適した状態:結腸通過時間正常型、腎障害
適さない状態:結腸通過時間遅延型
禁忌:妊婦
その他
一般名/薬剤名:浣腸、坐剤/グリセリン浣腸、新レシカルボン®坐剤、テレミンソフト®座薬※
特徴:直腸~下行結腸の蠕動運動を促進
適した状態:直腸に宿便がある直腸排便障害
適さない状態:結腸通過時間正常型
※テレミンソフト®坐薬は刺激性下剤の作用を有する
便があるのに出ない場合はどうする?
便が貯留しているにもかかわらず「出ていない;排泄されない」のは、大腸がんイレウスや腸捻転といった消化管閉塞や、特殊な例として今回の話題である糞便性イレウスが疑われるため緊急を要します。
その場合には腹痛や嘔吐といった症状を伴っていることが多く、ときに循環動態のアンバランスや血液データとして炎症所見の上昇など全身に影響を及ぼすこともあります。
また、「便が出ない」要因として、直腸から便をうまく排泄することができない病態があります。Outlet Obstruction(直腸排便障害*1)と呼ばれ、食事内容の工夫や下剤の調整をしてもスムーズに便を出すことはできません。
このような病態を有する患者さんは、便が排泄されていても残便感や排便困難などの不定愁訴が多くみられます。治療のひとつとしてバイオフィードバック療法や自律訓練法があり、排泄のしかたを見直すことが有用となります。
*1【直腸排便障害】奇異性収縮、直腸瘤、会陰下垂、直腸重積が起こることで、直腸からうまく便が排泄できなくなる状態。
便秘対策としての下剤投与は日常的に行われています。適切な薬剤選択と投与方法により、その効果が発揮されるようにしましょう。
排便日誌に記載する内容は?
便秘対策、つまり排便コントロールにおいて、日常生活や治療が排便に及ぼす影響を評価する必要があります。具体的には排便日誌として、排便時間や量、食事内容、腹部症状を継時的に記録します(表2)。また、客観的な評価として腹部X線検査や直腸診で便の貯留状態を確認します。
表2 排便日誌として記載したい内容
排便状況
●排便時間 ●性状
●量 ●随伴症状
食事状況(水分も含む)
●摂取時間 ●内容
●量
腹部症状
●腹部膨満感 ●腹痛
直腸肛門部症状
●肛門痛 ●残便感
入院患者に対して私たち看護師は、「1日何回排便がありましたか?」と必ず質問し看護記録に記載しています。この数字を、どのように活用しているでしょうか。便が出ていない場合、腹部症状の観察、そして便の生成につながるような食事摂取ができているかどうかを把握することが大切です。
体温、脈などの記録が重要
患者さんによっては、症状を訴えることができないこともあるため、腹部の視診 ・ 触診やおむつ交換を行う際の直腸診で、便が貯留していないか確認しましょう。
実際には、排便トラブルに対応する専門外来でなければ、「排便日誌」をつけることはほとんどないでしょう。しかし、そのような特別な記録をしなくても、ある程度の排便パターンを把握することは可能です。入院患者さんの体温、脈などを記載した記録こそがその人にとっての生活日誌であり、排便回数や食事量、さらに腹部症状といった便秘にかかわる情報が含まれています。
ふだんから便が出たか ・ 出ていないかについての確認にとどまらず、腹部症状(膨満、痛み)や肛門部症状(痛み、腫脹、出血、便の付着)を観察すること重要です。
(第8回)
- 1. 雪下岳彦:慢性便秘症例での薬物療法と一工夫.薬事 2016;58(1):61-65.
「便秘」についてもっと知るなら
●「見抜きたい!重篤な便秘」の記事一覧
●“3日間、便が出ないと下剤”は本当?
●便秘で下剤を使い分けるのはなぜ?
こちらもチェック!
●そのほかの連載はこちら
この記事は『エキスパートナース』2016年6月号特集を再構成したものです。本記事の無断転載を禁じます。個々の患者の治療開始前には、医師・薬剤師とともに添付文書およびガイドライン等を確認してください。実践によって得られた方法を普遍化すべく万全を尽くしておりますが、万一、本誌の記載内容によって不測の事故等が起こった場合、著者、編者、出版社、製薬会社は、その責を負いかねますことをご了承ください。