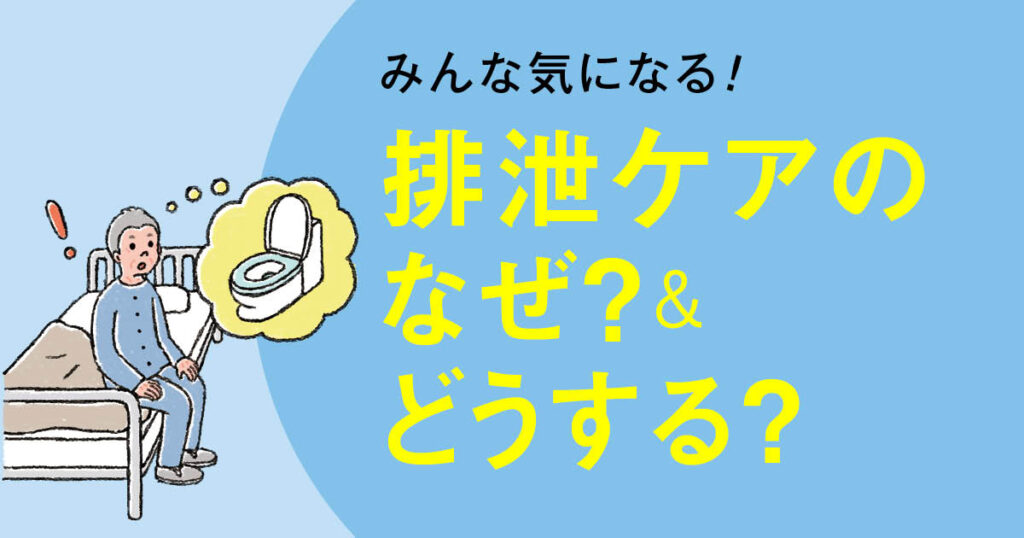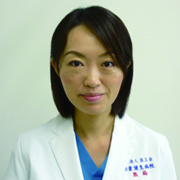機能性便秘は大腸通過正常型、大腸通過遅延型、便排出障害型に分けられ、それぞれの病態に応じた下剤を使い分けましょう。塩類下剤、糖類下剤、高分子化合物、刺激性下剤といった、主な下剤の種類と特徴、新規便秘薬について解説します。
この記事は『エキスパートナース』2019年9月号特集を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
個々の患者の治療開始前には、医師・薬剤師とともに添付文書およびガイドライン等を確認してください。実践によって得られた方法を普遍化すべく万全を尽くしておりますが、万一、本誌の記載内容によって不測の事故等が起こった場合、著者、編者、出版社、製薬会社は、その責を負いかねますことをご了承ください。
● 便秘といっても種類が異なるため、それぞれに合わせた下剤を選択しよう。
● 下剤の特徴をおさえて選択しよう。
機能性便秘の種類による下剤の選び方は?
慢性便秘症は一次性便秘症として、消化管の形態変化や運動障害に伴う非狭窄性器質性便秘1と、機能性便秘に分けられます(【第5回】の表2)。 機能性便秘は、①大腸通過正常型、②大腸通過遅延型、③便排出障害型に分けられ、それぞれの病態に応じた下剤の使い分けが必要です。
①大腸通過正常型
病態 大腸の糞便を輸送する能力が正常にもかかわらず、食事量や食物繊維が少ないために便量が減って排便回数が減少したり、硬便のために排便困難を呈する状態
対応 食物繊維の摂取や緩下剤の使用が効果的
②大腸通過遅延型
病態 大腸通過時間が遷延しているため、腸管内容物の水分が吸収されて硬便になる。また、便塊がなかなか直腸に輸送されないため、便意が消失していることも多い2
対応 緩下剤や刺激性下剤の使用が必要となる
③便排出障害型
病態 骨盤底筋群の協調運動障害・腹圧(努責力)低下・直腸感覚低下・直腸収縮力低下などのため、直腸からの便排出が障害され、排便困難や残便感を訴える
対応 直腸の伸展知覚鈍麻に対し、外用薬(坐剤、浣腸)の使用が必要な場合がある
主な下剤の種類と特徴とは?
下剤には主に、浸透圧性下剤(塩類下剤、糖類下剤、高分子化合物)、刺激性下剤、膨張性下剤、胆汁酸トランスポーター阻害薬、上皮機能変容薬があります。
塩類下剤(例:酸化マグネシウム)
塩類下剤は価格が安く、日本で広く使用されていますが、胃酸や膵液と反応してはじめて下剤としてはたらくため、胃切除後や酸分泌抑制薬が投与されている状態では効果が減弱します。
また、高齢者への投与(腎機能が正常な場合を含めて)は慎重投与とされており、定期的に血清マグネシウム濃度の測定をするなど注意が必要です。
糖類下剤(例:ラグノス®NF経口ゼリー、モニラック®)
糖類下剤はこれまで適応疾患が限られていましたが、ラグノス®NF経口ゼリーは2018年9月に慢性便秘症への適応が追加されました。ラクツロースを主成分とした薬剤で、消化酵素によって代謝されないため高浸透圧となり、内服後24~48時間で下剤効果が発揮されます。
また、善玉菌のエサとなり、分解されることで有機酸(酢酸・酪酸など)が生産されます。
高分子化合物(例:モビコール®)
電解質配合剤は、主成分のポリエチレングリコールの浸透圧効果で腸管内の水分量が増加し、便の軟化・便容量が増大することで生理的に大腸の蠕動を活性化します。米国では第1選択の薬剤で、電解質異常がなく、直腸などへの便貯留防止にも効果があるとされています3。
刺激性下剤(例:アントラキノン系薬剤→センノシド®、アローゼン®、大黄甘草湯など/ジフェニル系薬剤→ラキソベロン®)
刺激性下剤には、アントラキノン系薬剤とジフェニル系薬剤があります。どちらも長期連用によって効果の減弱が生じます。
ジフェニル系薬剤は、アントラキノン系薬剤よりも腸管の刺激性が少なく、効果も緩やかです。アントラキノン系薬剤とジフェニル系薬剤を同時に連用した場合、両方の薬剤に耐性ができてしまう恐れがあり注意が必要です。
『便通異常症診療ガイドライン2023―慢性便秘症』では、便秘診療に対し、まず生活習慣指導および浸透圧性下剤投与を行い、効果不十分の場合に刺激性下剤を考慮すべきとされています。
膨張性下剤(例:ポリフル®、カルメロースナトリウム)
この記事は会員限定記事です。