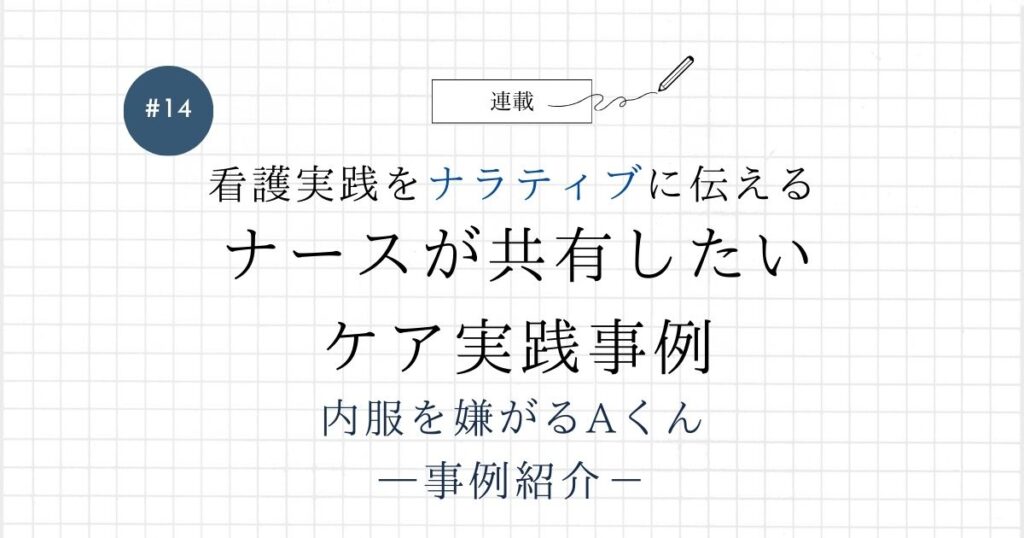事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は薬を飲みたがらない6歳の患者さんの事例を紹介します。
〈目次〉
内服を嫌がる6歳の患者さんが治療に向き合えるための環境づくり
「10時に内服しよう」の約束
薬を飲まない”に関連するさまざまな要因
支援方法を統一するためのカンファレンス
周術期に起こった Aくんの変化
内服を嫌がる6歳の患者さんが治療に向き合えるための環境づくり
6歳の男児Aくん、胸壁原発の神経芽細胞腫(小児がんの一種で、主に胸腹部に発生する)。Aくんには入院時、医師より「体の中にバイキンが入っているので、入院してやっつけなければならない。バイキンの名前は“神経芽腫”という名前である」と説明されています。
化学療法2コースが終了後、私はAくんの入院する病棟に配属となりました。そのとき、受け持ち看護師から、「Aくんはバクタ(経口の抗菌薬)を飲めず、注射のときも、暴れて看護師や母を叩いたりするので、どうかかわっていくのがいいのか困っています」と相談を受けました。
Aくんは小学1年生になったばかりで、このあと、手術、大量化学療法、放射線治療が控えていました。
「10時に内服しよう」の約束
化学療法が終わって数日後、私がAくんの部屋に行くと、Aくんはベッドでゲームをしていました。朝食は食べていなかったもののジュースは飲んでおり、抗がん剤による嘔気の遷延はなさそうです。
すでに院内学級の授業開始時間になっていたので、私は“朝のぶんのバクタを内服し、登校できるようにしよう”と考えました。ところがAくんに「バクタ飲んで、学校に行こう」と話しかけても、返事がありません。
バクタは苦みが強いことから、看護師はこれまでも“苦みを感じにくい方法”をさまざまに検討してAくんと母親に提案し、この時点ではチョコレートに混ぜることで何度か内服できていました。そのため私は、子どもの好む方法で、飲むタイミングを子どもに聞いて内服を促そうとしていました。
しかし話しかけても返事がなかったため、次に、バクタを飲む時間を約束しようと思いましたが、ベッドサイドに時計がありません。「何時に飲む?」と聞いても返事がないため、自分の時計を見せながら「じゃあ10時になったら飲もうか。長い針が上にきたら10時だよ」と言うと、Aくんはうなずきました。
私はいったんベッドサイドを離れ、10時に再度声をかけましたが、Aくんの気持ちは内服に向かず、説得する私を蹴ろうと足を上げることもありました。しかしAくんは「今のは足、上げただけ!」と言って、実際には私を蹴るのを踏みとどまっていました。
この様子から、Aくん自身も母親や看護師を叩いたりしてはいけないことをよくわかっていながら、この状況に対する怒りなどのさまざまな感情をうまく処理したり向き合ったりすることもできず、Aくん自身もつらくなっているのではないかと心が痛みました。
内服できないのでまた時間を約束して、その時間になってもまた内服できず……ということを繰り返して、午前中が終わりました。その日は結局、院内学級に登校せず、母親が面会に来てから母親の促しによって内服できました。
“薬を飲まない”に関連するさまざまな要因
この日のことを振り返ると、Aくんにとっては、看護師が来るたびに内服を促され、嫌なこととずっと向き合わなければならない状況になっていることに気づきました。
内服できないまま午前中が過ぎ、結局、登校できなかったことも問題です。小学生になったことを機に、入院生活においては1日の生活リズムをつけていくことが必要だと考えました。それによって「楽しい時間」と「嫌なことをがんばる時間」とを区別でき、楽しい時間が確保されることが必要だと考えました。
また、Aくんが入院生活の中にも楽しみを見つけることができれば、ストレス対処が“人を叩く”という不適切な方法ではなく、“遊びのなかでの昇華”へと変化するのではないかと考えました。
これから長く続く治療を乗り越えていかなければならないAくんにとっては、入院生活のなかに安全基地を見いだすこと、つまり、何があっても自分を受け止めてくれる人、がんばっている自分を認めてくれる人がいる、という実感をもてることが不可欠です。
そしてその存在になりうるのは母親と、病院の中で決して子どもに痛いことをしない、子どもの療養を支援する存在(子ども療養支援士、child care support〈CCS〉)、そして院内学級の教諭であろうと思いました。
Aくんが内服を嫌がる理由として、味が苦手ということもありますが、内服して嘔吐した経験から、「薬を飲んだら吐く」と思い込んでしまい、なかなか口に入れられないのではないかと考えました。
また、痛みを伴う処置への抵抗から、自分が入院して治療を受けなければならない理由をどのように理解しているのだろうか、という疑問も湧きました。
内服ができないことだけをAくんの課題としてとらえるのではなく、今後の治療にAくん自身が主体的に取り組み、達成感を感じられるように支援することが重要であると考えました。
支援方法を統一するためのカンファレンス
そのうえでは、Aくん自身が治療の意味を理解できるように、「体にバイキンがいる」というあいまいな説明ではなく、病名と治療予定を再度、医師から説明することも必要だと考えました。
そこで、医師・看護師・院内学級教諭・CCS(Bさん)ほか医療チームで話し合いを行い、以下の介入を提案しました。
①バクタの内服時刻を決め、それ以外の時間は内服の話題を出さず、登校や遊びを促し、Aくんが楽しいと思える時間をつくる。そして、Aくんが院内学級教諭やCCSと関係を築けるようにする。
②再度、病気とこれからの治療の予定を医師より説明し、入院治療や内服の意味について、Aくんなりに理解できるようにする。
①については12時を内服の時間と決め、その時間に担当看護師がAくんとのかかわりに集中できるように、業務調整を行いました。
そして、院内学級教諭とCCSに、Aくんとの関係づくりを進めてもらいました。また、Aくんが時計を読めるようになって、時間の感覚がつくように、時計を用意してもらうことを母親に依頼しました。
②については、医師より病名と、それが“がん”というものであること、今後の治療予定について、改めてAくんに説明しました。 このとき、Aくんは「嫌だ! 聞きたくない」と言ったものの、まったく聞いていないわけではありませんでした。
周術期に起こった Aくんの変化
1日の中で、“がんばること”と“遊び・学校の時間”を区別することで、「学校に行きたい」という発言が多く聞かれるようになりました。
また、看護師のことは名前で呼ばなくてもCCSであるBさんの名前は覚えて、「Bさん、いる?」「Bさんと遊びたい」と言うようになりました。
検査の帰りに散歩を促しても、「学校に行きたいから早く病棟に帰る」と言うこともありました。CCSと院内学級がAくんにとって安心できる対象となりつつあると考えられました。
一方、バクタの内服については、変わらずできないことが多いまま手術を迎え、内服そのものが中止となる時期に入ってしまいました。
Aくんは手術についての具体的な説明やプレパレーション(心の準備に対する支援)に対しても拒否を示し、「話なんて聞きたくない」と布団にくるまっていました。
このとき、母親から「直接話しかけても聞かないけれど、大人どうしの話は聞いているから、先生や看護師さんから私(母親)に話してもらうのを、隣で聞いている、という感じにすればいいかも」という提案があり、その形でAくんに手術の説明を行いました。
術後はICUで数日過ごしましたが、CCSと遊ぶ時間を楽しみにしており、ドレーンや点滴の扱いを大切にして、処置にも応じていました。胸腔ドレーン抜去後に、「これは嫌だった」と気持ちを冷静に言葉にすることもありました。自分の感情を暴力ではなく、言葉で表現できるようになってきたことは、Aくんにとって大きな成長でした。
術後、バクタ内服が再開されたときは、「こいつ(ゲーム上のキャラクター)を倒したら、バクタ飲む」と、自ら内服に取り組む姿勢を見せるようになっていきました。
処置の際に暴れて嫌がることは続きましたが、処置後のごほうびのコイン(CCSが折り紙で手作りしたもの)を集めて喜び、自慢げに「こんなに集まった!」と看護師に見せる姿もありました。
そのほか、精神科医師の助言のもと、かかわりの枠組みを定める(連日注射があるときは毎日決まった時刻に行う、処置の際に暴れたりものを投げたりするときはそれに看護師がリアクションせずAくん1人にしてクールダウンの時間を作る、など)ことで、Aくんは、予定された治療を完遂することができました。
※この記事は『エキスパートナース』2016年5月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。