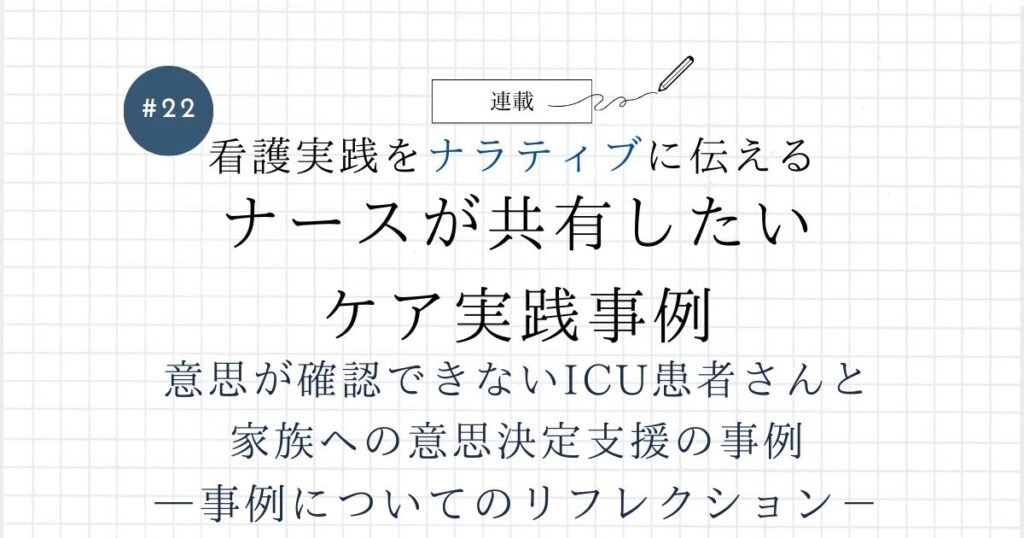事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は意思が確認できないICU患者さんと家族への意思決定支援を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第20回】意思確認が困難なICU患者と家族への意思決定支援
〈目次〉
医療従事者が「気づく」ということ
気づきと基準の統合:基準をもつことの重要性
事例についてのリフレクション
本事例では、家族の代理意思決定の際に、「患者さんにとって」を看護師も考え、家族も考え、意向や感情を整理していったプロセスが述べられています。
医療従事者が「気づく」ということ
患者・家族の権利擁護を考える際には、患者さんの以前からの言動、あるいは重要な説明後に表出される言葉や態度から、医療従事者が“いつもと違う何か”に気づくことが重要です。データの異常値に気づくためには、「正常値」を知らなくては異常をとらえられません。
同じように、患者や家族の言動が“いつもと違う”“納得していないような言動”“医師の説明を理解できていないのでは”と気づくためには、「通常」を知らなくてはなりません。
ふだんからの患者・家族の生活スタイル、大切にしている生き方や価値観を、患者が意識障害状態でコミュニケーションがとれない場合でも家族とのやりとりから読みとっていくような、患者・家族と医療従事者との関係性が根底に必要です。
この事例ではスタッフの皆さんが、ふだんの夫の言動からとらえた“家に連れて帰りたい”という思いを大切にしています。
このため、胃瘻・ストーマ造設の説明の際に、看護師はこの手術の侵襲により、希望である自宅退院ができなくなるのではと危惧します。そして「リスクの説明がもっと必要なのでは」「夫にリスクを含めた説明をすべきでは」など、複雑な感情が芽生えたと考えられます。
この感情は、看護師の患者・家族への善行の思いからといえます。
次にスタッフの皆さんがすばらしいのは、このよう「もう一度説明したほうがよいのでは」という非常に勇気がいることを、森田さんに相談していることです。
この記事は会員限定記事です。