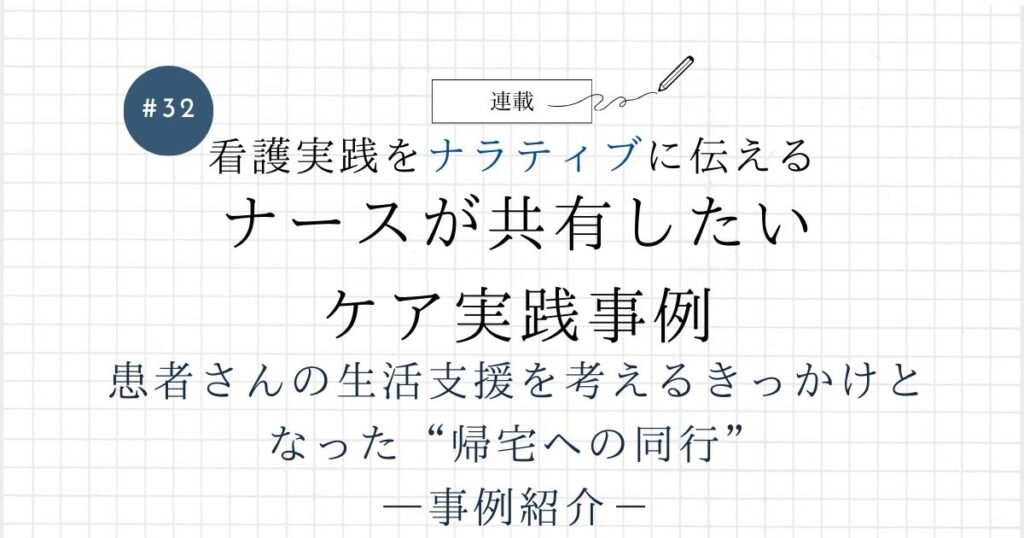事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は患者さんの生活支援を考えるきっかけとなった“帰宅への同行”の事例を紹介します。
〈目次〉
外来受診されたCOPD患者のAさんの様子
“会話の内容”“持ちもの”から見えてきたこと
同行しながら考えた、Aさんの生活に必要な支援
新たな支援を受け入れたAさんの生活を確認する
患者さんの生活支援を考えるきっかけとなった“帰宅への同行”
70代女性のAさん。ある日、屋外のベンチに座り苦しそうにしているところを通行人に発見され、外来を受診しました。
来院時のAさんは携帯用酸素のカートと外出用のリュックを持ち、鼻カニューレを装着していました。
外来受診されたCOPD患者のAさんの様子
私が外来診察室を訪れた際、Aさんは診察室の椅子に腰かけ、うつむき加減で肩呼吸をしていました。ピンクと白の上下のスウェットを身に着け、化粧もきちんとしておられました。
酸素は3L/分下でパルスオキシメーターの表示は 89%。顔色は悪く、呼吸数は1分間に26回と頻呼吸でした。
外来看護師は、「来たとき鼻カニューレは着けていたけれど、酸素の流量計の目盛は“0”になっていた」と話してくれました。
5か月前に受けていた一般検診の記録から、Aさんは慢性閉塞性肺疾患(COPD)で、10年前から在宅酸素を使っていることがわかりました。
Aさんにかかりつけの病院を尋ねると、「もうずいぶん前から通っています」とB病院の名前を出されましたが、それ以上を語られることはありませんでした。
当日Aさんは、よく利用する食堂に行くつもりで家を出たようです。状況を近親者へ伝えておいたほうがよいと思い家族について尋ねると、「家族はいないのでいいです」と口を閉ざしました。
マンションで1人暮らしをしているそうで、同じマンションの友人がよくしてくれるとも話してくれました。
“会話の内容”“持ちもの”から見えてきたこと
しばらくすると、Aさんの呼吸状態は落ち着き、帰宅が許されました。
私は、かかりつけのB病院についてくわしく語らない(語れない?)Aさんが気になりました。来院時に酸素の流量計が0であったことも気になっていました。
Aさんのこれからの支援を考える時期が“今”ではないかと感じ、もうしばらくAさんと一緒にいることを決め、会計に同行しました。会計に行きAさんの依頼でリュックを開けると、3日前の日付のB病院から出された薬袋が出てきました。B病院への通院についてAさんに尋ねてみると、「最近は行っていません」と答えます。
ほかにもリュックのなかには、ハサミや無造作にたたまれたメモ紙、書類の束が入っており、横のポケットには小銭がばらばらに入っていました。この時点で私は、Aさんに、認知症に伴う記憶障害や実行機能障害が出ているのではないかと考えました。
続けてAさんに介護サービスについて尋ねると「受けていません。大丈夫です」、酸素について聞くと「お勝手や洗濯物を干すときなんかはわずらわしいので外しています」と答えます。
酸素については労作時の酸素使用の必要性を伝えましたが、自宅で守れるか確信はもてませんでした。私は病院から自宅までの道を一緒に帰ることを申し出て、Aさんの帰宅に同行することにしました。
同行しながら考えた、Aさんの生活に必要な支援
Aさんの自宅までの道中には、大きな商業施設がありました。Aさんはいつもここを通っているらしく、“入口の椅子”と“出口あたりのジュース販売機横の椅子”で、二度の休憩をとりました。
「いつもここで休んでいくの。飲みものも買えるしね」と笑顔が見られたため、自宅での様子をもう少し聞いてみることにしました。食事は外出時に買ってきたものを食べることが多く、甘いパンが好きだと話してくれました。
いま困っていることはないか、掃除や洗濯はどうしているのかなどを尋ねると、「そうですねえ。まあ、できるぶんだけするようにしています」と表面的な答えが返ってきました。
15分ほどかけてご自宅に着きました。玄関先から見える室内には、買いもの袋や服が散在していました。私はAさんに、地域包括支援センターが日常の困りごとの相談にのってくれることを伝え、管轄の地域包括支援センターへ今日のことを伝えてよいか尋ね、了解を得ました。
Aさん宅から病院へ帰る途中、商業施設の店員に声を掛けられました。“Aさんが週に3~4回ここを通っていること”“最近、苦しそうにしているのを見かけて気になっていたこと”を話してくれました。
私は、苦しそうにしていたら声を掛けてみてほしいこと、その際、Aさんと一緒に酸素の流量計を見てみてほしいことを伝えると、「どうすればいいかわからなくて、これまでは声が掛けられなかったんです。今度はそうしてみます」と店員は笑顔で了解してくれました。
かかわりのなかで私は、Aさんが自ら困りごとを整理し、周囲へ支援を求めることは難しいだろうと感じていました。
Aさんが今後、支援を得ながら暮らすうえで鍵となるであろう地域包括支援センターに連絡し、今日のできごとを伝え、Aさんと連絡をとってほしい旨を伝えました。 認知症の可能性もあり、支援体制を変える時期に来ているのかもしれないという私の考えも話しました。
新たな支援を受け入れたAさんの生活を確認する
後日、地域包括支援センターから連絡がありました。自宅訪問をしてAさんと話をしたこと、Aさんの希望で、遠方のB病院から自宅近くのC病院へかかりつけ医を変えることにしたこと、介護保険申請を了承し、準備を始めたことなどを報告してくれました。
私はC病院の医師に、外来受診時の酸素やリュックの中身のこと、B病院の受診をAさんが覚えていなかったことなどを話し、認知機能の評価も検討してほしいと依頼しました。
その後AさんはC病院に通うようになり、アルツハイマー型認知症の診断を受けました。酸素と服薬管理を目的とした訪問看護が導入され、訪問介護と配食サービスも入るようになりました。
外来受診にはヘルパーが同行し、なじみの食堂への外出は、周囲の見守りのもと、現在も続けられています。
※この記事は『エキスパートナース』2016年11月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。