多職種連携に関連する悩みや疑問は、他職種に相談することで解決するかも!今回は、よく使う薬剤でも起こりうる配合変化のチェック方法について。混注時に看護師が注意すべきことを、薬剤師が解説します。
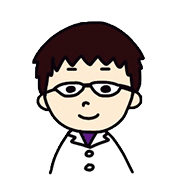
S.O.えすおー
薬剤師(Ph)
療養病棟担当の病院薬剤師。何でも輸液に混合しようとする医師のいる病院に勤めている。

ぽりまーぽりまー
薬剤師(Ph)
クリニックと在宅専門薬局で兼業している薬剤師。先日、PCAポンプの調剤を初めて経験した。
●薬剤師(Ph:Pharmacist)
院内のさまざまな場面で使用される医薬品に関する業務を担当する職種。最近は、病棟で見かけることも多くなっている、はず。ナースが普段感じている薬の使用感を裏づけるような、小話のネタをたくさんもっていることがある。
よく使う薬剤での配合変化はどうチェックする?
混注時、薬剤が混濁して焦ってしまった…!よく使う薬剤でも起こりうる配合変化、どうチェックするとよいの?
脳神経外科病棟の看護師です。先日、「フェニトインナトリウム注射液(商品名:アレビアチン®)と5%ブドウ糖液を混注*¹する」という指示処方が出て、溶解時に結晶析出するというインシデントがありました。本来ならば、生理食塩液か注射用水で希釈しなければなりませんでした。
先輩看護師からは「アミノ酸・糖・ 電解質・ビタミンキット(商品名:ビーフリード®輸液など)も配合変化しやすいから注意するように」と言われましたが、今後どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
*1【混注】混合注射。補液へ注射薬を配合すること
薬剤を混注する際の注意点は?
フェニトインナトリウム注射液(以下、フェニトイン注)は、脳卒中後のてんかんを予防する薬剤として使用され、配合変化を起こしやすい代表的な薬剤でもあります。注射薬はさまざまな組み合わせにより配合変化を起こすので、どんなときに起こりやすいのか知っておくことが大切です。
ここでは前述の事例で起きた配合変化について確認し、混注で気をつけるべきポイントを一緒に学んでいきましょう!
まずは注射薬のpH(酸性・塩基性)に着目
今回の配合変化(結晶析出)が起こった原因は、塩基性(アルカリ性)注射薬であるフェニトイン注(pH12)に弱酸性のブドウ糖液(pH3.5~6.5)を混注してしまったことです。酸性・塩基性が強い薬剤を覚えておき、処方時に確認する習慣をつけることで、このようなpH変動による配合変化をある程度防ぐことができます(表)。
混注時は、1剤ずつ大容量の輸液で希釈すると、配合変化が起こりにくくなることが知られています(希釈効果)。酸性・塩基性が強い薬剤を1つのシリンジ内で混注すると、配合変化リスクが非常に高くなるので避けましょう。
表 主な酸性注射薬と塩基性注射薬
〈酸性注射薬〉
アドレナリン pH2.3~5.0
エピルビシン塩酸塩 pH4.5~6.0
ガベキサートメシル酸塩 pH4.0~5.5
ドパミン塩酸塩 pH3.0~5.0
ドブタミン塩酸塩 pH2.7~3.3
チアミン塩化物塩酸塩 pH2.5~4.5
ノルアドレナリン pH2.3~5.0
ブロムヘキシン塩酸塩 pH2.2~3.2
ミダゾラム pH2.8~3.8
〈塩基性注射薬〉
アシクロビル pH10.7~11.7
アミノフィリ pH8.0~10.0
オメプラゾール pH9.5~11.0
カンレノ酸カリウム pH9.0~10.0
含糖酸化鉄 pH9.0~10.0
炭酸水素ナトリウム pH7.0~8.5
フェニトイン pH12
フロセミド pH8.6~9.6
(各薬剤の添付文書を参考に作成)
※本表に記載のpHは一例です。実際の使用にあたっては、個々の添付文書等を都度ご確認ください。
「難水溶性」「電解質」「コロイド」などを把握する
なお、今回問題となったフェニトイン注は、脂溶性が高いので水に溶けにくく(難水溶性)、生理食塩液や注射用水に溶解する場合でも注意が必要です。溶解補助剤の許容範囲を超えて希釈されると、この場合も結晶が析出してしまいます。このように、薄めることで引き起こされる配合変化もあるので、かかわったことがあるものから少しずつ覚えていきましょう。脂溶性の高い薬は、中枢神経系に作用する薬剤が多いので、頭の片隅に置いておくとよいと思います。
また、先輩看護師から言われたように、電解質などを含む輸液製剤も配合変化に気をつけたほうがよいです。例えば、一時的に絶食せざるをえない肺炎の患者さんに、PPN(peripheral parenteral nutrition:末梢静脈栄養)と抗生剤の投与が必要になる際に、カルシウム(Ca)を含む輸液製剤(ビーフリード®輸液など)とセフトリアキソン注(ロセフィン®静注用)を同時投与すると、難溶性の結晶を生成するため、別ルートで投与するか、前後フラッシュを行うこととされています。
他にも、エステルなどの加水分解やコロイドの塩析・凝析など、多様な機序で配合変化が起こるため、それらをすべて把握するのは薬剤師でも困難です。
最低限気をつけるべきポイントは?
ここまで、代表的な配合変化の例をお伝えしましたが、「膨大な注射処方をいちいち確認していられないよ!」というみなさんのために、最低限、気をつけるべきポイントをまとめました。
①採用薬で配合変化が起こりやすいものをある程度知っておく
最初は上表に挙げた薬剤だけでも、病棟で見かけた際に「何かあったな……」と思えるとよいですね。余裕が出てきたら、採用薬の中で配合変化が起こりやすい薬剤を探してみましょう。注射処方せんにフラッシュ用の生理食塩液を見かけたら、覚えるチャンスです!
②新規処方や新しい組み合わせを見かけたら確認する習慣をつける
何回も見かけている組み合わせについては、まず安心してよいと言えます。新しい組み合わせに気づいたら、ぜひ調べてみてください。オンラインで公開されている各薬剤の添付文書の、「製剤の性状(pH、浸透圧)」「用法・用量(溶解液)」「適用上の注意(投与経路、投与時など)」で確認できます!
③注射薬に詳しい先輩看護師や薬剤師とコネクションをもっておく
自分が所属する病棟の頻用薬で、配合変化に注意すべき薬剤は何か、事前に先輩看護師や病棟薬剤師に聞いてみると、詳しい人を紹介してもらえるかもしれません。早めに見つけておくと、いざという時に安心ですね!
*
薬剤部では、配合変化についての資料がすぐ見られるようにしてあるほか、過去にインシデントが発生した薬の保管場所に注意喚起のシールを貼ったり、注射処方せんの薬剤名に(配合変化注意)などの文言を追加したり、システム面での工夫も取り入れているところが多いです。
注射薬の配合変化のポイントを知ること、わからないことをそのままにしないことは、未来の自分を救う意味でも大切です。注射薬の処方に少しでも不安があるときは、いつでもお近くの薬剤師に問い合わせてくださいね!
この記事は『エキスパートナース』2021年9月号連載を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
個々の患者の治療開始前には、医師・薬剤師とともに添付文書およびガイドライン等を確認してください。実践によって得られた方法を普遍化すべく万全を尽くしておりますが、万一、本誌の記載内容によって不測の事故等が起こった場合、著者、編者、出版社、製薬会社は、その責を負いかねますことをご了承ください。






