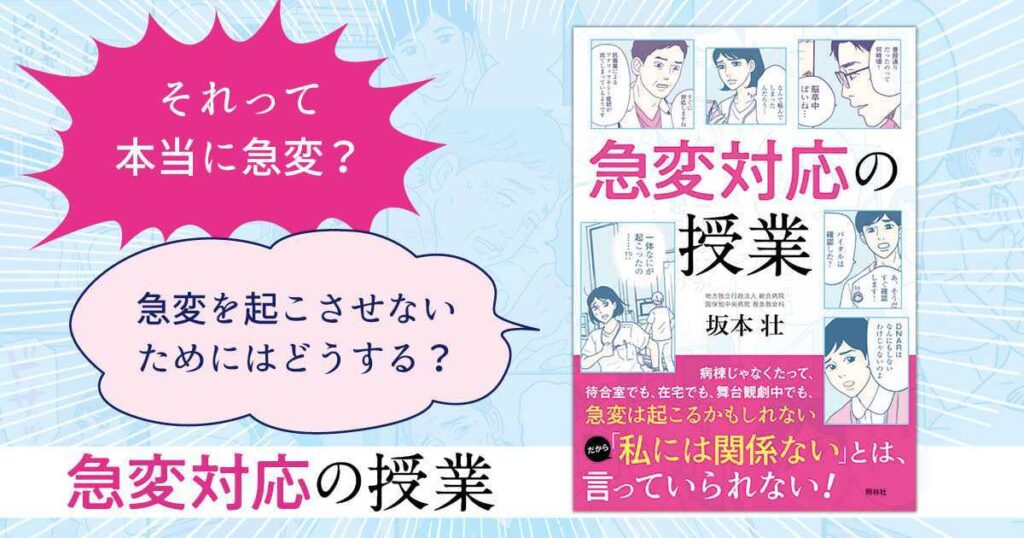急変対応は何年たっても自信がもてないもの。急変を起こさないようにするためには、観察やアセスメントが重要です。看護師や研修医に向けて、救急初期対応などの研修を豊富に行っている坂本壮先生の新刊『急変対応の授業』の一部を抜粋(全4回)。第2回は、第1回で紹介した急変対応において大切なことの1つ目「患者さんの把握」について解説します。
急変対応で大切なこと①患者さんを把握しよう!5Pをチェック
あたりまえですが担当患者さんの把握は大切です。相手のことを知らずして適切な対応はできませんよね。何のために入院し、どのような治療方針なのか、何が問題点なのか、今後起こりうる出来事はどのようなものが挙げられるのか、このあたりを整理することが大切です。
【1】目的(Purpose):入院の目的・理由は?
目の前の患者さんは何のために入院しているのでしょうか。
〇発熱、呼吸困難を主訴に救急外来を受診。精査の結果、細菌性肺炎の診断、点滴による抗菌薬治療のため入院となった。
〇自宅で転倒し動けなくなり、精査の結果、左大腿骨近位部骨折の診断で手術目的に入院となった。
〇不明熱の精査目的に入院となった。
このように、担当患者さんの入院の目的を理解しましょう。
急性期病棟では患者さんの入れ替わりが激しく、また夜間などは把握すべき患者さんの数が多く大変かもしれませんが、何のために入院しているのかを把握していなければ、みるべき点や備えるべき点を意識することはできません。
【2】患者(Patient):患者さんはどんな人?
入院の目的は同じでも、急変のリスクは同じではありません。基礎疾患のない若年者と、複数の病気を治療中の高齢者とでは、明らかに後者のほうがリスクは高そうですよね。
抱えている病気やアレルギー歴、内服薬(抗血栓薬など)、嗜好歴(タバコ、アルコールの程度)なども整理しておきましょう。高齢者では介護度などにも注目し、普段のADLを把握しておくとよいでしょう。カルテ記載を鵜呑みにしてはダメですよ。担当医を信じるなという意味ではありません。誰でも誤ることはありますし、初療の段階では聞き逃していることもあるものですから。必ず一度は、自身で確認するくせをもっておきましょう。
【3】方針(Policy):今後の方針は?
担当患者さんが今後、どのような方針なのかを理解しておきましょう。例えば、
〇細菌性肺炎で抗菌薬治療中、食事が半量以上摂取できれば点滴は抜針、抗菌薬は内服へ移行予定。
〇出血性胃潰瘍で点滴管理中、本日内視鏡を再検し、止血が確認できれば食事を開始する予定。
など、具体的に方針を確認することで、患者さんの進むべき道が見え、退院へのイメージがわくはずです。
また、入院当初は必要であった点滴や尿道カテーテルも、不要な状態となればただちに抜去が望ましいですが、担当医よりもベッドサイドに近いみなさんのほうが早期に判断ができるかもしれません。みなさんが気づき、適切なタイミングで抜去できれば感染を未然に防ぐことができます。
方針を確認するためには、担当医とのコミュニケーションが不可欠です。最近は電子カルテの病院が多いと思いますが、カルテ上のみでのやりとりでは適切なコミュニケーションはとれません。また、なにか問題があってもリアルタイムで対応できません。スマートフォンやPHSでもかまいませんが、可能な限り回診時などに対面で情報を共有しましょう。
【4】問題点(Problem):現在の問題点は?
方針どおりに事が進めばよいのですが、全部が全部そうはいきませんよね。
〇細菌性肺炎に対して抗菌薬治療を行っているものの、なかなか酸素化が改善しない。
〇急性期脳梗塞で入院した患者さんが、痙攣を認めた。
〇大腿骨近位部骨折の術後の患者さんが、創部の痛みを訴えている。
など、現在の問題点を患者さんごとに整理しておきましょう。
問題点も担当医と共有ですよ。みなさんが記載している看護記録、予想以上に医師は見ています。痛みの訴えや治療方針の不満など、看護記録には患者さんからの訴えの記載があるものの、担当医へ連絡がないのは寂しいものです。
看護師が患者さんの異変に気づいているのにもかかわらず、実際に医師へ報告したのは75%であったという報告があったりします1。4回に1回は報告しないのです。個人差はあると思うのでこの割合を覚える必要はありませんが、みなさんも気になることがあっても全例報告することなく、胸の内に秘めてしまったことってあると思います。報告すべきか自信がもてずしなかった、報告しづらい状況であったなど、さまざまな要因があるとは思いますが、理想はなんでも相談できる関係ですよね。まずはリーダーなど先輩看護師に相談するのもよいですが、報告すべきか悩んだらぜひぜひ担当医へも積極的に相談してください。
【5】予測(Prediction):急変する可能性ってある?
“○○さんは□%の確率で急変します”。そんなことが数値化され、見える化されればわかりやすいですが、確立したデータはありません。しかし、ここまでの【1】〜【4】を把握し、後述する急変のサインを知れば、起こりうる急変のリスクをある程度、見積もることはできます。
例えば、若年者と高齢者では、基礎疾患や臓器の予備能から高齢者のほうがリスクが高いでしょう。治療が奏効している患者さんと難渋している患者さんでは、後者のほうがリスクは高いですよね。また、点滴や膀胱留置カテーテルを要している場合には感染のリスクは高く、寝たきりなどADLが低下している場合には深部静脈血栓症(DVT)、それが原因となって引き起こされる肺塞栓症のリスクがあります。他にも、せん妄のリスク、転倒のリスクなどを見積もる術がありますが、それはまたいずれ取り上げます。
確立されたものはないと記載しましたが、「GO-FAR score」という院内心停止の予後予測スコアは存在します2。このスコアで24点以上となると、機能良好(CPC 1;意識清明、軽度の脳神経障害や軽度の精神障害があっても普通の生活、労働が可能)での生存退院率が1%未満と報告されています。評価項目数が多いですが、webやアプリケーションで簡単に計算でき、慣れるとそれほど時間はかかり
ません(私は「MDCalc」というアプリをスマートフォンに入れて利用しています)。
例えば、施設入所中の80歳の女性が急性期脳卒中で入院し、誤嚥性肺炎を併発している場合には、その時点で24点以上となり、心停止に陥ってしまった場合の神経学的予後はきわめて不良と考えられます。
あくまで院内心停止の予後予測であり、このスコアが高いから急変しやすいというわけではありませんが、担当患者さんの急変の可能性の見積りに悩んだ際には、参考にするとよいでしょう。見た目の重症度が低そうに思えても、じつは危険因子を複数併せもっていることを理解していれば、日々の観察を慎重に行いたくなりますよね。
- 1.Franklin C,Mathew J:Developing strategies to prevent inhospital cardiac arrest:analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event.Crit Care Med 1994;22(2):244-247. PMID:8306682
2.Ebell MH,Jang W,Shen Y,et al.:Development and Validation of the Good Outcome Following Attempted Resuscitation(GO-FAR)Score to Predict Neurologically Intact Survival After In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitation.JAMA Intern Med 2013;173(20):1872-1878. PMID:24018585 DOI:10.1001/jamainternmed.2013.10037
【本記事は、『急変対応の授業』からの抜粋です。続きは書籍でどうぞ】
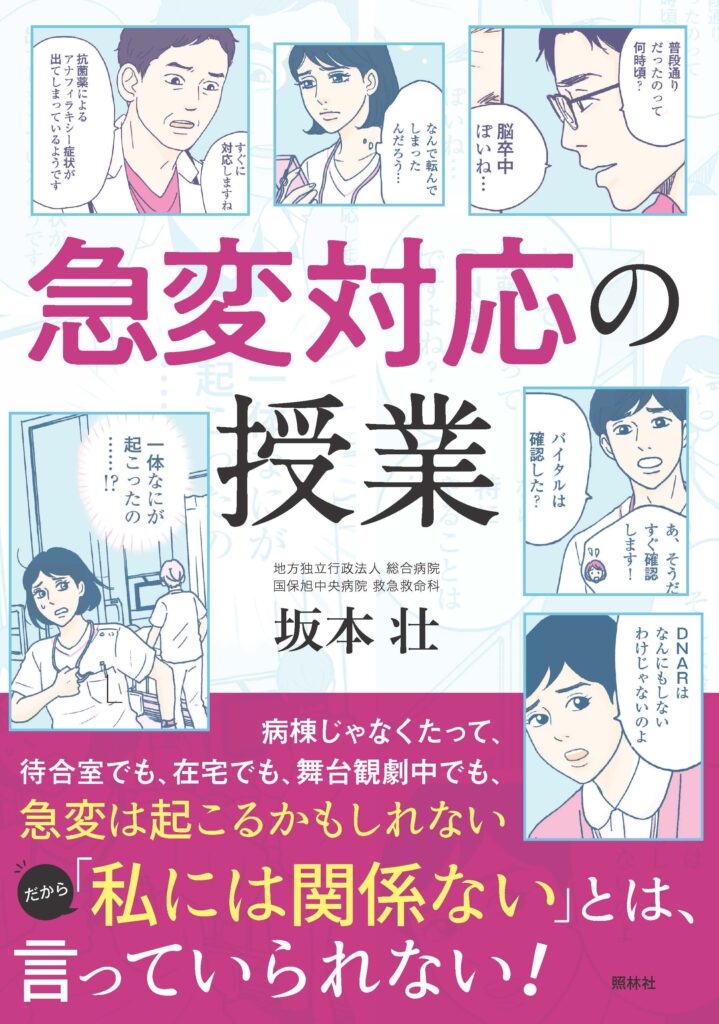
※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。