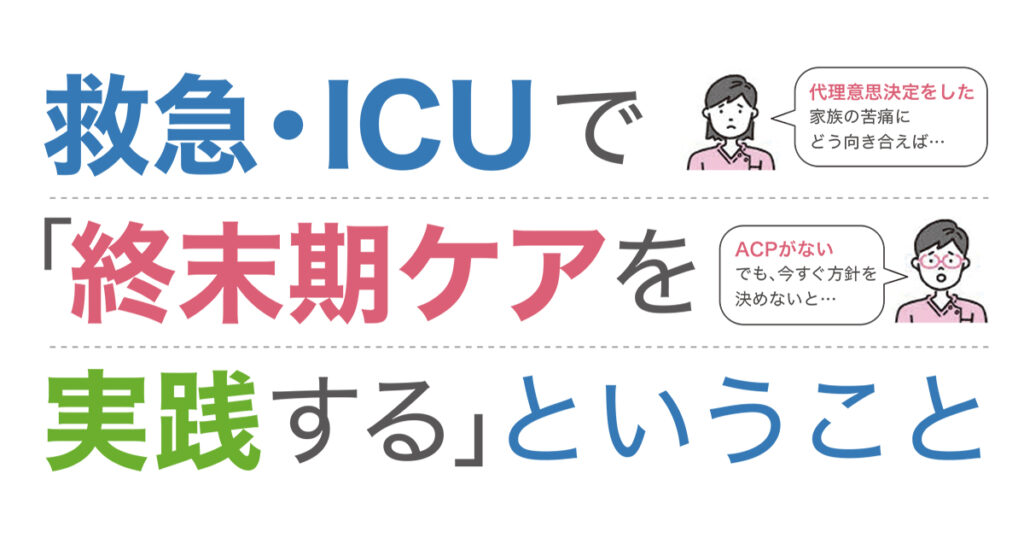『救急・ICUで「終末期ケアを実践する」ということ』の試し読み記事をお届けします。今回は「意思決定した後、患者や家族に、どうかかわればいい?」という疑問について解説。看護師ができる、緩和ケア、悲嘆ケアのアプローチとは?
前回の記事:救急・ICUにおける終末期ケアが注目される理由とは?
人生における重要な決定をした患者と家族に対して、その感情を受け止め、共有して寄り添い、心理的負担を軽減できるようなかかわりが必要となります。緩和ケア、悲嘆ケアのアプローチが有用です。
「行う決断」より「行わない決断」のほうが、心理的負担が大きい
終末期にある患者・家族は、意思決定を行った後、どのような心理状態となるのでしょうか。
決定を行ったことで緊張から解放されるかもしれません。しかし、多くの患者・家族は、自責の念にかられ、選択や決断を後悔したり、“これでよかったのだろうか…”と、決断の是非を自問自答したりすることでしょう。
意思決定後の後悔を完全になくすのは難しい
後悔には、行為後悔と非行為後悔があります。行為後悔が時間とともに解消するのに対し、非行為後悔は時間がたっても解消されず、むしろ後悔が強くなる傾向がある1)ことが、多くの研究で明らかとなっています。
終末期には、新たな治療の差し控え(withholding)や治療の中止(withdrawal)、DNAR(do not attempt resuscitation:蘇生適応除外)など、行わない決断をすることが多いです。そのため「行っておけば、あったかもしれない現在」と「今ある現実」を比較すると、後悔が強くなります。
意思決定後の後悔を完全になくすことは難しいですが、「そのときの最善を尽くした」と思えるようなかかわりが、患者と家族の心理的負担を和らげる大きな支えになります。
行為後悔:行ったことに対する後悔。
非行為後悔:行わなかったことに対する後悔。
治療の差し控え(withholding)と治療の中止(withdrawal)の違い
「治療の差し控え」は、治療を最初から始めないこと、今実施している以上の治療を追加することを
控えることをさします。
一方「治療の中止」は、すでに開始されている治療を中止することをさします。倫理的・心理的な側
面から、より慎重に対応が必要とされる場面が多いです。
「行わない代理意思決定」を行った家族の支援
事例の概要
〈これまでの経過〉
Bさん(54歳)は、家族(妻、長女)と買い物中、突然「胸が苦しい」と言いながら卒倒。心肺停止状態で、蘇生処置を行いながら救急搬送されました。初期波形は心室細動で、複数回除細動を行ったものの心拍再開せず、緊急でV-A ECMOを挿入。心臓カテーテル検査で急性心筋梗塞と診断され、経皮的冠動脈形成術が行われたものの、自己心拍の改善は乏しく、全身管理のため、ICU入室となりました。
主治医は家族に「多臓器障害や代謝性アシドーシスも進行してきており、予後が非常に悪い」ことを説明。これまで、本人のACPや事前指示はありません。
〈現在の状況と意思決定〉
7病日目となっても状態は悪化の一途をたどり、心不全ケアチームや多職種による協議の末、Bさ
んは救命の見込みがなく終末期であると判断されました。家族へインフォームド・コンセントが行わ
れ、医師から「多臓器不全が進行し、これ以上の治療は効果が見込めず、残念だが終末期の状態」と伝
えられました。
話し合いの結果、V-A ECMOが停止しても交換しないこと、心室細動時の除細動を行わないこと、輸
血や補液をこれ以上行わないこと、カテコラミン投与は現行量を最大とすること、などが決められま
した。
V-A ECMO(Veno-Arterial ECMO):静脈から動脈に送る体外式膜型人工肺。PCPSとも。
状況整理:意思決定後の状況は?
家族(妻)
「これまでずっと元気だったのに、こんなことになるなんて、まだ信じられません」
「先生のおっしゃることは理解できました。助かる見込みがないと聞いて、仕方ないことだと自分に言い聞かせています。これ以上苦しむ姿も見たくないですしね」
「でも、これで本当によかったのかわかりません」
「寂しがり屋の人だったから、少しでもそばにいてあげたいですね」
ポイント①意思決定した家族の思いを支持する
妻は「助かる見込みがないと聞いて、仕方ないことだって自分に言い聞かせています」と話しています。この発言から、受け入れるのもやっとの心理状態であり、意思決定は容易でないことが想像できますから、意思決定後には、つらい判断をしたことを労いましょう。
また、妻の「これで本当によかったのかわかりません」という発言からは、決断に対する感情の揺らぎもうかがえます。インフォームド・コンセントの場は何度でも調整できること、決定は変えられることを伝え、そのつど、医療者も、ともに考えていくというスタンスを提示しましょう。
代理意思決定後の家族への声かけ例
〈つらい判断をしたことをねぎらうとき〉
「決めるのはつらかったですね」「みなさんが○さんのために一生懸命考えている事実は、私たちも見てきましたし、ご本人もわかってくれていると思いますよ」など。
〈感情の揺らぎを受け止めるとき〉
「気持ちが揺らぐことは当然ですし、何が正解かはわかりません。どのような選択をしたとしても、後悔することはきっとあると思います。それでも、本人のために最善の選択をしたと思えるよう、これからも一緒に考えていきましょう」など。
ポイント②家族のニードを充たす
重症患者の家族のニードとして、①サポート、②安寧・安楽、③情報、④接近、⑤保証の 5 つが知られています3)。
アドバイス
終末期における意思決定後には、日々変化する患者の状況をわかりやすく情報提供しながら、ベッド周囲の環境を整えたうえで接近してもらい、最期のときを過ごすなかで、患者に最善の治療が提供されていること・家族の決定に沿ったケアが提供されていることを保証することが、家族の後悔の軽減につながる。
妻の「少しでもそばにいてあげたいですね」という発言から、接近のニードが高いことは当然想定できます。さまざまな医療機器に囲まれている状況は、それだけで家族の心理的負担となります。機器を離すことは難しいとは思いますが、患者の周囲はライン類をまとめ、見えている顔周りや手の周囲などは、家族が触れやすいように整えておきましょう。
また、経過のなかで妻から「今つながっている薬は何ですか?」という発言もあり、情報のニードがあることもうかがえます。つながれている点滴や機械、モニターの情報などは、わかりやすい言葉を用いて伝えますが、不安へとつながらないことへの配慮が必要です。
アドバイス
情報提供は「何でも伝えればいい」わけではない。まず「わからないことや疑問があれば、いつでもおっしゃってくださいね」と、こちらに情報提供できる準備があることを示したうえで、必要な情報に関してわかりやすい平易な言葉を選んで説明する。家族が内容を理解しているかの確認も行う。
さらに、妻は「苦しむ姿も見たくないですしね」と話しています。経過のなかで「きつくないでしょうか」という発言もあることから、苦痛緩和に関する保証のニードもうかがえます。患者に最善の治療が提供されていること、家族の決定に沿ったケアが提供されていることを伝えましょう。
終末期にある家族とのコミュニケーションはなかなかハードルが高いかもしれません。コミュニケーション技法(VALUE)を使用することで、家族のニードの把握を心がけてみてもよいでしょう(表1)。

代理意思決定後、家族はかわるがわるBさんのそばに付き添いました。看護師は、そのつど家族の心理的状態をアセスメントしながら、適宜、Bさんの状態やケアの状況について情報提供し、ベッド周囲の環境整理を行いました。2日後、Bさんは徐々に血圧が保てなくなり、心拍数が低下しはじめました。家族に待機してもらうタイミングを医療者で検討・共有し、いざ臨終の際には、家族が到着し、感情表出できる時間を確保したうえで、落ち着いてから死亡確認を行うに至りました。
この間、医療者との会話のなかで、家族がBさんの人生を振り返るなど、ライフレビューを語る場面もあり、グリーフワークへとつなげることができました。
終末期における患者・家族の意思決定は、ゴールではなく新しいケアの始まりです。意思決定後に訪れるさまざまな不安や葛藤・後悔に対して、患者・家族を支えるために最も力を発揮できるのは、いつもベッドサイドでケアを行う私たち看護師ではないでしょうか。
日ごろから患者ケアを十分に行い、患者・家族が少しでも治療に対して安心感が得られるようにすることは、予期悲嘆の援助にもつながります。そのために、看護チームだけでなく、多職種で共有・連携してサポートする体制を整えてみてはいかがでしょうか。
- 1)Gilovich T, Medvec VH. The experience of regret: what, when, and why. Psychol rev 1995; 102: 379-395.
2)大坂巌,渡邊清高,志真泰夫,他:わが国におけるWHO緩和ケア定義の定訳.Palliat Care Res 2019;14(2):61-66.
3)山勢博彰,立野淳子,田戸朝美,他:CNS-FACEⅡについて.
https://ds26.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~cnsface/user/html/about.html(2025.6.18アクセス).
\続きは書籍で/
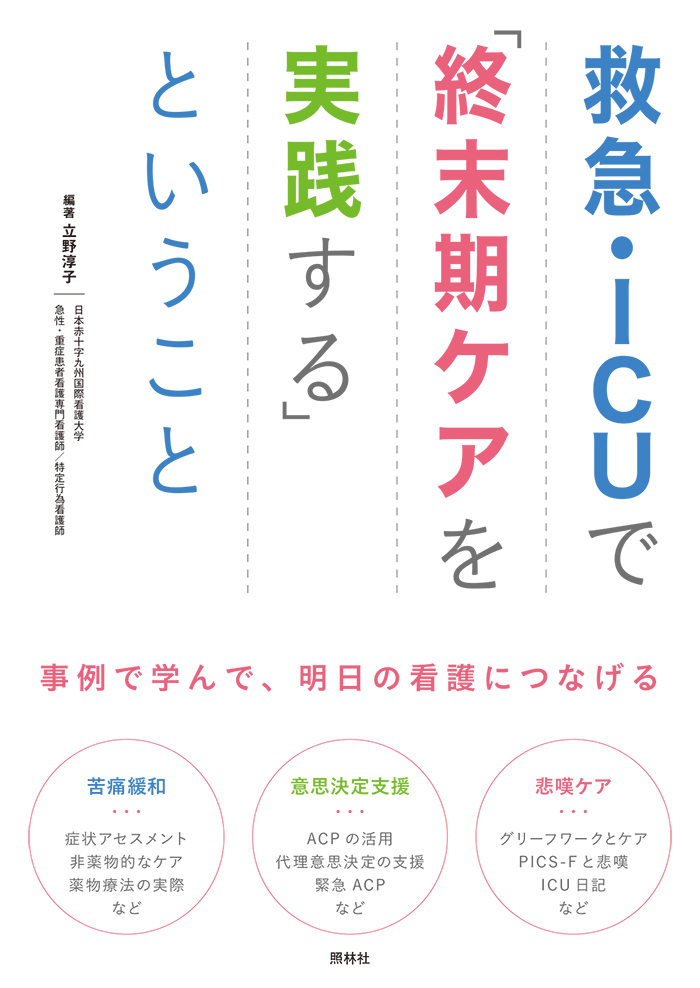
救急・ICUで「終末期ケアを実践する」ということ
立野淳子 編著
B5・192ページ、定価 2,970円(税込)
照林社
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。