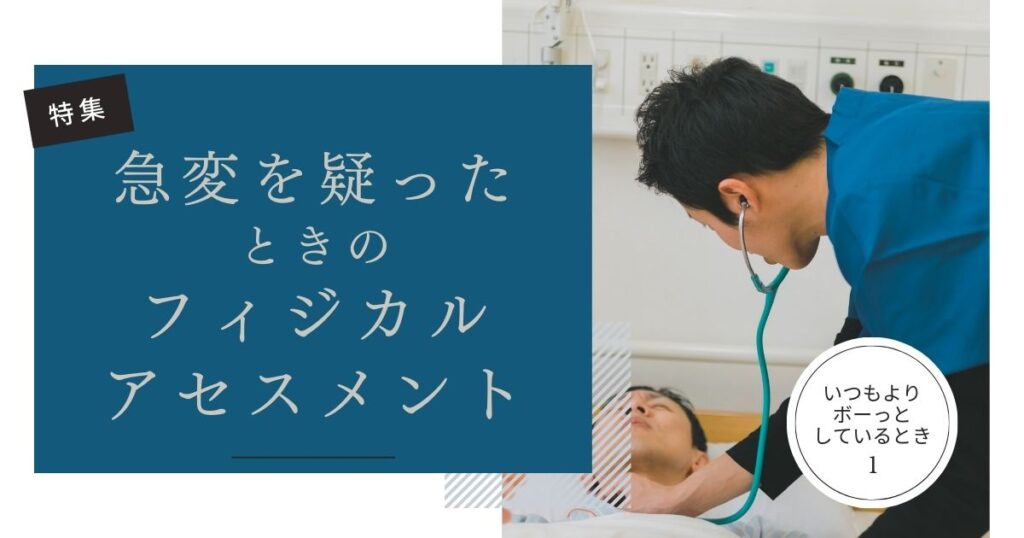急変を疑ったとき、ナースにできるたくさんのフィジカルアセスメントのなかから“本当にいま必要な3項目”を選べるようになりましょう。今回は何となくいつもよりボーっとしているときの対応の第1段階。まずは意識レベルを評価します。
Step1 まず「ボーっと」をスケールで評価する
「何かおかしい…」に気づくことが第一歩
ケアをしているときやお話をしているときの患者の様子を見て、「あれ?何となく、いつもよりボーっとしているな……」と感じたことはありますか?
ここでも大切なことは「なんとなく」「いつもと比べて」ということです。何かおかしいと気づくことができることが、急変の前兆を見抜くはじめの一歩です。「いつもよりボーっとしている感じ」に気づかず対応が遅れてしまえば、患者は意識消失し急変してしまうかもしれません。その前に、わずかな変化に気づいて適切な対処が必要です。
その変化に気づくためには、普段の患者の状態を把握しておくことが重要です。もし、意識がなければ、緊急事態として迅速に対応する必要があります。
意識レベルの評価と、繰り返しの確認を
まずは意識障害がないか確認してみましょう。意識レベルの判断は、JCSやGCSを用いて行います。
また、そのときの意識レベルの評価だけではなく、意識レベルの変化をとらえることが重要です。スケールを用いて繰り返し判定することで意識レベルの変化がとらえられます。
ここでスケールについて振り返りましょう。JCSは、覚醒軸に主眼を置いた評価スケールで、覚醒の判断を「開眼」で判断します。桁数で大まかな重症度が判定できることやシンプルに評価できることから広く利用されています。
GCSは開眼(E)、言語反応(V)、運動反応(M)の3つの項目で点数化し、合計点で意識状態を評価するスケールです。E、V、Mそれぞれが細かく点数化されており、評価者間でばらつきが出にくく詳細な変化をとらえやすいとされていますが、合計点だけでは患者の全体像が把握しにくいということもあります。
JCS、GCSどちらのスケールを使用するか、明確なルールはありません。ただ、意識レベルの変化をとらえるために、また、多職種間でも共通の評価を行うために、施設ごとでどちらのスケールを使用するか統一しておいたほうがよいでしょう。急変時には簡便に評価できるJCSで評価することが多いと思います。
この記事は会員限定記事です。