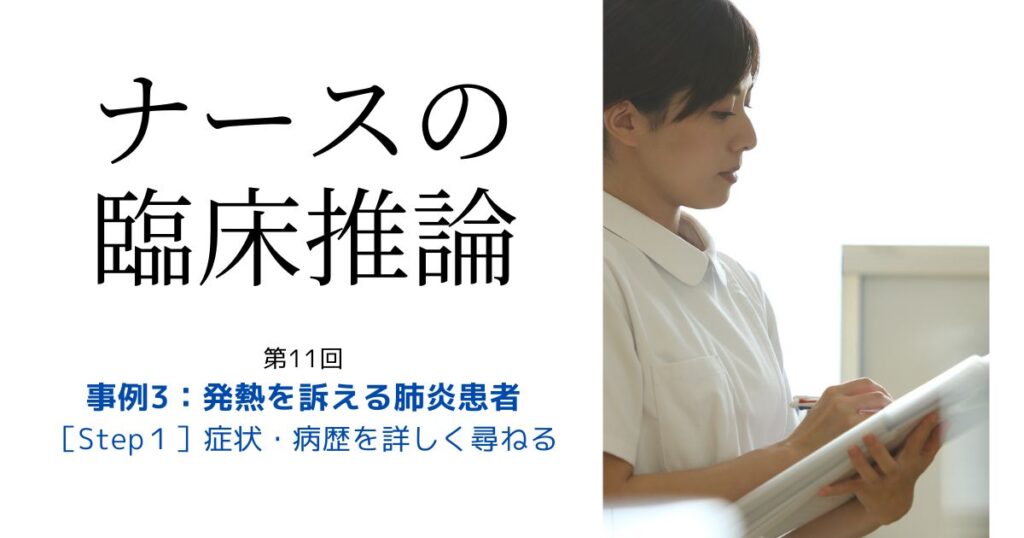患者さんの訴えの裏に隠された疾患を見逃さないために大切な「臨床推論」。どのような思考過程を経て臨床診断を導き出しているのかを考えていきます。今回は発熱を訴える肺炎患者さんの事例を紹介。Review of systems(ROS)を利用して症状・病歴を尋ねるポイントを解説します。
事例➂「発熱」で救急搬送された女性
Cさん(30代・女性)は、入院当日の朝~夕方になっても起きてこず、痰がからみ気味、熱感、体温39℃で救急搬送され、肺炎と診断され入院しました。抗菌薬と酸素を投与され、救急担当医から内科担当医に引き継ぎ。入院前日の朝まではいつも通り過ごしており、入院前日の夜、家族が帰ってきたころにはすでに就寝していました。既往は統合失調症。
その他の情報
●最近不眠傾向が続いていたが、入院前日の朝まではいつもと変わりなかった。搬送時、胸部単純X線検査で浸潤影。
●髄膜炎
●薬物中毒
●誤嚥/肺炎(レジオネラを含む)
●肺塞栓
第1ステップ 症状・病歴を詳しく尋ねる
「よくある疾患」に隠れた疾患を見逃さない!
本症例では、統合失調症の治療中で安定していたCさん(30代、女性)が、ある日いきなり眠り続け、発熱(39℃)、痰がらみを認め、胸部単純X線検査の結果から誤嚥性肺炎と診断されました。
肺炎はよくみられる疾患です。Cさんのように意識障害などによる誤嚥が原因で発症する肺炎以外に、もともと嚥下障害のある高齢者が他の疾患が原因となって誤嚥して発症するなど、原因はさまざまです。
また、低酸素症の原因が肺炎以外に複数ある場合もあるため、肺炎の陰に隠れている疾患を見逃さないことが重要です。
そのためには、診断に有用な特異的な病歴がないか、詳しく病歴を聞き、注意深く身体所見をとる必要があります。
発症時の状況や、家族の行動を確認する
以下のポイントをおさえましょう。
●発症様式(突然か、急か、数日かけて緩徐に起こったのかなど)
●発症の前後の状況
●起こった場所
●症状に気づいたきっかけは何だったのか
●本人や家族はその症状をどうとらえているか(解釈モデル)
Cさんはもともと陰性症状が強く、自宅に引きこもりがちでしたが、毎日1回、主治医との約束でウォーキングをしていました。最近、不眠が続いたため悩んでいました。母親は、睡眠薬を飲んで寝ていたと思っていましたが、熱があることがわかり、驚いて救急車を要請したとのことでした。ベッド横の机には、おおよそ1週間分の睡眠薬の空の包装シートがありました。
Cさんはずっと同じ姿勢で眠り続けていたようで、母親が昼頃様子を見に行ったときには口腔内が乾燥していました。母親は水分をとらせなければいけないと思い、スポンジに水を含ませて水を与えたとのことでした。
患者さんや家族の話を聞き漏らさないために、ROSを利用する
患者さんおよびそのまわりの人たちが、一度にすべてを話してくれないということはよくあります。聞き漏らしを防ぐために、問診を行う際に全身を系統的にチェックするReview of systems(ROS)をとるようにしましょう。
ROSによる質問では、最近、体重が増加傾向にあることをCさんが気にしていたことがわかりました。そのほかには、特に新しい情報は出てきませんでした。
Review of systems(ROM)(文献1を参考に作成)
Ⅰ.全身状態
●全般的に健康状態はいかがですか?
●発熱、悪寒、寝汗:熱や悪寒や寝汗はありますか?
●最近体重が変化しましたか?どのくらいの期間で何kg増え(減り)ましたか?何かダイエットを実行していますか?
●食欲は良好ですか?
●よく眠れますか?すぐ眠れますか?寝つきが悪いことはありませんか? 途中で目が覚めることがありますか?眠りが浅いですか?熟睡感はありますか?目が覚めたときにまだ疲れが取れないですか?
Ⅱ.頭部・中枢神経系
●転んで頭に怪我をしたことはありませんか?どうして転んだのですか?
●頭痛はありませんか?
●めまいはありませんか?くらくらして倒れそうになる「脳貧血」のようなめまいでしたか?部屋がぐるぐる回っているような、目が回っているようなめまいでしたか?
●気を失ったり気を失いそうになったことはありませんか?そのとき、実際に意識を失いましたか?何分間ぐらい?
●倒れましたか?怪我はありませんでしたか?
●よく見えますか?視力に問題はありませんか?物が□ぼやけたり二重に見えたりしたことは?
●耳はよく聞こえますか?不便はありませんか?
●歯に問題はありませんか?飲み込みにくかったり、むせたりしませんか?
Ⅲ.リンパ系
この記事は会員限定記事です。