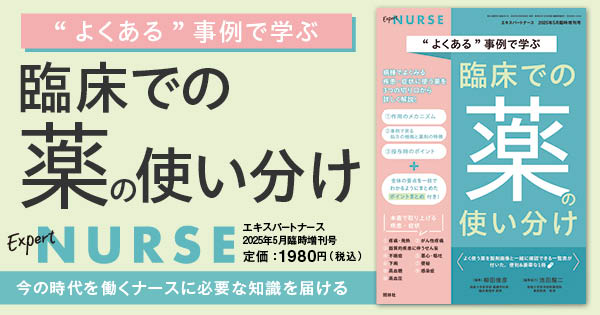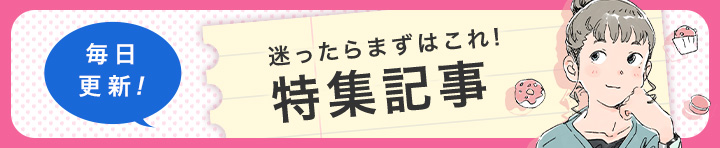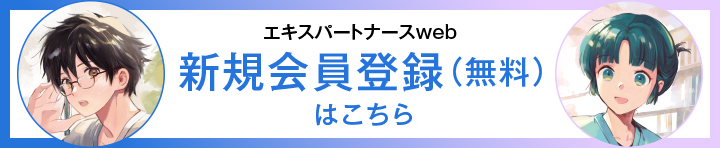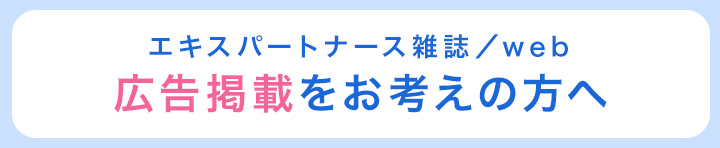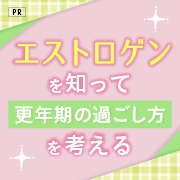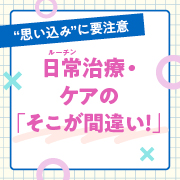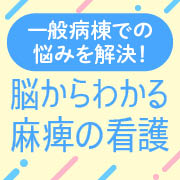-
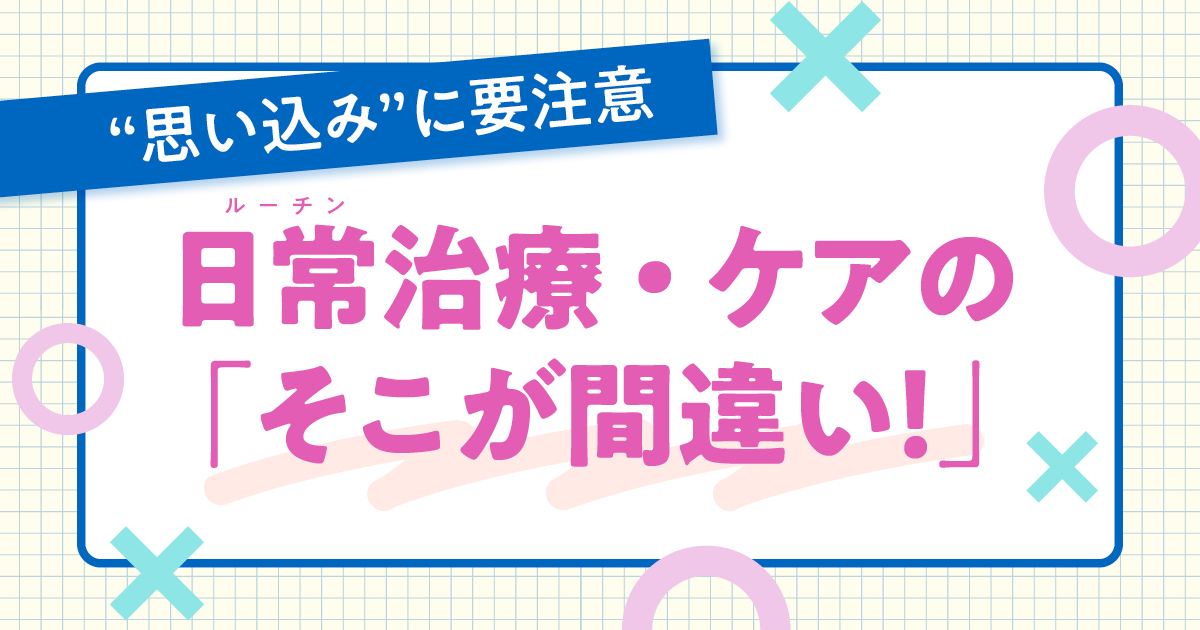
NSAIDsの使い分けとアセトアミノフェン使用時の注意点
- 会員限定
- 特集記事
-

【新規会員登録(無料)キャペーン】PDFを1冊まるごとプレゼント!
- 会員限定
- お知らせ
-

川嶋みどり 看護の羅針盤 第185回
読み物 -

『シティーハンター』とコラボ!“ヒーロー”として医療福祉職の魅力を発信
ニュース -
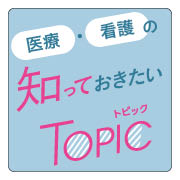
EHRとは―地域医療介護連携ネットワーク「サルビアねっと」の事例を参考に
最新トピック -
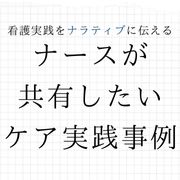
【連載まとめ】ナースが共有したいケア実践事例
患者対応 -
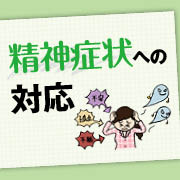
【連載まとめ】精神症状への対応
特集記事 -
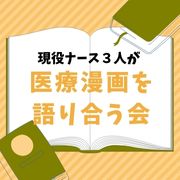
【連載まとめ】医療漫画を語り合う会
マンガ -
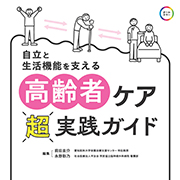
【試し読み】高齢者ケア超実践ガイド
特別記事 -
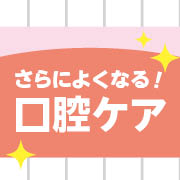
【連載まとめ】さらによくなる!口腔ケア
特集記事
特集記事
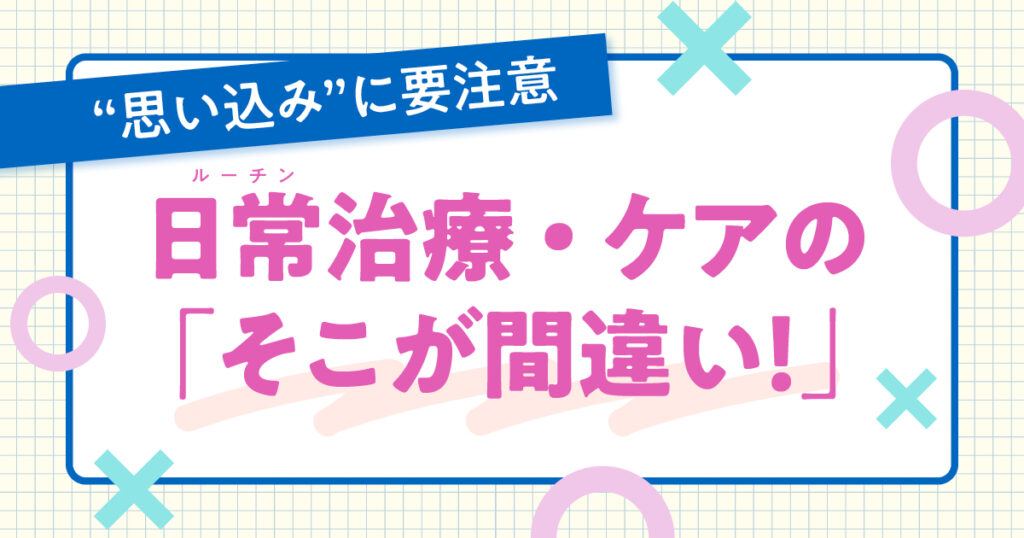
NSAIDsの使い分けとアセトアミノフェン使用時の注意点
術後疼痛には、機序の異なる鎮痛薬をあわせて使用することが大切です。今回は、NSAIDsの使い分けのポイントやアセトアミノフェン使用時の注意点を解説します。 NSAIDsの剤形ごとの使い分け NSAIDsは副作用の軽減や即効性、効果の長時間持続といった目的で注射薬や坐薬などが開発されています。 1)静注薬:経口摂取ができない手術直後の患者に使用 唯一の静注薬であるフルルビプロフェン アキセチル(ロピオン®)は、血中濃度の上昇がすみやかで効果発現が最も早く、健常成人に 50mgを単回投与すると投与 6.7±1.7分後には最高血漿濃度に達します。経口薬のロキソプロフェンは、最高血漿濃度に達するまでの時間は30分(ロキソプロフェン)~50分(活性代謝物)となっており、このことからも静注薬の効き目が早いことがわかります。そのため、全身麻酔による手術直後で経口摂取ができない患者に用いるのがよいでしょう。 また、静注薬であれ経口薬であれ投与後に、除痛されることによってそれまで痛み刺激によって亢進していた交感神経や下垂体-副腎系の内分泌反応が減弱し、血圧や心拍数が低下することがあるので、バイタルサインや痛みを含めた患者の症状の変化には十分注意する必要があります。 ただし静注薬は、経口摂取ができない状態にしか基本は使用できません。 2)坐薬:意識状態が悪いときや吐気が強い、 座位を保持できない患者などに使用 坐薬は、直腸投与のため、胃腸粘膜への直接刺激を避けることが可能です。ただし血中に入ってからも作用するため、胃腸障害軽減に寄与しますが、重篤な消化管障害を抑えるエビデンスはありません。 また直腸から吸収された薬剤は肝臓での代謝を受けにくく、経口投与に比べ作用発現が早く、高齢者などで低体温ショックに注意する必要があります。 効果の強さに応じたNSAIDsの使い分け NSAIDsには種類が多くありますが、化学構造によって分類され、効果の強さ、血中半減期の長さおよび副作用などにそれぞれ違いがあります。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 効果 ・ 副作用は個人差が大きくはっきりとした比較はできませんが、化学構造別に分類した場合、アリール酢酸系(ボルタレン®、インドメタシンなど)およびオキシカム系(モービック®、ロルカム®など)のNSAIDsは一般的に効果が強く、プロピオン酸系(ロピオン®、ロキソニン®など)は、これらに比べるとやや弱いです。アントラニル酸系のメフェナム酸(ポンタール®)は、特に鎮痛効果が強くなっています1。 ボルタレン®は、アリール酢酸系、ロキソニン®はプロピオン酸系であり一般的にボルタレン®のほうが鎮痛作用は強いと言われています。ただ、胃腸障害などの副作用は出やすくなると言われています(「ボルタレン®>ポンタール®、インドメタシン>ロキソニン®」1)。 そのため、副作用出現のリスクが低い患者で鎮痛効果を優先するのであればボルタレン®を使用し、副作用発現リスクの高い患者では、効果は少し落ちますが副作用も少なく安全で総合的になるようバランスがとられているロキソニン®を使用します。 また、1種類のNSAIDsが効かないとのことで、もう1種類のNSAIDsを追加したり、通常の服用量以上を使用しても天井効果(有効限界)があるため効果は増えず、逆に副作用が増加する可能性があるため推奨できません。 アセトアミノフェン使用時の注意 アセトアミノフェンの最大使用量は1日4,000mg アセトアミノフェンの1日最大使用量は成人で4,000mgであり、1回使用量は300~1,000mgとなっています。市販の風邪薬やPL配合顆粒、トラムセット®配合錠などの薬剤にもアセトアミノフェンが含まれており、1日の合計使用量が4,000mgを超えないように注意が必要です。 術後の患者には注射薬を使用する 2013年11月からアセトアミノフェンは注射製剤(アセリオ®1,000mg)が発売されており、今まで術後で経口薬や坐薬の使用が困難の患者でもアセトアミノフェンが使用できるようになっています。 アセリオ®は効果を適正に発揮させるために、年齢、体重や投与量にかかわらず15分かけて静脈内投与することが推奨されています。 引用文献1.龍原徹,澤田康文:ポケット医薬品集2017年版.白文舎,福岡,2017. さらに学ぶなら術後疼痛管理における鎮痛薬の選択:機序の異なる薬剤の組み合わせ鎮痛薬の投与時に看護師が注意すべきことは?そのほかの連載記事はこちら この記事は『エキスパートナース』2017年5月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。個々の患者の治療開始前には、医師・薬剤師とともに添付文書およびガイドライン等を確認してください。実践によって得られた方法を普遍化すべく万全を尽くしておりますが、万一、本誌の記載内容によって不測の事故等が起こった場合、著者、編者、出版社、製薬会社は、その責を負いかねますことをご了承ください。
- 会員限定
- 特集記事
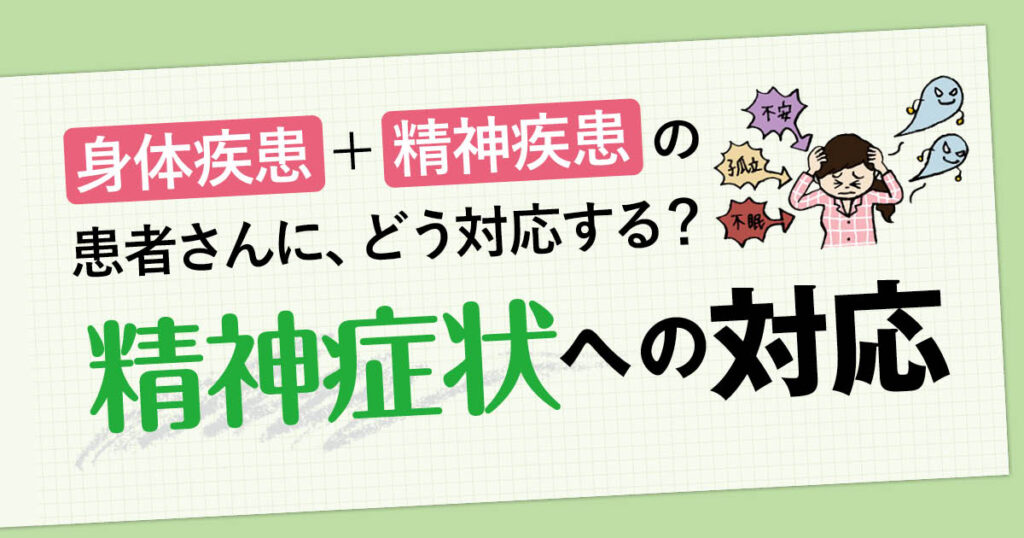
【連載まとめ】精神症状への対応
不安、抑うつ、焦燥感 ─ 。患者さんに現れる精神症状は多種多様ですが、どれも“つらさからこころを守る反応”であることに変わりはありません。基本として知っておきたい、精神症状との向き合い方を解説する連載です。 【第1回】治療の場での精神症状へのかかわり方 〈目次〉●精神症状とは“つらさからこころを守る反応”●“日常生活の感情”と“精神症状”の境目は? 【第2回】看護師ができる精神症状への対応 〈目次〉対応1 安易な共感はせず、“認証する”・基本は患者さんの言葉を“なぞって繰り返す”・“認証”とは、論理的に患者さんの苦しみを理解すること対応2 “侵襲的でない空気”をつくる対応3 患者さんを“あせらせず”、“ゆとり”をもてるようにする・あせりの誘因①:不安・あせりの誘因②:不眠・あせりの誘因③:孤立 【第3回】身体疾患による精神症状を除外する 〈目次〉●身体疾患を疑う12のポイント●精神症状を引き起こす身体疾患の例 【第4回】うつ病/双極症の基礎知識と対応のポイント 〈目次〉●疾患の基礎知識・うつ病・躁・軽躁・薬剤治療の進み方・経過観察とアセスメントのポイント・対応のポイント●自殺の可能性があるとき、ナースに何ができる?・TALK の原則”に沿って話を聞こう・徹底した聞き役になることで、患者さんのつらさを抱える 【第5回】統合失調症の基礎知識と対応のポイント 〈目次〉●統合失調症の基礎知識・薬剤治療の進み方・経過観察とアセスメントのポイント・対応のポイント●幻聴の訴えがあるときは、“いつもの対応”を尋ねてみる●治療拒否や攻撃的態度があるときは、不安をやわらげる言葉を●患者さんが強い興奮状態にあるときは、複数人で対応する 【第6回】不安症、強迫症の基礎知識と対応のポイント 〈目次〉●疾患の基礎知識・不安症・強迫症・薬剤治療の進み方・経過観察とアセスメントのポイント・対応のポイント●頻回のナースコールがあるときは、ゆとりをもつ姿勢を大切に・事例:比喩を用いて原因を探る 【第7回】身体症状症の基礎知識と対応のポイント 〈目次〉●身体症状症の基礎知識・薬剤治療の進み方・経過観察とアセスメントのポイント・対応のポイント●器質的な原因がみつからない身体症状を訴えるときは、日常生活へと視点をずらす・事例:患者さんの視点を“あせり”から“ゆとり”にずらす質問法 【第8回】パーソナリティ症の基礎知識と対応のポイント 〈目次〉●パーソナリティ症の基礎知識・薬剤治療の進み方・経過観察とアセスメントのポイント・対応のポイント●自傷などの行動化があったとき、ナースに何ができる?・行動化のプラス面も認めたうえでかかわる・ナースにできることは“感情”の認証●極端に好意的な態度や攻撃的な態度をとられたときは、医療者として態度を一定に保つ 【第9回】摂食症の基礎知識と対応のポイント 〈目次〉●摂食症の基礎知識・薬剤治療の進み方・経過観察とアセスメントのポイント・対応のポイント●食事を拒否し、栄養面の管理がうまくできないとき、ナースに何ができる?・診察を通じて、自身の「やせ」に納得してもらうことから始める 【第10回】患者さんの暴力にはどう対応する? 〈目次〉●暴力の原因は“ゆとり”のなさ●こちらの感情を入れず、“なぞって繰り返す”が基本●病院としての姿勢を明確にし、複数人で対応を 【第11回】抗精神病薬の作用と注意したい副作用 〈目次〉●抗精神病薬は脳内のさわがしさを抑えてくれるイメージ・気をつけたい副作用は錐体外路症状・主な抗精神病薬の副作用 【第12回】抗うつ薬の作用と注意したい副作用 〈目次〉●抗うつ薬は頭の中の停滞をかき混ぜて浮上させるイメージ●主な新規抗うつ薬・SSRI・SNRI・NaSSA・S-RIM●気をつけたい副作用 【第13回】ベンゾジアゼピン系(抗不安薬/催眠鎮静薬)の基礎知識 〈目次〉●ベンゾジアゼピン系はお酒のようなもの・半減期、筋弛緩作用、鎮静作用で薬剤の特徴が出てくる●抗不安薬か催眠鎮静(睡眠薬)、用途によって使い分ける・抗不安薬として用いる主なベンゾジアゼピン系・催眠鎮静(睡眠薬)として用いる主なベンゾジアゼピン系 【最終回】身体疾患治療薬との飲み合わせの注意点 〈目次〉●飲み合わせに影響を与える「CYP」とは?●抗精神病薬との飲み合わせの注意点●新規抗うつ薬との飲み合わせの注意点●ベンゾジアゼピン系との飲み合わせの注意点 そのほかの連載はこちら
特集記事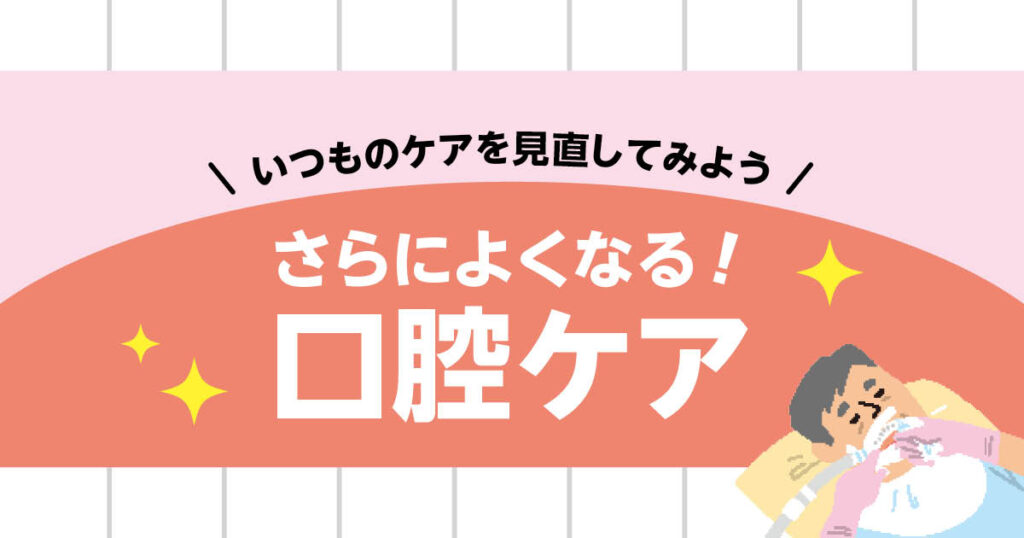
【連載まとめ】さらによくなる!口腔ケア
毎日行うからこそ、さらにいい方法があれば知りたい「口腔ケア」!より効果的に進めるため、看護師が知っておきたいポイントを紹介した連載です。 【第1回】口腔内のアセスメントスケールは何をどう使うと効果的? 〈目次〉●アセスメントスケールを見直してみようA.口腔ケアの「自立度」評価に向くスケール:BDR指標B.口腔内の状況を簡便に評価できる口腔アセスメントシート:OHAT(Oral Health Assessment Tool)・OHAT評価時ポイント 【第2回】義歯(入れ歯)の洗浄・装着方法 〈目次〉●義歯の管理不足による口内炎も起こりうる●義歯清掃の“効果的な”進め方●食べていない場合でも、就寝時以外は極力装着を 【第3回】口腔内のトラブルを見抜くための観察ポイント 〈目次〉1.出血傾向2.乾燥3.重度の汚染4.重度の舌苔5.カンジダ症6.歯の動揺 【第4回】効果的な口腔ケアのスケジュールとは? 〈目次〉●夕食後・就寝前の口腔ケアが望ましい●ケア回数を増やしても菌数は恒常的に減少しない●理想的な時間帯よりも「できる」時間帯に重点的なブラッシングを 【第5回】他職種連携、アセスメントによる効果的なケア 〈目次〉●他職種との連携:「必要度×難易度×緊急性」で考え、難しければヘルプを①口腔ケアの必要度②口腔ケアの難易度③口腔ケアの緊急性●看護チーム内での連携:口腔ケアでも「実施」→「評価」サイクルを回す①口腔のアセスメント・計画立案②実践③評価・改善 【第6回】「拭き取り法」とは?口腔ケア後の“洗浄”を検討 〈目次〉●口腔ケアにおける「拭き取り法」の検討●「拭き取り法」の検討結果●臨床での「拭き取り法」のポイント・「拭き取り法」の手順・「拭き取り法」の注意点●汚染物除去方法の注意点 【第7回】「開口」が難しいときの対応方法 〈目次〉●口を開きたくても“開けない”場合●口を開くことが“わからない”場合●本人の意思で“口を開かない”場合 【第8回】口腔内が乾燥する原因と対応方法 〈目次〉●低栄養・脱水の場合●薬剤による影響の場合●開口状態が持続している場合 【第9回】口腔内出血の原因と対応 〈目次〉●口腔内の出血の要因●出血傾向(全身的原因)の場合●歯周病などによる出血(局所的原因)の場合 【第10回】歯ブラシ・歯間ブラシ・フロスの選び方と使い方のポイント 〈目次〉●細かいところまで磨けるヘッドの小さいものを選ぶ●ブラッシングの際は歯間、噛み合わせの溝などに磨き残しがないよう注意 【第11回】舌ブラシの選択と使い方のポイント 〈目次〉●ブラシタイプは舌表面を傷つけにくい●粘膜の保護を心がけながら舌の清掃を行う 【第12回】口腔粘膜清掃用グッズの選択と使い方のポイント 〈目次〉●絶食中の患者では特に口腔粘膜ケアが重要●口腔内の加湿・保湿に注意しながら清掃 【第13回】口腔内の消毒薬の選択と使い方のポイント 〈目次〉●術後や歯肉炎のときのみに使用する●口腔内に用いる消毒薬の種類と特徴・グルコン酸クロルヘキシジン・ベンゼトニウム塩化物・ポビドンヨード・過酸化水素 【第14回】口腔保湿剤の選択と使い方のポイント 〈目次〉●保湿剤は“加湿効果”か“保湿効果”、どちらを得たいかで使い分ける・保湿剤の製品例と使い分け●患者の状態をこまめに観察して保湿剤の使用頻度を決める 【第15回】排唾管・吸引つき歯ブラシの選び方 〈目次〉●口腔ケア中の吸引には、吸引孔が大きい排唾管を使用する 【最終回】開口器を活用した口腔ケア 〈目次〉●開口器で視野を確保し、効率的にケア そのほかの連載はこちら
特集記事