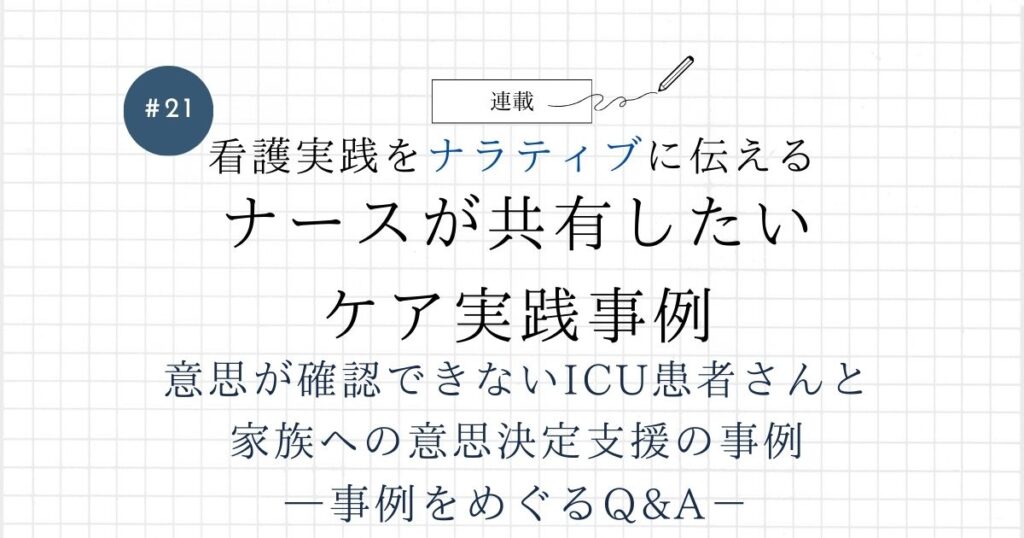事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は意思が確認できないICU患者さんと家族への意思決定支援をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第20回】意思確認が困難なICU患者と家族への意思決定支援
〈目次〉
この事例を選んだのはなぜ?
夫が代理意志決定者としての理解と意思決定能力があると考えた理由は?
情報を整理して分析した効果は?
看護師のもやついた気持ちはどう変わった?
事例をめぐるQ&A
この事例を選んだのはなぜ?
宇都宮 この事例を選択された理由を教えてください。
森田 私たちが日々ケアを行っている臨床では、「あれ?」「これでいいのかな?」と思うことが多々あります。それは私たちの倫理的感性のアンテナに引っかかったという重要なポイントです。
そのときに、“それは自分だけかもしれない”“誰にどう言ったらよいのかわからない”と思い、そのままになってしまうこともあるのではないでしょうか?しかし、その奥には倫理的な問題、または倫理的問題が生じる可能性が潜んでいます。
今回の事例は「これでいいのかな?」を声に出し、共有することで倫理的問題へ発展することなく解決に至ることができました。
また、話し合うときに、今回のようなツール(【第20回】事例紹介・表1参照)を用いることで思考を整理し、論理的に解決することが効果的であることを学んだため、この事例を選択しました。
夫が代理意志決定者としての理解と意思決定能力があると考えた理由は?
宇都宮 森田さんは夫が代理意思決定者として十分な理解と意思決定能力があると考えました。そのポイントはどこですか?
森田 代理意思決定するためには、代理意思決定者が以下の状態であることが重要です。
①正しく現状が把握でき、意思決定できる精神状態にあること
②患者のことをよく考え最善の意思決定をしようとしていること
この記事は会員限定記事です。