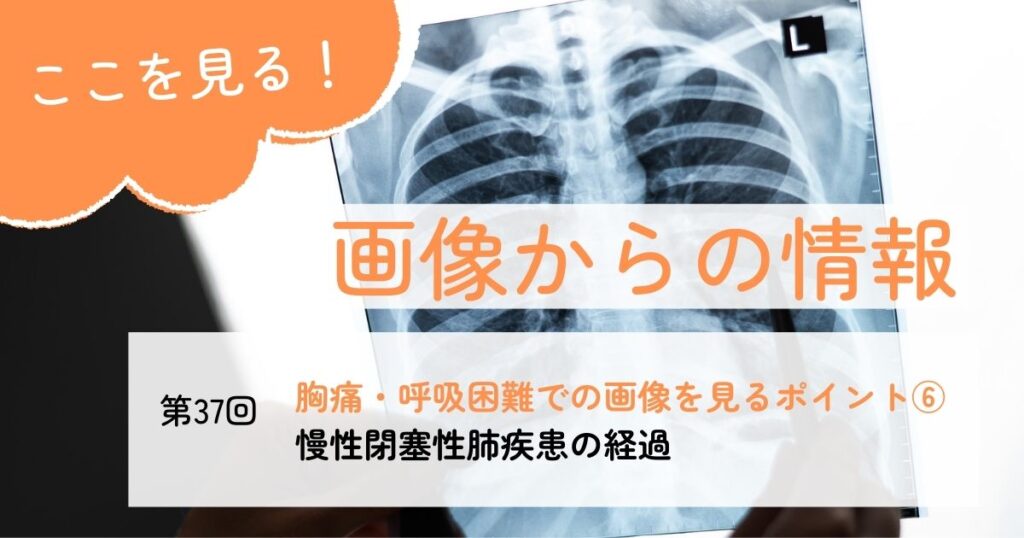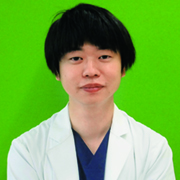ワケがあって医師がオーダーしている画像検査。臨床場面でナースがとりたい画像からの情報をわかりやすく示します。第37回は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者が肺炎や気胸をきたしていないかを確かめるため、画像検査を行う際のポイントを紹介します。
胸痛・呼吸困難での画像の着目ポイントは第32回を参照ください。
慢性閉塞性肺疾患の患者で、肺炎や気胸がないか見ている
〈症例〉
●70歳代男性。40年以上の喫煙歴があり、慢性閉塞性肺疾患と診断されていた
●当日の朝よりいつにもまして呼吸困難が強く、痰の量も多いため、救急要請した
●体温37.0℃、血圧 160/70mmHg、脈拍110/分、SpO2 92%(経鼻酸素3L/分)。聴診では、両側の肺より喘鳴が聴取された
COPD患者で急に呼吸状態が悪化したら、肺炎や気胸、肺塞栓症をきたしていないか、検査します。過去の画像と比較することも大事です。
胸部X線では、これまで見てきた肺と比べると、随分大きく見えます(図1)。肺の過膨張というのですが、典型的な慢性閉塞性肺疾患の所見です。
胸部CTではタバコによって肺胞が壊れてできた空洞を反映して、黒くなっている部分が多いです(図1)。
図1 慢性閉塞性肺疾患患者の胸部X線画像と肺の状態を見た胸部CT画像
この記事は会員限定記事です。