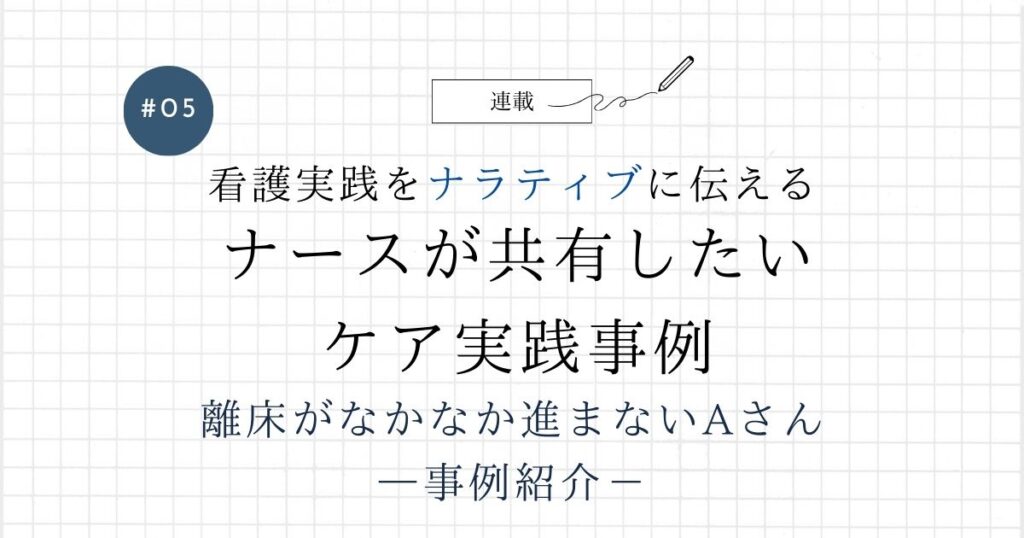事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は離床がなかなか進まなかった患者さんの事例を取り上げます。
〈目次〉
離床がなかなか進まなかったAさんへの「介入のきっかけ」
筆談の拡がりから得た情報
看護チームでの意識の変革
多職種カンファレンスをもとに離床機会が増える
離床がなかなか進まなかったAさんへの「介入のきっかけ」
Aさん、50代の男性患者。工務店を経営し、仕事は多忙期。妻、息子、娘夫婦と孫と同居。特に既往歴なし。
Aさんは、不調の際「いつもの喉風邪だろう」と市販薬を飲み過ごしていたのですが、数日間のうちに敗血症に陥ってしまい、生命の危機的状況にさらされることになってしまいました。
病名は、扁桃腺炎を起因とする頸部膿瘍、降下性壊死性縦隔炎、右膿胸で、救命治療のためには外科的治療以外の選択がない状況でした。そして、緊急手術(胸腔鏡下胸腔掻爬、縦隔切開、深頸部膿瘍切開ドレナージ術)を受け、術後にICU入室となりました。
ICUでは、感染源のコントロールのために持続的前縦隔洗浄が行われ、術後も非常に苦痛を伴う治療を受けざるを得ませんでした。また、遷延する敗血症により全身の消耗は激しく、日を追うごとにAさんは抑うつ傾向を示すようになりました。
このように混沌とする状況のなかで、さらなる問題がありました。それは、術後11日目に敗血症が重症化したことを契機に、深頸部に膿瘍が再形成されているのがわかったことです。Aさんは再手術(深頸部膿瘍切開ドレナージ術)を受けなくてはならなくなりました。
また、人工呼吸器からの離脱困難な状況*にもあったため、あわせて気管切開術を受けることとなりました。 その後、原疾患のコントロールを図ることができ、敗血症から離脱することはできましたが、身体的・精神的な問題があり、Aさんの離床やリハビリテーションはうまく進みませんでした。
*人工呼吸器離脱困難の原因は、今回新たに発覚した重度のCOPD(ヘビースモーカー:ブリンクマン指数〈BI〉=900)、敗血症に伴う廃用、右膿胸に伴う広範囲無気肺。
筆談の拡がりから得た情報
第15病日ごろより、ST(言語聴覚士)も介入し、経口摂取が開始されました。
その日、いつになくAさんの表情は凜(りん)としていました。昼食を終えたAさんは端座位になり、TVを観て笑っていました。
また食後には口腔ケアを自分で行った様子で、そばには使い終わった歯ブラシ、含嗽したあとのガーグルベイスン、手鏡と電動髭剃り、顔拭きタオルが、オーバーテーブルに整頓され置いてありました。
私は“何となくの予感”を覚え、Aさんと話(筆談やジェスチャーでの会話)をしてみようと思い、ベッドサイドにふらっと立ち寄り、担当看護師(以下、担当と表記)も交えて筆談しました。
筆者「あれ? Aさん、ずいぶんとシャキッとしましたね!かっこいいですね!」
Aさん「(笑いながら照れて数回うなずき)さっきも(担当看護師を指差し)言われた。そう言ってくれるのは看護師さんだけ」
担当「毎日、夕方の面会のとき、みんなで一緒にTV見たり、本当に仲いいなって、うらやましいなって。だから絶対、ご家族もかっこいいって言いますよ」
Aさん「(笑いながら手を横に振り)この間、孫が生まれて、みんなそっちに(写真を見せてくれる)」
その日のAさんは、笑顔にあふれ、淡々とした筆談からも、話の拡がりが感じられました。私たちは写真を見ながら会話を進めました。
担当「わあ、かわいいですね。娘さんのお子さん?」
筆者「そうすると、Aさんはおじいちゃんですね?」
Aさん「そう。でも、いま、寝たきりのおじいちゃん(笑いながら)」
担当「寝たきりのおじいちゃん?」
Aさん「(人工呼吸回路を指差し)ほらこれ、なんだかこれ体の一部(笑っている)。邪魔をする。動こうとするとき。こうすると咳、ヤッカイ。(体を左右に動かして回路が引っ張られて気管切開チューブにテンションがかかる様子をジェスチャー)」「だから“寝たきりのおじいちゃん” 。リハビリ。立てない、だめ」
筆者「寝たきりのおじいちゃん?だめ?」
Aさん「うん。リハビリ。(ハアハア肩を動かしながらそのときの様子を真似して)ドキドキ、痛い、苦しい」「(首を傾げながら)息できない、アブナイ、悪くなる」
担当「危ない? 悪くなる?」
Aさん「普通のとき→大丈夫」「動く→ここ(創部、ドレーン刺入部を指し)がまんできなくなる」「また急に手術、管(ドレーン)入る、いやだ(笑顔で)」
看護チームでの意識の変革
その後、病室の外で担当・リーダー看護師(以下、リーダー)とAさんのケアについて話をしてみることにしました。
筆者「今日はすごく表情がよくて、いろいろと話してくれているね」
担当「そうなの。昨日、生まれたばかりのお孫さんの写真を家族が持ってきてくれてから」
筆者「なるほど、家族の力ってやっぱりすごい!」
担当「本当。炎症も落ち着いてきたし、いくぶんか体も楽なこともあってか、ちょうどタイミングがよかったね」
筆者「そういえばリハビリ、どんな感じだろう?」
担当「いま呼吸器はCPAP『8』、PS(プレッシャーサポート)『8』で、血液ガス分析も問題なく経過できているんだけど、端座位から立位になると呼吸回数が増えてSpO2も低下して。30秒位で“だめ”って感じで」
筆者「そうかあ。リハビリも進まないね。この際、呼吸器つけながら歩いてみない?Aさんも前向きだし」
担当「え? 立位もできないのに……? あまり呼吸器つけたまま歩いたりっていうのはしたことがない」
筆者「確かに気管切開だし、危ないよね。でもAさんの真の気持ち、必要なケアって何だろう」
担当「……そうだね。この間の夜勤のとき、奥さんとこんなこと話してたよ。“孫のお宮参りには歩いていかないとね、車椅子とかだとかっこわるいよね”って」
筆者「なるほど。踏み出そうとする気持ち、感じられるね。どうだろう、なおのこと、その気持ちに寄り添うケアは作れないものだろうか?」
「一番いいのは呼吸器を離脱して、吹き流しにでもして、離床、歩行練習だよね。でも、Aさんの病態やこれまでの呼吸機能の経過を見ると、一筋縄ではいかなそう……。でも、だからと言って、ずっとベッド周囲っていうのは、心をふさぎこむのを促しちゃうよね」
リーダー「私もそう思っていたんですよ。どうすればAさんが一番望むこと、希望に寄り添いながらリハビリを進めてあげられるかって。ここで離床できないことは、負の連鎖を産むだけだって思う。長くICUにいればいいってわけでもないしね……」
筆者「移動用の、PEEPがかかる呼吸器もあるしね。環境は整えられる」
担当「でも、リハビリ中の痛みがくせものだよね」
筆者「平常時の痛みのコントロールは良好だよね。問題は運動時。そしたら先生やICU薬剤師と話し合って、その前にレスキューで鎮痛薬を考慮してもらったらどうかな。少なからず負荷で痛みは生じてしまうけど、軽減させて、それでAさんが成功体験をつかめられたら、きっと納得しながらステップアップできると思う」
担当「たしかに。そうしたら先生と薬剤師と相談してみる」
リーダー「じゃあどうしようか、離床のこと」
筆者「ICU医師と主治医、機器の安全面などもあるので、CE(臨床工学技士)も含めて、あとPT(理学療法士)にも意見を聞いてみよう」
「病態的には、運動負荷による酸素需要量増大と、高心拍になったときに無気肺も残存しているから、よけいにⅠ型の呼吸不全が進行している。そして、遷延した敗血症で呼吸筋の疲弊が顕著で、リハビリで運動負荷をかけると呼吸仕事量と呼吸器サポートとのミスマッチを起こして、Ⅱ型呼吸不全にシフトしているように思う」
「まずはAさんが成功体験を得られるように、呼吸器サポートと酸素濃度のレベルを上げれば、離床の機会やきっかけを作れそうじゃないかな。段階的に進めて、その時間軸で病状もより安定化して、結果的にリハビリも進みながら、呼吸器離脱は進められると思う」
「栄養は経口摂取もできるようになったし、術前の全般的な栄養状態や、もともとの職業柄の筋力量をみても、全身の回復可能性は早期に期待できる。この点はNSTにも意見を求めてみよう」
リーダー「そうか、そういったことを話し合って、リスクも考えながら、全体でケアプランを立てていければいいですね」
多職種カンファレンスをもとに離床機会が増える
この後、多職種カンファレンスが開催されました。安全面についても十分に話し合われ、複数の医師と看護師を調整して集めて行っていく計画を練りました。
そして、薬剤師には薬剤効果と調整のモニタリング、CEには移動式人工呼吸器の準備、トラブルシューティング、ICU医師にはAさんの運動負荷に追従できるよう呼吸器サポートレベルの適宜調整指示が得られるよう調整しました。
その結果、Aさんの可動性は飛躍的に向上し、せん妄や二次的合併症の発症はなく経過し、離床ができるようになりました。
さらに段階的に人工呼吸器からも離脱ができ、第32病日に一般病棟へ転棟、第40病日には軽快し、Aさんは退院することができました。
※この記事は『エキスパートナース』2016年2月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。