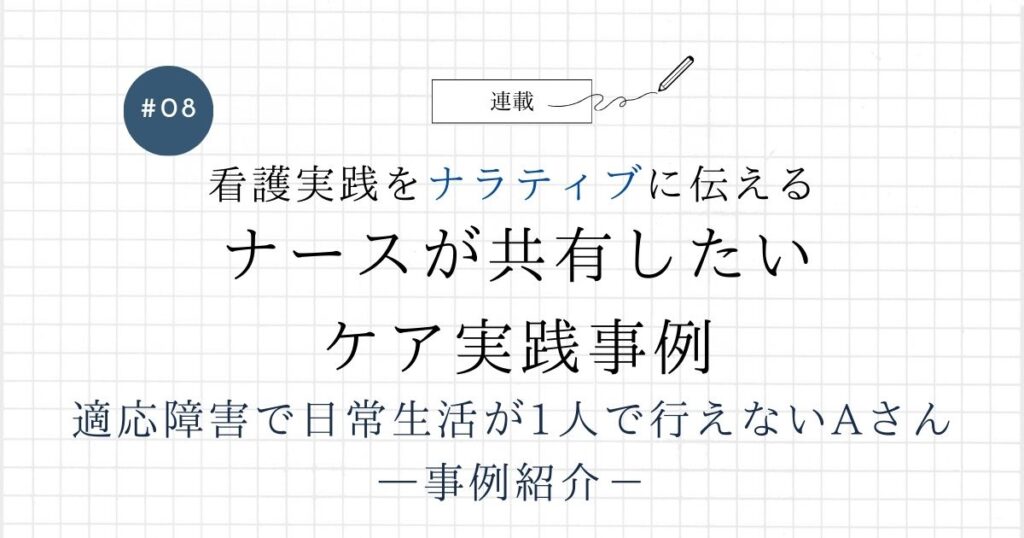事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は適応障害により、日常生活が1人で行えなかった患者さんの事例を紹介します。
〈目次〉
適応障害*により、日常生活が1人で行えなかった患者さんとのかかわり
初回面接で伝わってきた“試す”という評価基準
Aさんとのかかわり方の統一により得られたこと
適応障害*により、日常生活が1人で行えなかった患者さんとのかかわり
今回紹介するAさんは、22歳の女性で、適応障害の患者さんでした。BMI「40」の肥満という以外は身体的な異常はなく、1人で動けるはずなのに、排泄行動や入浴ほかのADL(日常生活動作)が1人では行えず、依存的で訴えが多い方でした。
反面、看護師の提案に対しては、常に「イヤ」「やりたくない」など拒否的で、病棟ではAさんに対して陰性感情をもつ看護師が多くいました。
今回、病棟プライマリーナースのB看護師から「Aさんにどのようにかかわったらよいか、わからない」と相談があり、専門看護師である私が介入することになりました。
Aさんの両親はAさんが幼少のころに離婚していたため、Aさんは病弱な妹と、精神的に不安定な母親と3人で暮らしていました。幼少期や学生時代は、いじめに遭うことが多かったようです。家では、Aさんがアルバイトと家事を1人でこなし、家族の生活を支えていた時期もあったとのことです。
詳細はわかりませんが、数年前に妹、そして1年前に母が、いずれもAさんが外出中にお亡くなりになりました。以後、Aさんは生活保護を受給し1人で生活をしていましたが、徐々に不眠、抑うつ気分などの症状が出現し、活動性が低下していきました。
そして、とうとう身の回りのことが1人でできなくなり、ほぼ寝たきりの状態となってしまったため、症状の改善と生活の立て直しのために入院となりました。
*執筆当時、『ICD-10(国際疾病分類第10版)』により、「適応障害」と診断された
初回面接で伝わってきた“試す”という評価基準
私が初めてAさんに会ったのは、入院後、約4週間が経過したころでした。B看護師からの情報では、意欲の低下の改善は見られず、1日のほとんどをベッド上で過ごしているとのことでした。
肥満も相まって、1人では排便後の保清ができない、便汚染していても下着を取り替えないなど、必要最低限のADLも保てない状態が続いていたそうです。
また、依存的で身体愁訴などの訴えが多くて困っているとのことでした。B看護師は、身体愁訴に対しては、背中をさすったり、マッサージしたりすると、比較的訴えがおさまると話していました。
私はB看護師とベッドサイドにうかがい、「いろいろな病棟を回りながら患者さんが早く退院できるようにお手伝いをしている看護師です」と自己紹介しました。
その後10分程度、雑談を行いました。Aさんは、私が何者であるのかを探るような様子はありましたが、私が継続的にかかわらせていただくことに拒否はなく、すんなりと受け入れてくれました。
Aさんは、幼少期に両親が『精神的な安全基地』として機能せず、愛着形成がうまくできなかったために、慢性的な見捨てられ不安や自己否定感を抱えていると考えられました。
対人関係のとり方が不安定なのは、“他者が自分を受け入れてくれる存在であるか”に非常に敏感で、その評価基準が“自分の欲求を受け入れてくれるかどうか試すこと”になっていたからだと考えられました。Aさんにとっては、わざと嫌がるようなことをしても見捨てずにかかわってくれる人が合格なわけです。
このようなAさんにとっては、まず、他者と健康的な人間関係を築いていく経験や“信頼できる人がいる”という感覚をもてることが重要であると考えました。
そこで、Aさんと健康的な関係を築くために、“試す”というAさんの評価基準に振り回されず、22歳の女性というAさんの健康的な部分にはたらきかけながら、Aさんの依存欲求を満たしていく方法を検討しました。
また、身体感覚の歪みや人との境界があいまいであると考えられたので、タッチングを取り入れながら時間をともにするケアが有効ではないかと考えました。
さらに、Aさんの自己肯定感が少しでも高まるよう、肯定的なフィードバックを積極的に用いることにしました。
Aさんとのかかわり方の統一により得られたこと
Aさんが“試す”必要がないように、Aさんから要求があったときにかかわるのではなく、毎日、ある一定時間、Aさんにかかわる時間をもつことにしました。
具体的には、「その日の日勤帯の担当看護師が、1日1回15分間、一緒にストレッチとマッサージを行う」というプランを立案しました。
さらに私とB看護師は、散歩に一緒に出掛けるなど、Aさんと過ごす時間をできるだけ多くとるようにしました。また、Aさんの健康的な部分に焦点を当てながら、セルフケアの向上をめざしていくというかかわり方を病棟看護師全員で統一して行いました。
例えばAさんは、年齢相応におしゃれや美容に興味をもっていたため、おしゃれの話題を利用して更衣を促したり、Aさんがあこがれる女性看護師から“美肌の秘訣”を話してもらいながら、さりげなく洗顔を促してもらったりしました。
そしてAさんにかかわる際には、どんなにささいなことでも、達成できたことを褒めたり、一緒に喜ぶという、肯定的なフィードバックを用いました。
病棟全体でかかわり方を統一してから1週間が経過したころから、Aさんの行動面に変化が現れました。笑顔が多くなり、散歩やストレッチなどスタッフと過ごす時間を楽しみに待つようになりました。
そして、2週間経ったころには、スタッフからの提案も素直に受け入れるようになり、それまでスタッフに依存的であったADLも自立して行えるようになりました。
1か月後には、活動性が上がったことで体重減少も見られました。効果が数値になって現れ視覚化されたことで、Aさんは自発的に他患者を誘ってストレッチを行うなど、対人交流も見られるようになっていきました。
スタッフ間では、日々のカンファレンスの中で、Aさんの行動面の変化について共有しました。また、肯定的なフィードバックがAさんの行動の動機づけになっていることや、おしゃれやストレッチなどAさんの“健康的な部分”を強化することがセルフケアの向上につながっていることなど、日々のケアの意味について共有しました。
スタッフはAさんの変化が実感できたことで、さらに積極的にAさんにかかわるようになり、スタッフとAさんの関係性が深まる……というように、相乗効果が生まれました。
Aさんは依存的で訴えが多い方でしたが、Aさんの病理に振り回されるのではなく、健康的に依存欲求を満たすということが効果的であったと思いました。 また何よりも、両親と愛着をうまく形成することができなかったAさんにとって、病棟看護師がどんなときも見放さない態度で、安定した対人関係を示したことが、Aさんの行動変化に結びついたのだと思います。
※この記事は『エキスパートナース』2016年3月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。