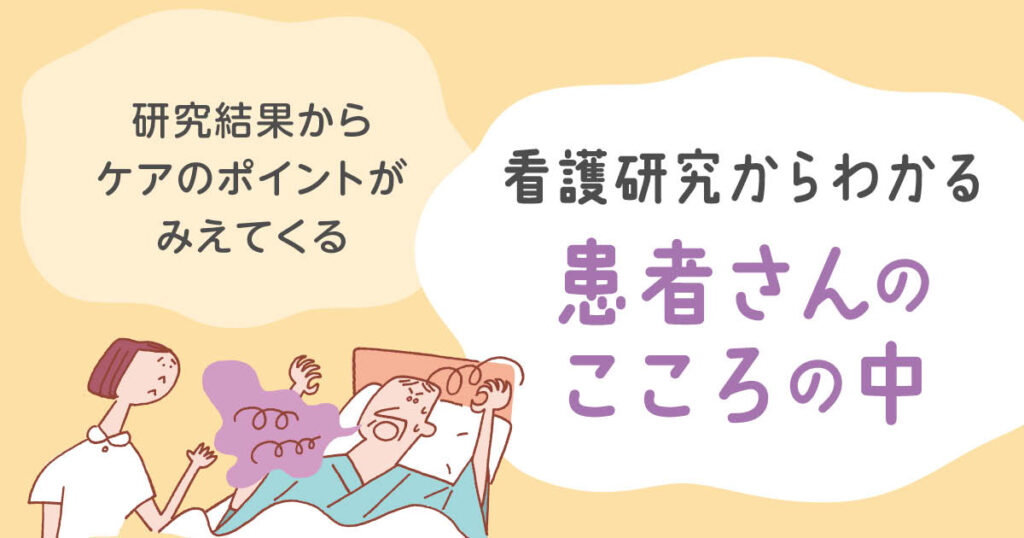不穏・興奮・せん妄などを呈する患者さんは、ICUでの記憶にゆがみがあり、その体験の確認作業や理由づけを行うことが研究からわかりました。研究結果をもとに、実践したいケアを紹介します。
前回の記事:ICU患者の記憶にゆがみ?不穏・興奮・せん妄の影響とは【看護研究#1】
患者さんの主観的体験世界を知り、支援者だと伝えよう
●患者さんの非現実的な体験も患者さんにとっては事実だと考える
●患者さんの体験を否定せず耳を傾ける
●自身の記憶のゆがみから解放されたがっている場合は、支援を行う
患者さんの主観的体験世界を想像する
私たち医療者は、患者さんの不穏・興奮・せん妄状態を“危険行動”“手に負えない”“つじつまが合わない”と表現することが多いです。
これは、医療者側が感じたことを言葉にしていますが、患者さんは前回の研究・発見2で示したような体験をしているのです。
また、幻覚で見たものは、夢とは違って現実のできごとのように迫ってくると表現している人々もいました。
そのような体験を自分のなかで整理できず、 苦悩し解放されようと努力している患者さんの思いを知ることが大切です。それを理解することができれば、患者さんが不穏やせん妄などの状態にあっても医療者が体験を想像することができ、対応のヒントがみつかるのではないでしょうか。
研究プログラムの内容を活用し患者さんの精神的支援を行う
ICU体験でのゆがんだ記憶から患者さんが解放され、身体的にも精神的にも健康を取り戻すために、『記憶のゆがみをもつICU退室後患者への看護支援プログラム』を作成しました。このプログラムの最終的な目標は、「ICU体験の整理ができ、混乱や不安がないこと」です。
このプログラムをICUから退室した記憶のゆがみを呈した患者さんに適用した結果、適用した患者さんたち(20名)のほうが、適用しなかった患者さん(31名)に比べ、不安状態(1.6 vs 3.6)、うつ状態(2.5 vs 4.8)、心的外傷後ストレス障害(posttraumatic stress disorder、PTSD)傾向(4.9 vs 10.7)において有意に改善している結果となりました(p<0.05)。
また、「話してよかった」「自分の体験について納得できた」といったような声が聞かれました。
この研究が行われる前は、ICUで明らかにつじつまが合わないことを言っていた患者さんに対応するとき、「そのことに触れてよいかどうかわからない」「記憶がない患者さんにICUのことを触れてはいけないのではないか」という看護師の迷いがありました。
しかしこの研究から言えることは、患者さんは話したい、 話を聞いてもらいたいと思っているということです。明らかに幻覚・妄想だったとしても患者さんにとって起こったことは事実であり、それを否定しないで聞いてほしいのです。
さまざまな患者さんがいるので、話したくないのに無理に聞いたり、知らなくてよい事実を突きつけたりすることは厳に慎まなければなりませんが、患者さんが記憶の整理や記憶がないところを埋めたいと思っている、事実の確認を必要としているなどの思いがないかどうかを確認し、記憶のゆがみから解放されることをお手伝いしていただければと思います。
このプログラムは、研究のなかではICU退室後訪問としてICU看護師が行うことを前提として作成しました。
実際には、「患者さんのICU退室後に訪問ができない」「ICU後方病棟の看護師だけど患者さんを支援したい」など、さまざまな立場のかたがいらっしゃると思います。
多様な立場のかたが、このプログラムのエッセンスを理解し、活用して患者支援に貢献していただければと思います。
この記事は会員限定記事です。