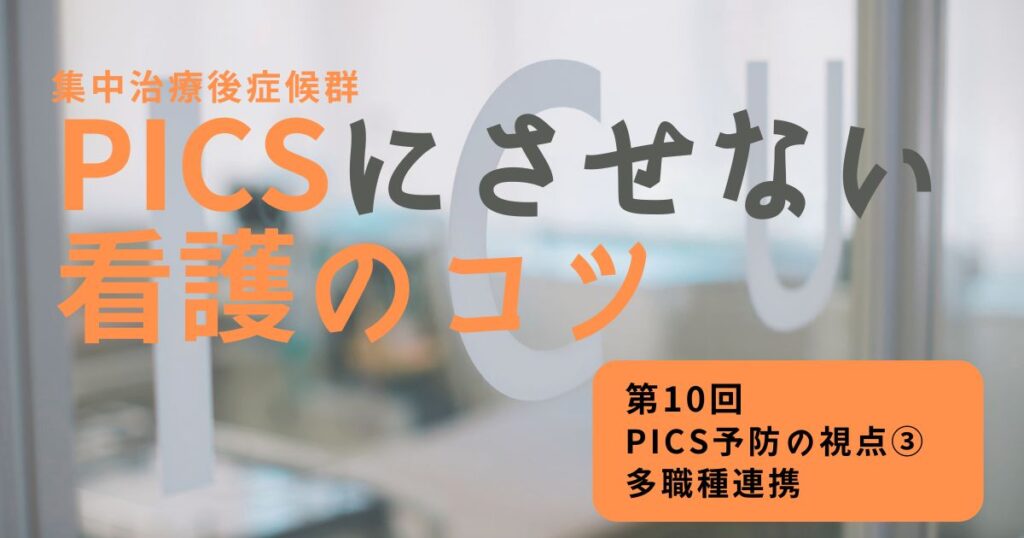一般病棟でも注意しておきたいPICS(集中治療後症候群)についてわかりやすく解説。今回は、医師、看護師、理学療法士、作業療法士など、多職種でPICS予防に取り組む重要性に関して紹介します。
なぜ、PICS対策をみんなでやるのだろう?
ここまでの文章を読まれたみなさんには、PICSというとなんだか新しい言葉のように感じられているかもしれません。ですが、そうではありません。昔から、少し調子が悪くなった患者さんは、ADLが低下したり、なんとなく認知機能が落ちていることを疑わせたり、あまりしゃべらなくなったりとしていたのではないかと思います。
そうした患者さんには、みなさん苦労された記憶があるのではないでしょうか。苦労して、答えがみえず、リハビリスタッフや皮膚・褥瘡を専門としている看護師・栄養士、それに家族などさまざまな人に相談したり、協力してもらったりしながら、なんとか元気になってもらったり、退院できるように調整したりしたはずだと思います。
ズバリ、その患者さん、今でいう「PICS患者さん」かもしれません。今も昔も、こうした患者さんは、あちこちの調子が悪くて、いろいろな人(専門家や家族含む)の助けが必要なのです。そして、いろいろな人の助けは、悪くなってからだけでなく、悪くならないように予防するときにも必要になります。多角的な目線でチェックすることで抜けなく、かつ、多職種で行うので1人ひとりの労力が少なくすみ、無理なく予防できるようになるというわけです。
PICS対策には、多くの非医療従事者が含まれていることが望ましい
多少、個人的な見解が入っていますが、協力が必要な方には、たくさんの非医療従事者が含まれているほうがよいと思っています。つまり、患者さんも、その家族も、また地域の人々にもPICS症状を知ってもらい、PICSを予防する早期に、治療やリハビリテーションに取り組むなどの姿勢が必要であると考えています。
そのためにも、非医療従事者の認識を変えてもらう必要があります。例えば、病院から帰ってきたら人が変わってしまったように感じた場合、「もしかしたらPICS症状で手助けが必要なのかもしれない」と思ってもらえるように啓蒙活動をする必要があります。
また、少なくとも医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、栄養士などの各専門職間で、PICS症状に関する理解を深める必要があります。その理解があってこそ、患者さんにPICS症状がみられた場合、各専門職にお願いをすることができるようになりますし、また、各専門職に診療報酬など含め、PICSに具体的にどのような対応が可能であるか協議してもらうこともできるのではないかと思います。
1つの例として、ABCDEFGHバンドル(第3回参照)を使用してICUでPICSを予防するために多職種で取り組む方法を紹介します。ここにはICUでの一般的なPICS予防策が記載されていますが、一般病棟でも使用できます。
例えば、浅い鎮静、せん妄予防などは、不穏な患者さんへの薬剤を医師や薬剤師とともに協議して使用する(場合によっては使用しない)などが含まれます。また、早期離床を達成するためには、筋肉をつくる栄養が十分であったほうがよいため、栄養士との協議は欠かせません。
このように、こうした要素に関して各専門職と話し合いならPICS治療・予防を進めていきます。
PICS対策に向けて多職種で同じビジョンを共有しよう
この記事は会員限定記事です。