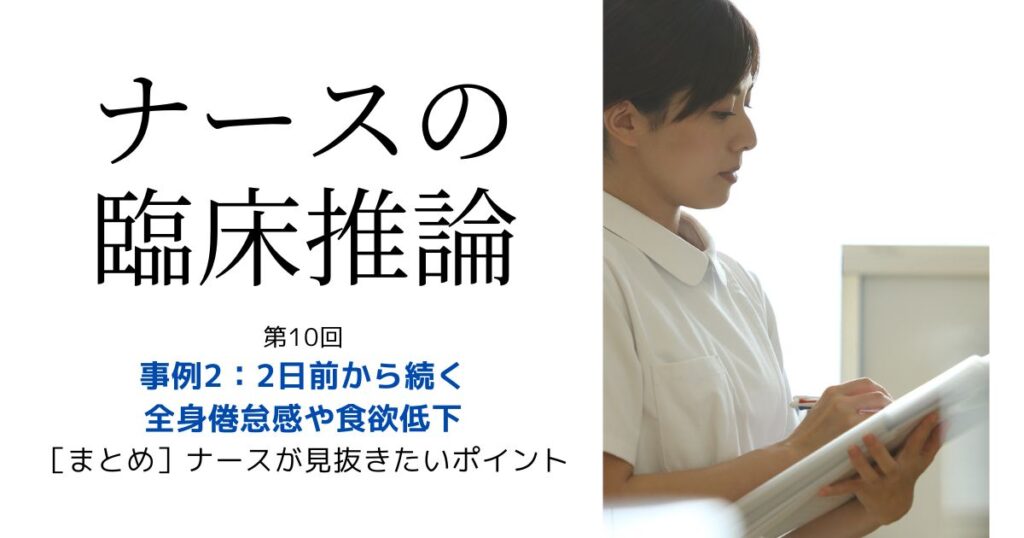患者さんの訴えの裏に隠された疾患を見逃さないために大切な「臨床推論」。どのような思考過程を経て臨床診断を導き出しているのかを考えていきます。今回は第7回で紹介した全身倦怠感や食欲低下を訴える患者さんの事例の、ナースが見抜きたいポイントを紹介します。
高齢者の、説明のつかない”全身倦怠感”は危ない
主訴は全身倦怠感と食欲低下でした。人間、調子が悪ければ、たいていこの症状は現れるものです。鑑別がわからないなりにも、今回は2日前からの急な悪化であったこと、またわざわざ夜に受診したことなどから、緊急度は高めに考えて行動するほうが得策といえそうです。
硬膜下血腫の患者さんは、倦怠感や発動性低下というわかりにくい症状で受診するものです。特に高齢者の、他に説明のつかない倦怠感では「硬膜下血腫」も考えます。最終的に否定されるまで考えておきましょう。
また、病棟でこのような状況に出合うとすれば、病棟内での転倒後の倦怠感や意識障害でしょう。臨床で非常によく出合う疾患です。症状が数日以内に遅れて現れてくるのがポイントです。夜間転倒があった場合は、夜勤者は必ず申し送りのときに硬膜下血腫の可能性について引き継ぎをしましょう。
症状前後の時間軸に焦点を当てた病歴や患者背景をチェック
診断のための有力な情報が、主訴以外少ない場合はどうすればよいでしょうか。早めに診察や検査に進むことも重要ですが、さらに一歩踏み込んで病歴を聞いてみる、または病歴のクリアでない部分を明らかにしようという執念が、ときに大きな発見をもたらすことはよくあります。
その有効な方法が、「症状前後の時間軸に焦点を当てた病歴や患者背景の把握」なのです。
診断がわかれば治療は決まります。診断があいまいなまま、いたずらに対症療法を行うのは的外れです。正しく病状を把握するために情報を詳細に集めることは、回り道のように見えて、最も近道です。
こういった病歴の技術は本来医師が得意とするところですが、病歴は医師の専売特許ではありません。こまやかな洞察力にすぐれたナースが、病歴において医師を上回ることはたびたびあります。エキスパートナースは、ぜひ病歴にこだわるナースであってほしいと願っています。
鑑別が難しいときこそ、問診を
鑑別のきっかけがみえないことは日常診療でときどき遭遇します。そんなときこそ診察の基本に立ち返ることが大事です。
診断困難な症例に活路を与える方法、それは「病歴、病歴、病歴」です。
一般的に、バイタルサインや全身状態が安定している場合、できる限り患者さんの全体像を把握するための病歴をとることが望ましいと思います。
例えば、衣食住について、家には誰と住み、1日をどのように過ごすのか、今までどのような人生を送ってきて、何か直面している悩みなどはないか、などです。その理由は、ふだんの生活の様子を把握することで、俯ふかん瞰的な視点から今回受診に至った症状を考え直すことが可能になることが多いからです。そのときにはじめてみえてくるものもあります。
Bさんの場合は、普段は快活で友人らとハイキングに出かけることからADLは良好かつ外交的な性格、またキルティングの趣味、救急受診にもかかわらず身なりもきちんとしていることからも高い生活・文化水準であることがうかがえます。
この記事は会員限定記事です。