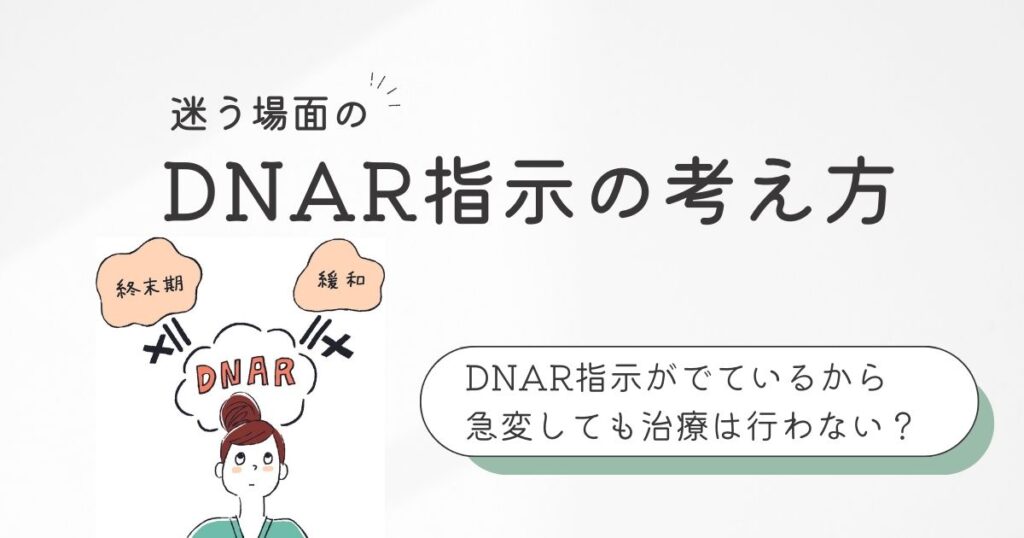DNAR(do not attempt resuscitation)とは、心停止時に心肺蘇生(CPR)を実施しないこと。“ナースが誤解しがちな点”を解説の切り口とした、全5回の連載です。「誤解」を「正解」にしましょう!
【第1回】DNAR指示、看護師の正しい対応を解説
DNARは「治療をしないこと」だと思っていませんか?正しくDNARを理解したうえで、医療チームで方針を検討することが大切です。
〈目次〉
●よくある誤解①「DNAR指示がでているから急変しても治療は行わない」は間違い!
・DNARとは“積極的な治療を行わないこと”ではない
・「DNAR指示=治療差し控え」になってしまっている現状
・DNAR指示が有効なのは、心停止時のみであることを覚えておこう
・「心停止時」を「急変時」にすり替えるのは危険
・DNARの“正しい”定義
【第2回】DNAR指示と終末期医療、終末期医療と緩和医療は異なる
「DNAR指示=終末期医療」「終末期医療=緩和医療」という2つの誤解を取り上げています。インフォームドコンセントの具体例も参考にしてみましょう。
〈目次〉
●よくある誤解②「DNARだからもう緩和医療にシフトしよう」は間違い!
・まず、「緩和医療」についての誤解がある
・患者側が誤解のないように合意形成を
・終末期医療の合意は、DNARとはまた別に行う
・Partial DNAR指示は行うべきでない
・DNARの“正しい”合意形成
【第3回】DNAR指示は患者の状況によって方針を変える
患者や家族の気持ちは、病状や生活状況の変化などで揺れ動くもの。DNARの同意は撤回できるので、繰り返し検討を重ねる必要があります。
〈目次〉
●よくある誤解➂前の入院でDNAR指示が出ているから今回も同じ方針で…は間違い!
・DNARの同意は撤回可能。一度同意があった後も検討を
・早い段階でのDNAR指示の注意点
・DNARに関する方針や検討プロセスは共有できるように
・DNARは同意後も検討を重ねる
・「終末期医療の方針の再確認」
【第4回】DNARの方針検討における看護師の役割
看護師が専門職の1人として、DNAR指示の決定に参画できるようなシステムづくりが重要。患者や家族、医療チームが集まるインフォームドコンセントでの行動がカギとなります。
〈目次〉
●よくある誤解④「DNAR指示は医師が決めることだから…」は間違い!
・看護師もDNAR指示の決定に参画できる機会を
・インフォームドコンセントでは“観察者”で終わらない
・インフォームドコンセント後のかかわりにつなげる
・DNARの決定には看護師も介入
【最終回】医療現場でDNARに関する教育を受ける必要性
DNARにまつわる疑問があったときは、ガイドラインや勧告を参考に。また患者・家族の理解度を確認し、情報の伝え方などを医療チームと検討し共有しましょう。
〈目次〉
●DNARに関する教育の機会が求められる
●ガイドラインや勧告を指標に
●患者の理解度を確かめながら意思決定支援を