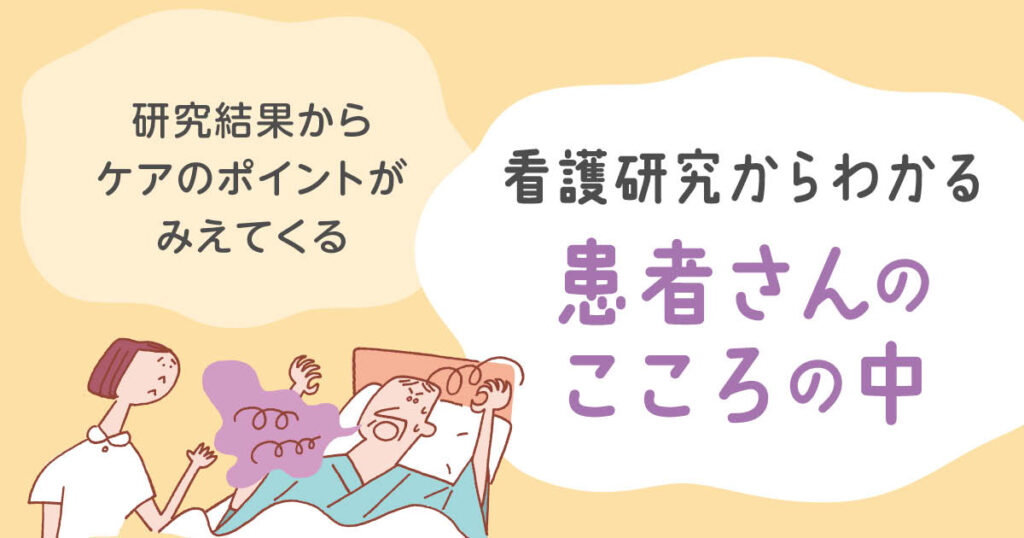血液透析を行う慢性腎不全患者さんの心理についての研究結果をもとに、実践したいケアを紹介します。患者さんの気持ちを理解し、寄り添うために看護師ができる支援を紹介します。
前回の記事:血液透析を受ける慢性腎不全患者の心理とは?【看護研究#15】
患者さんの気持ちを知りたい、という姿勢で患者さんに向き合う
●患者さんの気持ちを断定せず、気持ちを知りたい、という姿勢で患者さんに向き合う
●患者さんの気持ちを聴いたときに感じる、看護師自身の気持ちを言葉にする
●気持ちを表現する的確な言葉が見つからないときは、身体に生じる感覚を言葉にしてみたり、たとえなどを用いてみる
透析患者さんの気持ちに寄り添えるよう、理解するための方策を見つけ出す
日本人は、他者に自分を理解してもらったと感じるとき、日常的には「私の気持ちをわかってもらえた」と表現します。
“気持ち”は日本人にとって、自分の中核を表現している言葉ですが、日常的な用語のために、学問用語として使われません。
しかし、看護の現場では、“患者さんの気持ちを理解する”という表現は、患者さんの心理や存在意味的(スピリチュアル)側面の理解と同義語的に使われています。 また、アメリカの臨床心理学者C.Rogersはその理論の基本的命題として、個人はすべて絶え間なく変化している経験の世界に存在している、と述べています。この経験世界が、日本文化では“気持ち”に相当するのではないかと考えます。
1)患者さんの気持ちを聴いたときに感じた看護師自身の気持ちを素直に言葉にしてみる
本研究から、“気持ち”は次のように説明できます。
●人の内部および外部から生じるできごとを経験するときに、人に生じる状況の認知、引き起こされる感覚や感情・情動・思い・思考などが融合/統合した経験の世界
●日常生活のなかで言語で表現される部分と、言語で表現できないが確実に感じている部分の経験をすべて含む
共感的理解に基づいて他者に理解されたとき、人は「気持ちを理解してもらった」と感じるとともに自分自身の存在を尊重されたと感じます。
そのため、患者さんの気持ちを理解するには、まず、患者さんの気持ちを知りたい、という姿勢で患者さんと向きあうことが最も大切です(C. Rogersのいう「積極的関心」)。誠実に向き合う勇気と覚悟も必要です。
まずは、患者さんの話を聴いたときに看護師自身が感じた気持ちを素直に言葉にしてみましょう。そして、「〇〇な気持ちを抱いていらっしゃるように私は理解しましたが……」などと確認してみましょう。
看護師が、自分自身が感じたことや気持ちを言葉に表すことができなければ、患者さんの気持ちを言葉にすることは難しいでしょう。気持ちを表現する的確な言葉が見つからないときは、身体に生じる感覚を言葉にしてみたり(「胸がわさわさする感じ」など)、「ガラス張りの箱に入っているような気持ち」など、たとえなどを用いてみることも、気持ちを表現する助けになります。
看護師が自身の感覚的経験や気持ちを素直に表現できれば、患者さんも気持ちを話しやすくなります(C. Rogersのいう「自己一致」)。
しかし、患者さんが自分から語れる状況でないときに、表現だけ「〇〇のような気持ちなんですね」とあてはめたり、断定するようなことはしてはなりません。
2)「経験している気持ち」を口に出して共感の練習をしてみる
患者さんがどのような気持ちなのか、【第15回】・表1の「経験している気持ち」を実際に看護師が口に出してみるのも1つの方法です。
看護師が「透析をやりたくない」という患者さんの理解のために、「透析をやりたくない」と口に出したとしましょう。看護師自身は透析をする状況ではないので、「透析をやりたくない」という患者さんの気持ちと同じ経験はできません。
この記事は会員限定記事です。