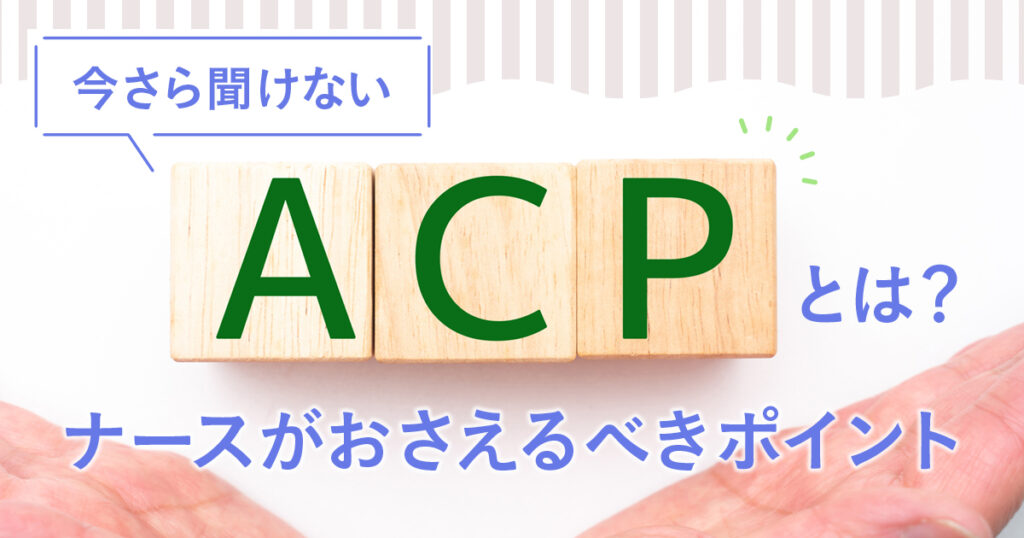国内外のACPの定義、話し合いの内容やポイント、メリットと課題、看護師に期待される役割について紹介した全7回の連載です。看護の場面によって異なるACPのコツも合わせて解説しています。
【第1回】アドバンス・ケア・プランニングの基礎知識
〈目次〉
●ACPの定義
①ヨーロッパ緩和ケア学会(EAPC)の定義(2017)
②厚生労働省の定義(2018)
③日本版ACPの定義
●ACPで医療者と患者さんが話し合う内容
●ACPのメリットと課題
●ACPにおいて看護師に期待される役割
【第2回】ACP、DNAR、リビング・ウィルの違いは?
【第3回】継続的な意思決定支援のポイント
〈目次〉
●ACPで決めた方針は変更してもよい?
●意思決定能力が十分でない場合のACPの進め方は?
・厚生労働省のガイドラインにおけるACP
●看護師による意思決定支援のポイントは?
【第4回】急性期の重症患者へのアプローチ
〈目次〉
●ICU患者にとってのACPの重要性とは?
●ICU患者のACPにおいて看護師に必要な能力とは?
●ACPの開始時期はどうする?
●患者・家族への支援方法は?
【第5回】心不全患者さんへのACP支援
〈目次〉
●心不全におけるACPの重要性
●ACPに対する心不全患者の心理は?
●心不全患者におけるACPの進め方は?
●心不全患者へのACP支援の事例
●心不全患者におけるACPの話し合いの時期
【第6回】訪問看護で行うACPのコツ
〈目次〉
●訪問看護での意思決定支援のポイントは?
●訪問看護での意思決定支援の時期と内容は?
●患者の思いを引き出すには?
【最終回】介護保険施設で行うACPのコツ
〈目次〉
●情報共有シートを活用したACP
●特別養護老人ホームにおけるACPの進め方は?
●介護保険施設でのACPにおける看護師の役割