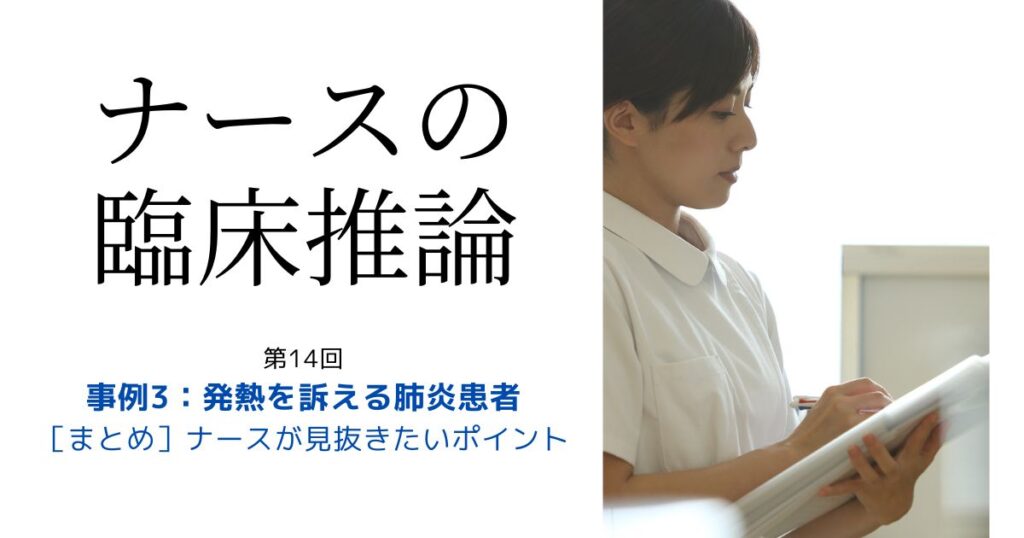患者さんの訴えの裏に隠された疾患を見逃さないために大切な「臨床推論」。どのような思考過程を経て臨床診断を導き出しているのかを考えていきます。今回は第11回で紹介した発熱を訴える肺炎患者さんの事例を通して、ナースが見抜きたいポイントを解説します。
呼吸不全の原因・病態だけでなく、身体所見を詳しくとる
呼吸困難の主な原因は、低酸素による呼吸不全であり、その病態は、①シャント、②拡散障害、③低換気、④換気血流不均衡、⑤静脈血酸素分圧の低下、⑥吸入酸素分圧の低下からなります。これらの原因が2つ以上同時にあることもめずらしくないので、原因を1つ見つけたからといってすぐ結論づけず、しっかり病歴と身体所見をとることが重要です。
患者さんの背景、どういうタイミングで呼吸困難をきたしたのか、咳、痰、胸痛、冷汗などの随伴症状、呼吸回数、副雑音の有無、頸静脈の怒張、下肢の腫脹などの身体所見が重要となります。
低酸素性呼吸不全をきたす疾患・病態
●心房中隔欠損など
●間質性肺炎、細菌性肺炎、心不全
●神経筋疾患、薬物中毒異物、低K(カリウム)血症など
● COPD、喘息、肺塞栓など
●貧血、心拍出量の低下など
●有毒ガスの吸入、高地環境など
上記の疾患があると以下の病態が引き起こされる
①シャント
②拡散障害
③低換気
④換気血流不均衡
⑤静脈血酸素分圧の低下
⑥吸入酸素分圧の低下
行った治療の効果が見られなければ、病歴と所見をとり直す
本症例で一歩踏み込んで診察と病歴をとり、肺塞栓を見逃さずに診断できた理由として、入院後の酸素投与に見合った酸素化が得られなかったことがあります。胸部単純X線の画像は提示しませんでしたが、担当医は引き継ぎの際、この症例の肺炎像で、ここまで酸素化がひどいのはおかしいと考え、意識して病歴と所見をとり直しました。
いつも私たちは、レジデントに対して「主訴から予想される身体所見、主訴と身体所見から予想される検査所見を考えながら身体所見をとり、検査をオーダーしなさい」と指導しています。
治療も同様で、それぞれの病状に対して治療・処置をすると得られる反応や経過は、おおよそ予測することができます。その予想に反する経過がみられた場合、診断が間違っていたり、治療が不十分だったりします。治療に見合った効果が得られない場合は、診断の誤りや治療の不十分を考慮し、病歴と所見をとり直すことも必要です。
この記事は会員限定記事です。