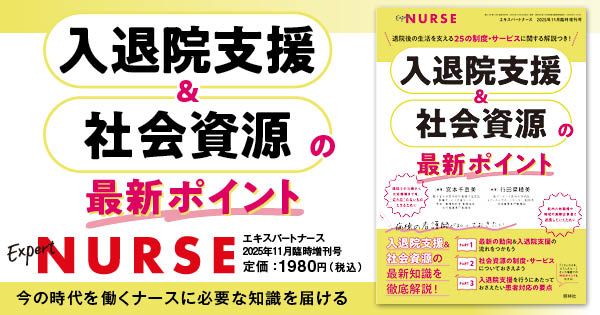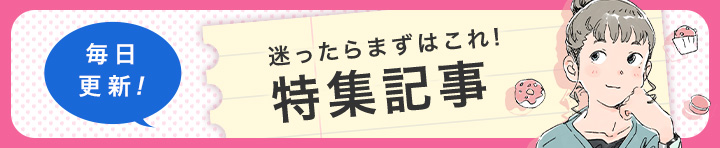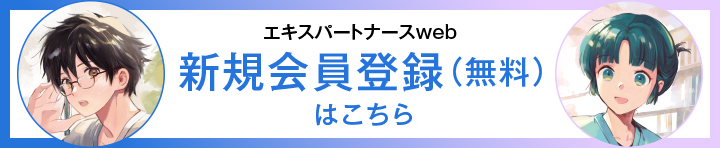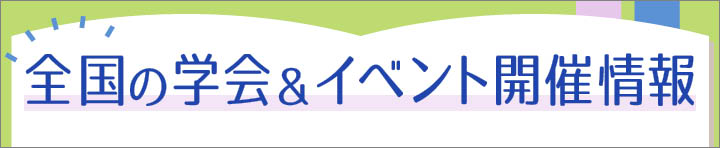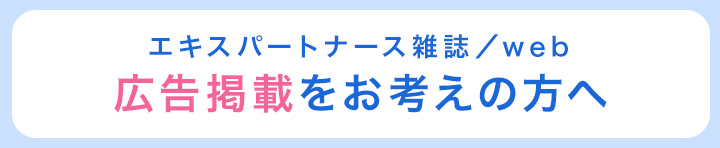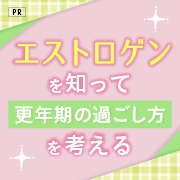-
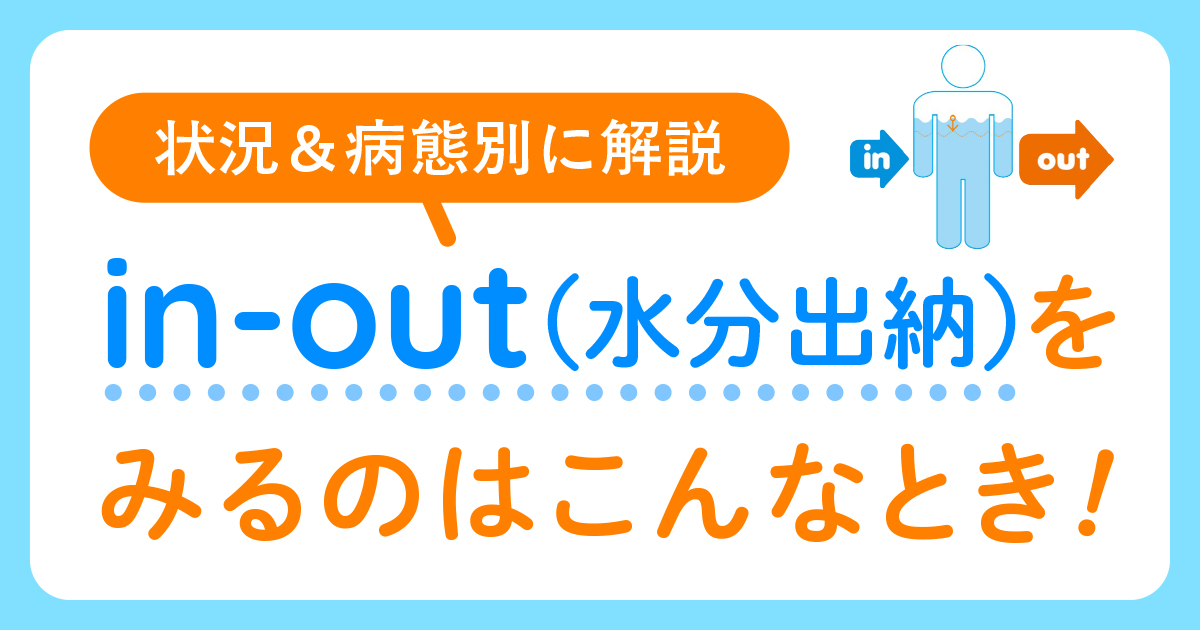
低張性脱水を見抜くには?利尿薬使用中の水分出納管理【in-out】
特集記事 -

川嶋みどり 看護の羅針盤 第352回
読み物 -
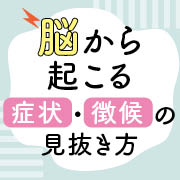
意識障害の症状・メカニズム・鑑別のポイント:意識混濁を中心に解説
- 会員限定
- 特集記事
-

【新規会員登録(無料)キャンペーン】PDFを1冊まるごとプレゼント!
- 会員限定
- お知らせ
-

川嶋みどり 看護の羅針盤 第351回
読み物 -
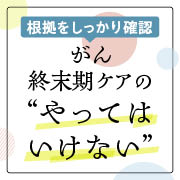
終末期せん妄への対応:身体的拘束の弊害と非拘束ケアの実践法
- 会員限定
- 特集記事
-
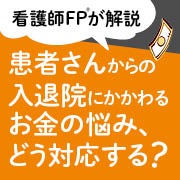
【連載まとめ】看護師FP®が解説!患者さんからの入退院にかかわるお金の悩み、どう対応する?
特集記事 -
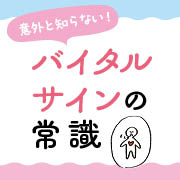
【連載まとめ】バイタルサインの常識
特集記事 -

【連載まとめ】拘縮患者さんへのケア
特集記事 -
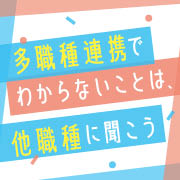
【連載まとめ】多職種連携でわからないことは他職種に聞こう
チーム医療
特集記事
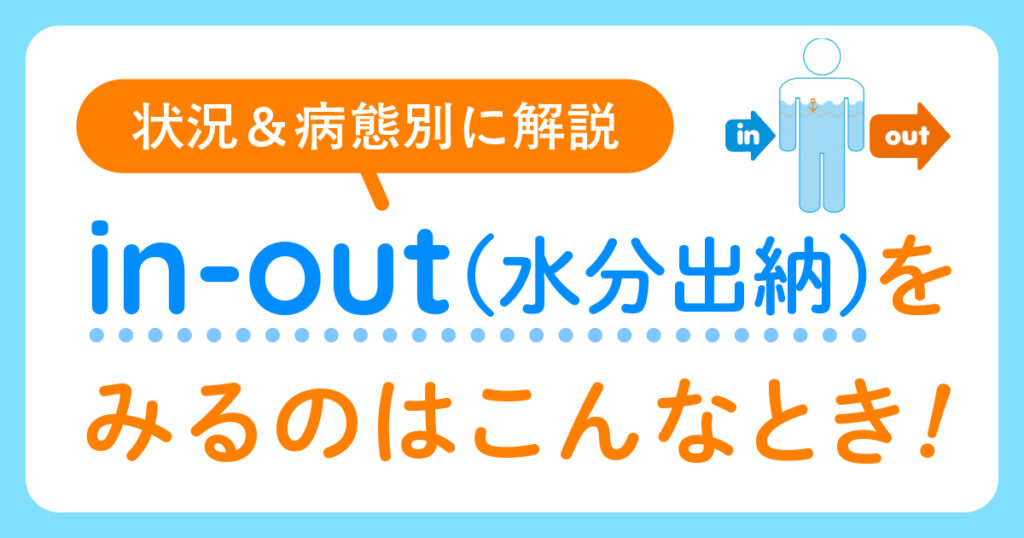
低張性脱水を見抜くには?利尿薬使用中の水分出納管理【in-out】
特に意識して水分出納(in-out)を確認すべき状況や病態とは?今回は利尿薬使用中、低張性脱水を考慮して水分出納を見るポイントについてです。利尿薬の電解質バランスへの影響や副作用も紹介します。 「in-out(水分出納)をみるのはこんなとき!」の連載まとめはこちら 脱水(in<out) 利尿薬によって尿量が増え、低張性脱水になる可能性がある 利尿薬を使用すると、尿量が増えます。利尿薬の種類によって薬剤の作用時間が異なりますが、尿量が急激に増えることにより、低張性脱水になる可能性があります。 またそれによって電解質バランスの崩れや循環動態の変化もありうるため、全身状態に影響があることを念頭に置き、in-outとその他の症状も観察していくことが重要です。 in-out:利尿薬の電解質バランスへの影響 利尿薬には、いくつか種類があります(図1)1。 図1 各種利尿薬の作用部位と電解質バランスへの影響 (文献1より引用、一部改変) 以下、それぞれの薬剤の特徴をもとに、in-outバランス(特に電解質バランス)への影響を示します。 ①ループ利尿薬 最も強力な利尿薬ですが、腎血流量・糸球体ろ過値を減少させず、腎障害時にも適することから、多く用いられます。 ループ利尿薬の代表的な薬剤・フロセミド(ラシックス®)では、作用発現時間が内服で1時間、静注で5~15分です。最初の1時間で最大の尿量が得られます。 作用機序として、ヘンレループ上行脚でのNa-K-Cl共輸送体を阻害するため、これらが尿として排泄され、低カリウム血症、低カルシウム血症、低マグネシウム血症と、それによる代謝性アルカローシスが起こる可能性があります。 ②サイアサイド系利尿薬 降圧薬として使用されています。腎血流量低下作用があるため、血清クレアチニン≧2mg/dLでは禁忌です。 例としてトリクロルメチアジト(フルイトラン®)では、作用発現時間が2時間、最大尿量は6時間後です。 作用機序として遠位尿細管でのNa-Cl共輸送体を阻害することにより、Naの再吸収を抑制します。レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系が活性化している状態では多くのNaが遠位尿細管に到達してKとの交換を刺激するため、遠位尿細管においてKの排泄を増加させ、低カリウム血症、高カリウム血症と、それによる代謝性アルカローシスが起こる可能性があります。 ③カリウム保持性利尿薬 遠位尿細管に作用し、ごく弱い利尿効果しかないものの、他の利尿薬の電解質代謝異常の補正に用いられます。 例としてスピロノラクトン(アルダクトン®A)では、作用発現時間が徐々(2~4日)、最大の利尿効果が得られるのは2~3日後となります。集合管でのミネラルコルチコイド受容体阻害により、高カリウム血症を起こす可能性があります。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります ④炭酸脱水酵素阻害薬 一般的な利尿薬としては使用されていません。アセタゾラミド(ダイアモックス®)が、呼吸性アシドーシス、緑内障などの症例に用いられています。近位尿細管でのHCO3-再吸収阻害により、低カリウム血症を起こす可能性があります。 ⑤浸透圧利尿薬 浸透圧利尿薬の作用により、糸球体でろ過されても再吸収されません。また、化学変化を受けないため、尿細管内浸透圧が増加して、水・Naの再吸収が抑制されます。脳圧低下の症例に用いられます。 例えばD-マンニトール(マンニットール)では尿量への影響が大きく、濃グリセリン(グリセリン)のほうが尿量への影響が少ないと言われています。 作用機序は、近位尿細管での浸透圧利尿で、利尿以上に血管内ボリュームとして残留した量が多い場合、血漿浸透圧上昇によりうっ血性心不全、低ナトリウム血症などを起こす可能性があります。 利尿薬使用中のin-outの見方のコツ out:利尿薬投与後の尿量変化を観察する 利尿薬投与後は、尿量の流出が増加します。その後、薬剤の効果がなくなり、尿量も低下します。 よって、「利尿薬投与前」と「投与後」のin-outバランスを観察します。マイナス(-)バランスへ大きく傾いて、尿量が低下(尿量<0.5mL/kg/時)、尿性状の変化(濃縮尿)が起こります。それに伴い、血圧低下、心拍数の増加、またモニタリングしているときは動脈圧の呼吸性移動が起こります。 out:利尿薬の副作用を評価する 薬剤の効果が出すぎていないかどうかを、副作用をもとに観察します(表1)。血圧低下やバイタルサインの変化もあるので、モニタリングを開始し、不整脈の出現、心電図変化をともに観察しましょう。 表1 利尿薬の主な副作用 Na状態:低ナトリウム血症症状:●頭痛・悪心・嘔吐 ●筋肉のけいれん ●失見当識 ●反射低下 ●血圧低下注意点:急激な発症の場合は、てんかん発作、昏睡・ 呼吸停止、脳ヘルニアの症状が発現する K状態:低カリウム血症症状:●しびれ・筋脱力・麻痺 ●心電図異常(QT延長、ST低下、T波平坦化、U波出現)注意点:呼吸筋麻痺を起こすと呼吸停止に至る 状態:高カリウム血症症状:●筋力低下 ●徐脈 ●心電図異常(QT間隔の短縮、T波の増高:テント状T波、QRS延長、PR間隔の短縮、P波消失)注意点:高カリウム血症が続くと心室細動(VF)、心停止を引き起こす Ca状態:低カルシウム血症症状:●感覚異常 ●テタニー(低カルシウムに伴うしびれ)注意点:重症化するとけいれんに至る Mg状態:低マグネシウム血症症状:●下肢のけいれん ●筋脱力 ●振戦 ●眼振 ●片頭痛 ●気管支喘息 ●慢性疲労症候群 ●運動機能低下 など注意点:低カリウム血症と合併すると活動電位持続時間延長、QT延長から、トルサード・ド・ポアンツが発生しやすくなる その他合併症症状:●耳鳴り・難聴・めまい ●尿路結石 ●女性化乳房 ●多毛症 など out:循環不全の徴候(ツルゴール反応など)をみる 循環不全、細胞内中毒の状態により、立ちくらみ、倦怠感、頭痛、嘔気・嘔吐、ツルゴール反応低下、腋窩・口腔粘膜の乾燥が起こりえます ツルゴール反応は、主に前胸部の皮膚において、皮膚をつまんだのちに離し、その皮膚が3秒以内に元の状態に戻るかどうかで評価します。戻らなければ「ツルゴール低下」となります。脱水時には、皮膚の戻りが悪くなります。 利尿薬使用中のin-out報告のポイント 尿薬投与後は、いつもの尿量よりはるかに多くなります。薬剤ごとの利尿効果の得られる時間を確認し、利尿薬投与後の尿量への反応や、1日内での尿量の変化、in-outバランスの変化、そして体重の変化について観察します。 あわせて、皮膚の状態や、利尿薬投与前後のバイタルサインの変化(血圧低下、心拍数の増加)、意識レベルの変化(利尿薬の副作用)についても報告します。 利尿薬使用中のin-outを考えた対応 輸液量の確認 利尿効果により脱水になっている可能性があるため、in-outのバランスを観察し、輸液量や飲水量の制限がある場合は飲水できる量を医師へ確認します。 Na補正の準備 利尿薬投与に伴う脱水ではNaが低下しているため、輸液によるNa補正が開始される可能性があります。輸液ルートが確保されていないときは、静脈ラインの確保を行います。 モニタリングの開始 バイタルサインの変化がありうるため、もし行われていなければ、モニタリング(心拍数、血圧、呼吸〈SpO2〉)を開始します。 (第18回) 引用文献1.土田昌子:グループ別利尿薬の役割と特徴.ナースになじみの3つの「くすり」使いこなしガイド,エキスパートナース 2014(6月臨時増刊号);30(8):92-93. 参考文献1.絹川真太郎:循環器系5・利尿薬概略図.山田信博 編,治療薬イラストレイテッド改訂版,羊土社,東京,2009:59.2.大野博司:各論・利尿薬の作用機序と副作用.ICU/CCUの薬の考え方、使い方ver2,中外医学社,東京,2015:260.3.日本循環器学会,日本心不全学会:心不全診療ガイドライン.https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf(2025.6.3アクセス)4.大島千代美:電解質.鶴田良介 編,急性期ケアに必要な輸液の知識これだけBOOK エマージェンシー・ケア2012年(新春増刊),メディカ出版,大阪,2011:24-35.5.戸谷昌樹:輸液と利尿薬との関係について知りたい.鶴田良介 編,急性期ケアに必要な輸液の知識これだけBOOK エマージェンシー・ケア2012年(新春増刊),メディカ出版,大阪,2011:116-124.6.濱野繁:ICUにおける輸液・栄養・代謝管理とケア.道又元裕 監修,ICUビジュアルナーシング 改訂第2版,Gakken,東京,2021.7.Leullmann H,Mohr K,Hein L 著,佐藤俊明 訳:利尿薬.カラー図解これならわかる薬理学(第2版),メディカル・サイエンスインターナショナル,東京,2012:164-169. この記事を読んだ方におすすめ●in-out(水分出納)についての記事一覧●そのほかの連載記事 ※この記事は『エキスパートナース』2016年10月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
特集記事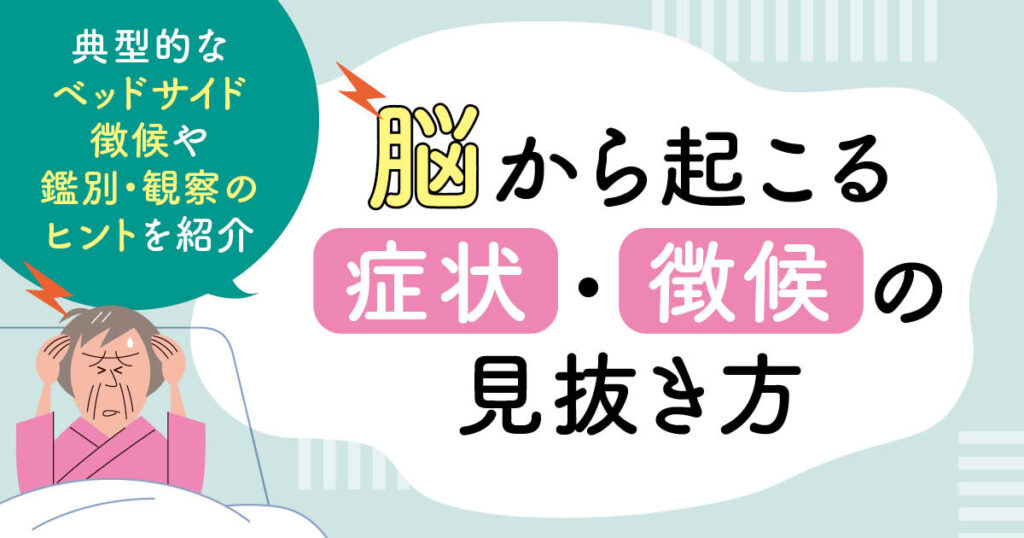
意識障害の症状・メカニズム・鑑別のポイント:意識混濁を中心に解説
意識障害に早期に気づくためには、まず意識混濁を見抜くことが重要です。意識障害の症状、メカニズム、鑑別のポイントを、意識混濁を中心にわかりやすく解説します。 * 前回の記事では、意識障害は意識混濁と意識変容に分類されると説明しました。 しかし、意識障害をとらえる際に、意識変容が単独で現れることは少なく、多くの場合、意識混濁が存在しています。つまり、意識障害に早期に気づくためには、まず意識混濁の有無を見抜くことが大切です。 今回は、意識障害の観察と対応のために重要な、意識混濁を中心に解説します。 意識障害の症状・徴候は? 意識混濁の症状は、覚醒(清明度)の程度によって「傾眠」「昏迷」「半昏睡」「昏睡」とさまざまです(表1)。また症状が軽度の患者であっても、意識変容などが併存していることが多く、患者は自分の状態を正確に伝えることができない状態にあります。 表1 意識混濁の分類(Mayo Clinicの分類)傾眠●刺激を与えないと閉眼して眠ってしまう状態●呼びかけや身体を揺すると容易に覚醒し、指示に従うことができる 混迷●強い刺激を与えるとかろうじて開眼し、指示にある程度反応できる●十分には覚醒させることができない状態 半昏睡●強い刺激を与えると、回避しようとしたり、顔をしかめるなど、ある程度合目的な反応を示す状態●指示に応えることはできない 昏睡●強い刺激(痛覚刺激)を与えても、除脳硬直の姿勢をとるなどの反射的な動き以外、反応がみられない状態●自動的な動きは消失 さらに、意識障害の症状に加えて呼吸・循環・代謝などにも障害をきたしている場合も多く、その原因は中枢神経系にとどまらず多彩です(前回の記事・表1参照)。 意識混濁の原因の鑑別は難しく、私たち看護師には“観察する力”と“観察したことを的確に伝える力”が求められます。 意識障害の事例 ●60 代男性、既往に心房細動あり●訪室すると倒れていた●大声で呼びかけると開眼するが、「ウ~」という発語があるのみ。痛み刺激を与えると右手で払いのける動作あり●脈拍数:60回/分(リズム整)、血圧:180/100mmHg、呼吸数:20回/分(リズム整)●左片麻痺がみられた 事例が起こったのはなぜ? ■「中大脳動脈の閉塞」による“上行性網様体賦活系の障害”からくる意識混濁 ①意識混濁の有無:意識混濁あり②A(気道)、B(呼吸)、C(循環)の評価:現在のところ生命危機に直結するABCの異常なし③意識レベル:JCS「Ⅱ-20」、GCS「E3・V2・M5」④AIUEOTIPS:血圧上昇と片麻痺が観察されることから、脳卒中などの頭蓋内疾患による意識混濁が疑われる●MRI拡散強調画像から、右中大脳動脈の閉塞により脳幹が脳浮腫に圧迫され、上行性網様体賦活系(覚醒機能の維持)が障害されたと考えられる●ただし、意識障害(意識混濁)は「脳」以外にもさまざまな要因で生じる。「意識障害」=「脳」と短絡的に捉えないよう気をつけたい 意識障害のメカニズムとは? 身体の覚醒機能のメカニズムについて、図1に示します。身体の各部からの感覚の刺激は神経線維の活動電位(インパルス)となって脳幹を上行し、大脳皮質へ伝えられます。 このとき大脳皮質へ向かう体性感覚インパルスの一部は、視床と脳幹(中脳・橋・延髄)にかけて存在する上行性網様体賦活系に伝えられます(図1-①)。上行性網様体賦活系は体性感覚インパルスによって興奮し、視床を経由して、大脳皮質や大脳辺縁系に刺激を送ることで覚醒を維持しています。つまり、覚醒機能は上行性網様体賦活系によって維持されており、上行性網様体賦活系が存在する脳幹が障害を受けることで、意識混濁(覚醒機能の障害)を生じます。 また、大脳皮質(図1-②)は体性感覚インパルスが投射されることで認知機能を形成する役割を担い、視床下部には睡眠・覚醒の基本リズムをつくる視床下部賦活系(図1-③)が存在しています。このように、上行性網様体賦活系と視床下部賦活系と大脳皮質が正常に機能することで意識を清明に保つことができ、これらの一部または複数の障害によって意識障害が生じます。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 図1 覚醒機能のメカニズム 意識障害の原因の鑑別ポイント 意識障害の原因を鑑別する方法として「AIUEOTIPS(アイウエオチップス、表2)」というツールが広く用いられています。これに加え、意識障害と併存する症状(表3)を観察することで、原因の鑑別に役立てることができます。 表2 AIUEOTIPS(意識障害の原因の鑑別) Alcoholism(アルコール)急性アルコール中毒、ビタミンB 12欠乏Insulin(インスリン)低血糖、高血糖(糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧性非ケトン性昏睡)Uremia(尿毒症)尿毒症Encephalopathy(脳症)肝性脳症、高血圧脳症Endocrinopathy(内分泌疾患)甲状腺クリーゼ、副甲状腺クリーゼ、急性副腎不全Electrolytes(電解質)Na・K・Ca・Mgの異常Electrocardiogram(心電図)不整脈(アダムス・ストークス症候群)Oxygen(酸素)低酸素症(呼吸不全による低酸素血症、循環不全など)Opiate(オピオイド)高二酸化炭素血症(CO2ナルコーシス)Overdose(過剰投与)麻薬や鎮静薬をはじめとする薬物過剰投与 Trauma(外傷)硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血Temperature(体温)熱中症、偶発性低体温、悪性症候群Tumor(腫瘍)脳腫瘍Infection(感染)敗血症、中枢神経系感染症(髄膜炎、脳炎、脳膿瘍など) Psychogenic(精神疾患)うつ病、統合失調症、ヒステリー、過換気症候群 Stroke(脳卒中)脳梗塞、脳出血、くも膜下出血Shock(ショック)循環血液量減少、血液分布異常、心原性、心外閉塞・拘束性ショックSeizure(けいれん発作)てんかん 表3 意識障害患者の観察すべき症状 眼球共同偏視→S:脳卒中、S:けいれん発作瞳孔収縮→S:橋出血、O:麻薬中毒瞳孔散大→脳ヘルニア、低酸素脳症瞳孔不同→S・T:脳卒中や外傷による脳ヘルニア 呼吸過呼吸・失調性呼吸→S:脳幹出血チェーンストークス呼吸→S・T:大脳半球病変、S:心不全クスマウル呼吸→I:高血糖(糖尿病性昏睡)呼吸数増加→O:低酸素症、I:敗血症、S:ショック呼吸数減少→O:麻薬や鎮静薬の過剰投与 呼気臭アルコール臭→A:急性アルコール中毒アセトン臭→I:高血糖(糖尿病性昏睡)アンモニア臭→U:尿毒症 言語機能失語→S:脳卒中 頸部硬直→I:髄膜炎、S:くも膜下出血頸静脈怒張→S:心不全・肺塞栓 心拍数(脈拍)頻脈→I:感染症、O:低酸素症、S:出血などショック徐脈→E:不整脈(アダムス・ストークス症候群) 血圧高血圧→S:脳卒中、T:外傷性頭蓋内損傷低血圧→S:ショック 皮膚所見蒼白・湿潤→S:ショック、O:低酸素症黄疸→E:肝性脳症チアノーゼ→O:低酸素血症冷汗→I:低血糖 四肢の動き片麻痺→S:脳伷塞、脳出血はばたき振戦→E:肝性脳症けいれん→S:てんかん・脳卒中、T:頭部外傷・脳腫瘍 体温体温上昇→I:感染症、S:脳卒中、E:内分泌疾患、T:熱中症・悪性症候群体温低下→T:偶発性低体温 (第2回) 参考文献1.水野樹:意識障害.医学の基礎を学びなおす 症状をどうアセスメントする!?,月刊ナーシング 2009;29(1):78-85.2.山口充,堤晴彦:意識障害.綜合臨牀 2004;53(11):2860-2865.3.西塔依久美:意識障害.救急看護のエキスパートが教える主要症状別「ファーストエイド」実践マニュアル,臨牀看護 2011;37(4臨時増刊):428-435.4.松尾貴公:特に注意したい症状 意識障害:医師が来るまでにできること.木村哲也編,ベッドサイドでナースができる! 脳・神経の異常“とっさの”見かたと対応,エキスパートナース 2015;31(3):28-30. この記事を読んだ方におすすめ●脳卒中を急変未満で見抜くポイント●大脳皮質の出血を画像で見るポイント●そのほかの連載はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2016年5月臨時増刊号を再構成したものです。本記事の無断転載を禁じます。
- 会員限定
- 特集記事
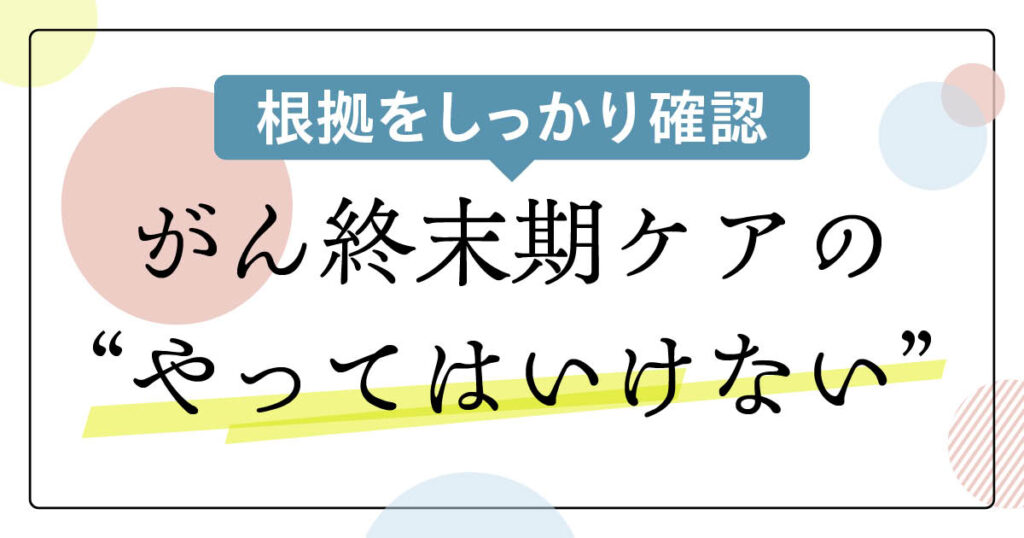
終末期せん妄への対応:身体的拘束の弊害と非拘束ケアの実践法
がん終末期に起こるせん妄に対しては、機能低下などの弊害が伴います。終末期における拘束のリスクと、環境調整や薬物療法など、身体的拘束に変わる具体的な支援方法を解説します。 「がん終末期ケアの“やってはいけない”」の連載まとめはこちら がん終末期ケアのNG是非を考えずに身体的拘束を行ってはいけない〈理由〉科学的根拠はない。かえって転倒事故が重大になったり、ご家族の自責感を増大する恐れがあるから 身体的拘束が効果的であるという科学的根拠はありません。 にもかかわらず、ADLが低下し予後が短い月単位と言われた患者さんに、身体的拘束が必要になってしまうのはどんなときでしょうか。 身体的拘束の弊害とは? 終末期がん患者さんにおいて、せん妄は85~90%に生じ、そのうち30~50%が回復する一方で、50~70%は回復しないまま死亡に至るといわれています。そして、終末期せん妄を体験したご家族の70%がつらい体験と感じています1。 せん妄状態は見ているご家族にも多大なストレスがかかる一方、患者さん自身にとっては、過活動によるベッドからの転落や転倒による骨折などのリスクがあります。そのため、医療現場においてはやむを得ず抑制(身体的拘束)が検討される場合があります。 しかし、身体的拘束には表1のような弊害があり、2024年度診療報酬改定では身体的拘束最小化の取り組みが強化されました。また、介護施設においてはすでに1999年に厚生労働省令で基準が示されてから行われなくなってきており、2024年には厚生労働省が『介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き』を発行しています2。 まずは、身体的拘束が患者さんに与える影響についてスタッフ全員がカンファレンスなどで話し合い是非を検討していくことが大切です。 表1 身体的拘束の弊害 ●転倒事故の重大化力を振り絞って動こうとするあまり、かえって転倒事故が重大化する●機能低下身体的拘束により、残された機能の低下を招く可能性がある●尊厳の低下精神的に傷つき、尊厳の低下を招く恐れがある 終末期せん妄への対応は? せん妄の原因はさまざまです。まずは、せん妄の原因を評価し、回復可能かどうかを医学的に判断することが重要です。 回復可能なせん妄と診断された場合は、原因の除去、環境調整、ご家族のサポート、薬物療法などを検討します(具体的な対応は後述)。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 回復困難な終末期せん妄とは、がんの肺転移による肺機能悪化に伴う低酸素によって起こるものなどがその一例です。終末期せん妄であると判断された場合には、今後の病状変化を予測したうえで、ご家族の気持ちに十分配慮した対応が求められます。 終末期せん妄が認められたがん患者さんのご家族を対象とした調査の中では、ご家族が患者さんのつじつまの合わない言動を見て「モルヒネのせいで頭がおかしくなったのではないか」と認識したり、「以前と違う姿を見るのがつらい」、「自分たちが、精神的に追い詰めてしまったのではないか」と自責感を抱いたりしていることがわかっています3。 そして、そのなかでご家族は医療者に対して、患者さんがおかしなことを言っても否定や修正をせず付き合い、不穏行動があっても抑制しないで対応してほしいと望んでいました3。 以上のようなことからも、基本的には身体的拘束は行うべきではないでしょう。 終末期せん妄への具体的な支援 身体的拘束に代わる、具体的な支援を以下に示します。 1)患者を尊重し、 苦痛を緩和し安全を確保する 患者さんの主観的な世界を大切にした対応を行います。患者さんの話を否定しないことが大切です。「これまでと変わらないその人」として尊重する対応により、社会的側面にも配慮します。 加えて、身体的苦痛の緩和に努め、安全確保のための環境整備を行います。点滴の固定のしかたを工夫したり、夜間は点滴を中止するなど、ルート類の整理も重要です。 2)家族に対して十分に説明し、 支援する ご家族には、終末期せん妄について理解できるよう十分な説明が必要です。「原因」「病態」「今後の経過」「治療方法」「対応のしかた」「せん妄は一般的によく生じる症状であること」について、患者さんの状態の変化に伴って随時説明します。 また、ご家族の身体的な介護負担の軽減と精神的支援を行います。ご家族へのねぎらいの言葉を忘れずに、申し訳なさを和らげる対応を行いましょう。 3)医療者間で連携し、 患者の変化に迅速な対応をする チームカンファレンスを通して患者さんへ対応しましょう。回復可能なせん妄では、見当識を修正するなど、環境調整がケアになる場合もあります(表2)。また、睡眠覚醒のリズム調整を目的とした薬物療法も検討されます(表3)。 表2 環境調整によるせん妄のケア ●頻回に見当識を与え、患者や家族を言葉で安心させる●認識が誤っている場合は是正する●昼夜の光彩に配慮する。昼間は通常より明るく、夜間はフットランプなどのみとし、頻回な訪室や過剰な知覚刺激は避ける●患者にとって親しみのあるもの(家族写真など)を置く●カレンダーや時計を置き、時間を意識させる●親しい人(可能ならば、家族や友人)との頻回な接触をはかる●可能な範囲で活動を促す 表3 睡眠覚醒リズムの調整を目的とした薬物療法 回復可能なせん妄の場合の処方例(1)グラマリール 3T×3(2)ハロペリドール 1.5mg、1T(夕) +トリアゾラム 0.125mg1T(眠前) 終末期せん妄の場合の処方例生理食塩水(20mL)1A、ハロペリドール 1A(夕方に静注) +生理食塩水(100mL)1A、ミタゾラム 1A(眠前に点滴) *あくまでも、メジャートランキライザー(抗精神病薬)による治療が中心。ベンゾジアゼピン系睡眠薬だけでは意識レベルを下げ、せん妄が悪化することがよく見られる 終末期において、せん妄は頻度の高い症状として出現することを忘れずに、まずは私たち医療者が、終末期せん妄であるのか否かをきちんと評価できることが大切です。 そして、患者さんに対する尊厳が守られた対応のなかで、見守るご家族の気持ちに配慮していくことが、患者さんとご家族との別離のプロセスにおいて有効なケアであると思います。 まとめ●身体的拘束は基本的には行わない。他の方法で安全確保や症状改善を目指し、患者の尊厳に配慮する●終末期においてせん妄は頻度の高い症状であることを理解し、家族の自責感を和らげる対応を行う (最終回) 引用文献1.森田達也,他:エビデンスで解決! 緩和医療ケースファイル.南江堂,東京,2014:163-167.2.厚生労働省:介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き.2024.3.Nanba M, et al.:Terminal delirium:families’ experience.Palliat Med 2007;21(7):587-594. この記事を読んだ方におすすめ●一般病棟でのせん妄対策はどうする?●「身体的拘束」最小化の動き●そのほかの連載はこちら ※この記事は『エキスパートナース』2015年6月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
- 会員限定
- 特集記事