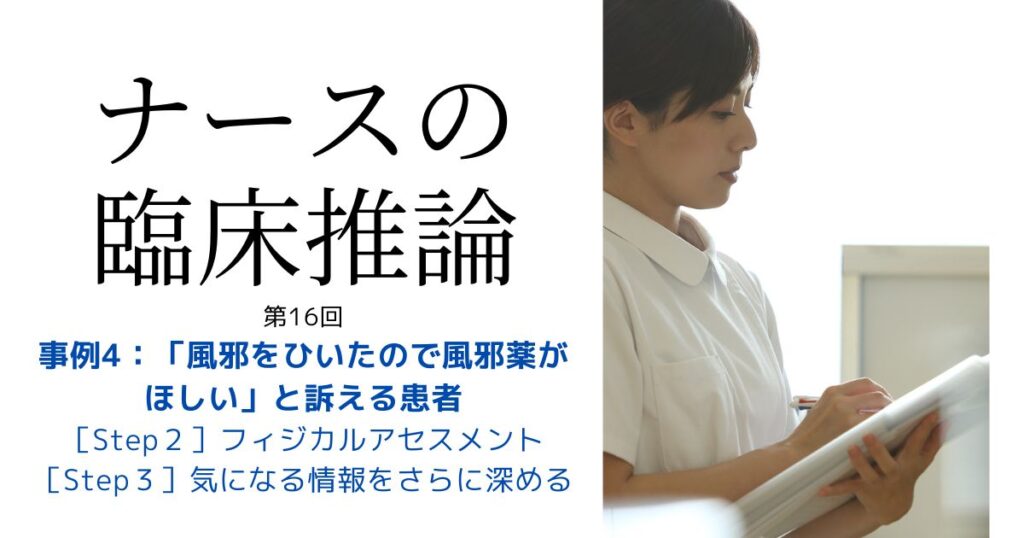患者さんの訴えの裏に隠された疾患を見逃さないために大切な「臨床推論」。どのような思考過程を経て臨床診断を導き出しているのかを考えていきます。今回は第15回で紹介した「鼻水、咳、体のだるさ」を主訴に受診した患者さんの事例の、フィジカルアセスメントとさらなる情報収集について解説します。
第2ステップ フィジカルアセスメント
Dさんのフィジカルアセスメント(身体所見)
●意識状態:JCSⅠ-1
●バイタルサイン:血圧100/70mmHg、脈拍96回/分、整、呼吸数30回/分、体温36.8℃、SaO2 98%
●眼瞼結膜に貧血なし、眼球結膜黄染なし。口腔内軽度乾燥。咽頭所見正常
●Jolt accentuation陰性
●瞳孔3mm/3mm、対光反射正常
●甲状腺に圧痛なし、腫大なし
●頸静脈怒張なし
●胸腹部:視診、触診、聴診、打診で特に異常認めず
●心音整、心雑音なし。心音でⅢ音聴取せず
●皮膚、四肢:皮疹なし。末梢冷感なし。浮腫は認めず
●脳神経の異常所見なし
●口臭異常(甘酸っぱい臭い=ケトン臭)あり
呼吸数に着目し、原因を鑑別する
まず気になるのが、呼吸数が多い(頻呼吸)ことです(正常範囲は12~16回/分)。20回/分以上であれば呼吸数は多いと判断します。
呼吸数が多いことで考えられるのは、酸素が足りない、代謝上呼吸を速くしないとバランスを保てない、呼吸中枢の問題、心理的ストレスのいずれかと考えられます。鑑別診断としては、以下を考えます。
頻呼吸の病態と鑑別診断
低酸素⇒肺炎、COPD急性増悪、心不全、肺塞栓症 など
気道閉塞⇒異物、急性喉頭蓋炎 など
代謝性アシドーシスの代償⇒糖尿病性ケトアシドーシス、アルコール性ケトアシドーシス、乳酸アシドーシス、腎不全、NSAIDs、トルエンなどの薬物中毒、発熱(敗血症等) など
中枢性⇒脳炎、脳血管障害 など
心理的ストレス⇒恐怖、不安障害(パニック発作等) など
*低酸素、気道閉塞、中枢障害はないので、この症例では赤字のどちらか
本症例ではSaO2は98%であり、低酸素は否定的です(一酸化炭素中毒、メトヘモグロビン血症など例外もあるので要注意)。軽度の咽頭痛がありますが、気道閉塞症状はありません。
病歴から、中枢性は否定的です。残るは、代謝性アシドーシスの代償によるものか、隠れた心理的ストレスによる頻呼吸です。
この記事は会員限定記事です。