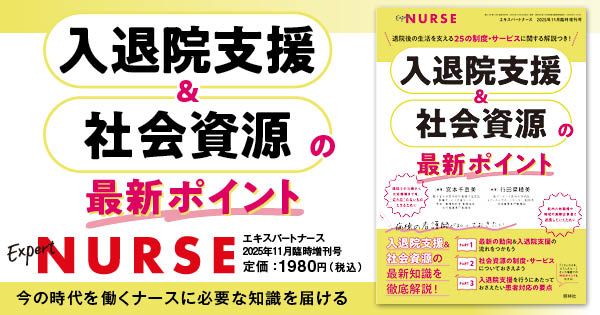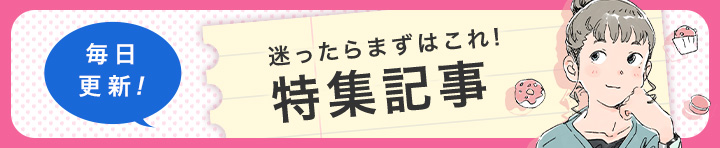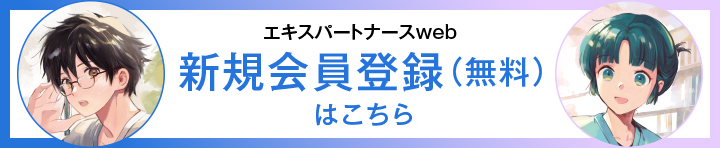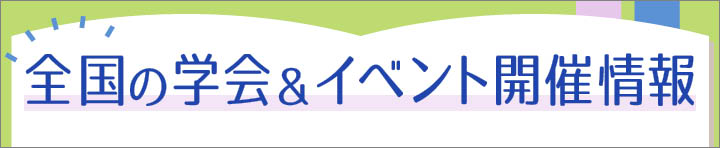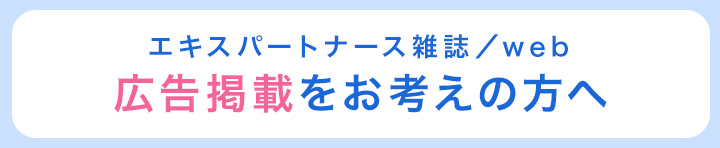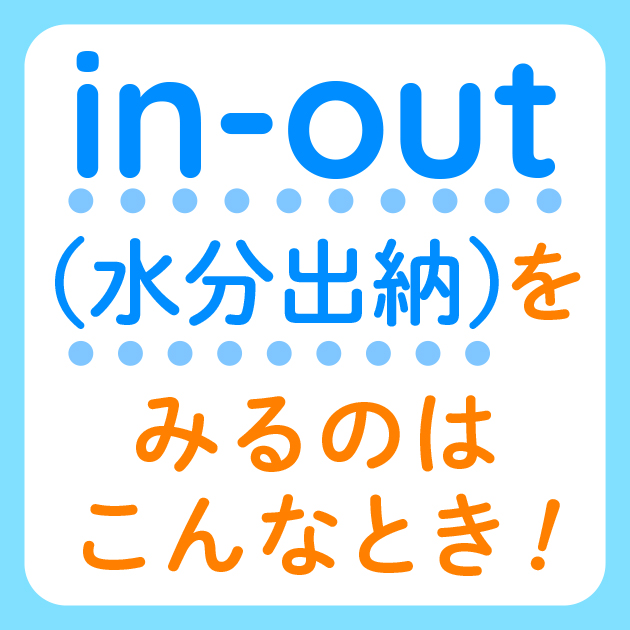-
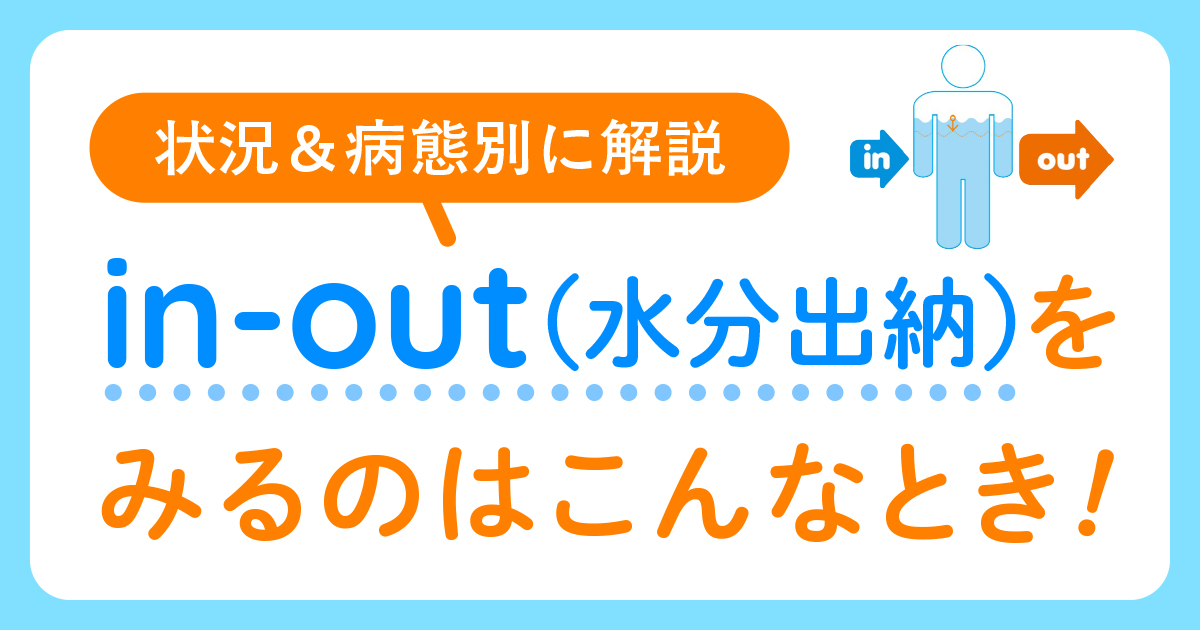
脱水を判断するには?感度・特異度に注目【in-out】
- 会員限定
- 特集記事
-
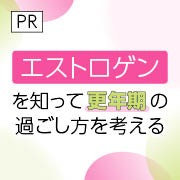
「エストロゲン」を知って更年期の過ごし方を考える
- PR
- タイアップ記事
-

川嶋みどり 看護の羅針盤 第366回
読み物 -

【2025年】エキナスweb人気記事ランキングTOP10
特集記事 -

【新規会員登録(無料)キャンペーン】PDFを1冊まるごとプレゼント!
- 会員限定
- お知らせ
-

川嶋みどり 看護の羅針盤 第365回
読み物 -
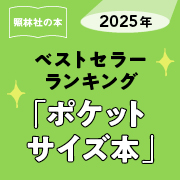
【2025年】看護師向けポケットサイズ書籍ランキングTOP5
BOOKレビュー -

川嶋みどり 看護の羅針盤 第364回
読み物 -
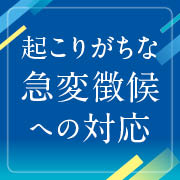
がん化学療法に伴う急変:腫瘍崩壊症候群・敗血症・間質性肺炎を見抜くには?
- 会員限定
- 特集記事
-
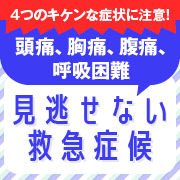
【連載まとめ】見逃せない救急症候―頭痛、胸痛、腹痛、呼吸困難に注意!
特集記事
特集記事
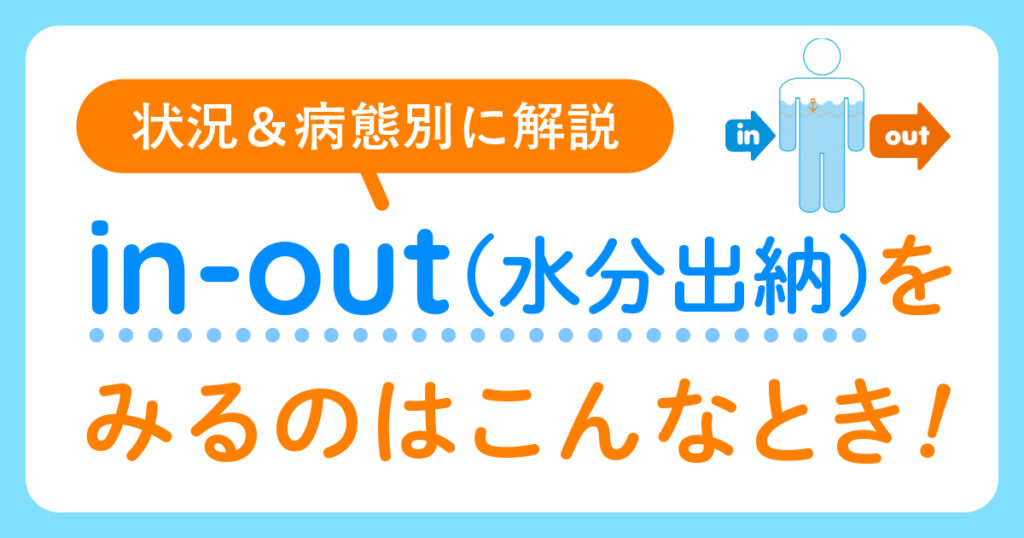
脱水を判断するには?感度・特異度に注目【in-out】
単独の観察だけでは判断できないケースが多い脱水。参考になるのが、感度と特異度です。感度と特異度に注目しながら、複数の観察を行うことが大切。ポイントをお伝えします。 「in-out(水分出納)をみるのはこんなとき!」の連載まとめはこちら 本連載の中でも脱水や溢水にかかわる多くの観察ポイントが示されていますが、単独の観察ではその病態(今回の場合では脱水・溢水)を言い切れないケースが少なくありません。 このとき、「感度」「特異度」などの統計学を参考にする場合があります。 感度●特定の疾患や状態にある集団のなかで検査陽性と判定される割合のこと●陰性の場合には疾患を除外するのに役立つ 特異度●特定の疾患や状態をもたない集団の中で、検査陰性と判定される割合のこと●陽性の場合には疾患を診断するのに役立つ *感度が高い観察または検査で“陰性”となれば、その疾患に罹患している確率は「低い」*特異度が高い観察または検査で“陽性”となれば、その疾患に罹患している確率が「高い」 表1 体液量減少に対する身体徴候の診断正確性 脈拍増加(>30回/分)感度:43% 特異度:75%起立性低血圧(sBp低下20mmHg)感度:29% 特異度:81%腋窩の乾燥感度:50% 特異度:82%口腔内の乾燥感度:85%*1 特異度:58%舌の乾燥感度59% 特異度:58%舌の縦溝感度:85% 特異度58%眼球陥没感度:62% 特異度:82%意識混沌感度:57% 特異度:73%CRT(capillary refilling time)感度:34% 特異度:95%*2 (文献1より引用) 【*1】感度で比較的「高い」のは“口腔内の乾燥”。つまり、乾燥の所見が「ない」場合は脱水の可能性は低くなる。しかし、口腔内の乾燥の特異度は58%と「低い」。つまり、脱水であっても約半数は、この所見はないと統計学上出ているということ。要するに、口腔内の乾燥だけの所見をとっても脱水ではないとは言い切れない。 【*2】特異度の高い検査は“CRT”。特異度95%であり、CRT“陽性”所見があれば、かなりの確率で脱水の診断を高める。しかし、CRTの感度は「低い」。その所見がないからといって脱水ではないとは言い切れない このブロック以降のコンテンツは非表示になります 表3 心不全(溢水)に対する身体徴候の診断正確性 起坐呼吸感度:50% 特異度:77%下肢浮腫感度:50% 特異度:78%体重増加感度:31% 特異度:70%頸動脈怒張感度:39% 特異度:92%crackles感度:60% 特異度:78% (文献1より引用) 理想的には「感度」「特異度」ともに高ければ診断しやすいのですが(感度・特異度ともに90%以上で診断に役立つと言われている)、そのような都合のよい観察・検査はあまりありません。よって、いろいろな観察や検査を組み合わせ総合的に判断することが求められます。このほかにも医学統計には「尤度比(ゆうどひ)」や「odds(オッズ)比」など、統計を理解すれば観察に参考になるデータが多く存在します。 少なくとも何かの病態を疑ったときには、“1つの観察では判断できないことのほうが多い”という認識のもと、複数の観察を行い、総合的にアセスメントするよう心がけましょう。 (第15回) 引用文献1.Simel DL, RennieD 編,竹本毅一 訳:JAMA版論理的診察の技術.日経BP,東京,2010:199-217,319-331. 参考文献1.Bickley LS,福井次矢 訳:ベイツ診察法(第3版).メディカルサイエンスインターナショナル,東京,2022:75-79. この記事を読んだ方におすすめ●「in-outをみるのはこんなとき!」の記事一覧●そのほかの連載記事 ※この記事は『エキスパートナース』2016年10月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
- 会員限定
- 特集記事
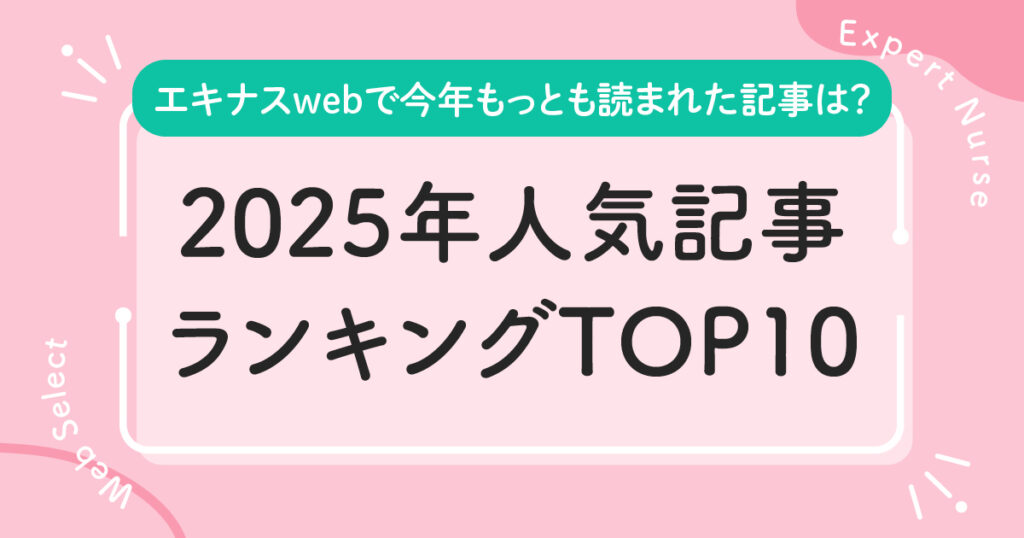
【2025年】エキナスweb人気記事ランキングTOP10
2025年も残りわずか。今年、『エキスパートナースweb』で人気だった記事TOP10をご紹介します。振り返りに役立ててみてください。各記事の末尾には関連記事が載っているので、そちらもぜひチェックを! 10位:発作性上室頻拍(PSVT)の心電図波形の特徴は? 発作性上室頻拍の心電図波形の特徴とは?注目したいポイントを整理しています。さらに、モニター上での動脈圧の見方や、発作性上室頻拍が現れたときの対応方法も学べます。〈目次〉●発作性上室頻拍の特徴とは?●PSVTが出現したらどうする? 記事はこちらから 9位:終末期のバイタルサイン変化:亡くなる前のサインとは? 終末期のバイタルサインはどのように変化していくのでしょうか。心停止前、がん終末期など、状況別に亡くなる前に見られるサインを取り上げています。患者さんと家族への適切なケアと心の準備のために重要です。〈目次〉●終末期のバイタルサインの変化とは?・心停止前のバイタルサインの変化・がん終末期のバイタルサインの変化・がん終末期以外の死亡につながるバイタルサインの変化 記事はこちらから 8位:メインと側管からの点滴は、同時投与でもいいの? 看護師にとって必要不可欠な薬の知識に関するギモンを取り上げました。点滴の際、側管が多ければメインが止まる時間が長くなります。では、メインと側管からの点滴は同時に落としてもよい?薬剤師が説明します。〈目次〉●メインと側管からの点滴は、同時に落としていいの?片方ずつがいいの?・ルートがない場合は、同時投与せざるを得ない場合も 記事はこちらから 7位:交差適合試験(クロスマッチ)と血液型検査、同時に採血しない理由は? 輸血の前、輸血検査として行われる血液型検査と交差適合試験(クロスマッチ)。それぞれの検体を別々に採血しなければならない理由とは?医療安全の観点から詳しく解説しています。〈目次〉●輸血検査の流れとは?●血液型検査と交差適合試験を同時採血してはいけない理由は?・ABO型不適合輸血実態調査 記事はこちらから 6位:アドバンス・ケア・プランニングの定義と支援のポイント 国内外のACPの定義を確認したうえで、話し合うべき内容や支援のポイントを紹介。患者さんによるACPのプロセスや、ACPを支援するメリット、看護師に期待される役割など、知っておきたいポイントが満載です。〈目次〉●ACPの定義●ACPで医療者と患者さんが話し合う内容●ACPのメリットと課題●ACPにおいて看護師に期待される役割 記事はこちらから 5位:胸腔ドレーンのフルクテーション(呼吸性移動)の確認方法 胸腔ドレーン管理において重要な呼吸性移動の確認方法をわかりやすく紹介します。呼吸性移動が観察できない場合の原因や、ドレーン閉塞を疑う場合のチェックポイントについても整理。適切な対応をとるための実践的な知識を習得できます。〈目次〉●呼吸性移動は「正常に交通している」ことを示す●水封室での呼吸性移動(フルクテーション)の確認方法は?●呼吸性移動が観察できない場合は注意●ドレーン閉塞を疑った場合のチェックポイント 記事はこちらから 4位:房室接合部調律の心電図波形の特徴とは? 房室接合部調律の心電図波形の読み方について、ここだけは覚えておきたい要点をピックアップ。図とともにコンパクトに解説しています。特徴の1つである「P波が出ていない」とはどんな状態なのか、注意点を含めて確認しましょう。〈目次〉●房室接合部調律の特徴とは?●「P波が出ていない」とはどんな状態? 記事はこちらから 3位:看護記録の監査や教育 いよいよTOP3です! 3位は「看護記録の監査や教育」。医療機関の品質管理と患者ケアの向上に不可欠な看護記録の監査。監査の目的やプロセス、種類などを整理しています。さらに、看護記録の教育についても紹介。その重要性や、ラダー別教育について知ることができます。〈目次〉●看護記録の監査とは?●監査の項目はどう選定する?●看護記録教育とは 記事はこちらから 2位:心室期外収縮(PVC/VPC)の心電図波形の特徴は? 「ここだけ覚えて心電図」の連載から、3つ目のランクイン。 心室期外収縮(PVC/VPC)の心電図波形の特徴をわかりやすく紹介しています。Lown分類による重症度判断もおさえておきましょう。急性心筋梗塞(AMI)、心不全、心筋症において、心室期外収縮とともに見るべき検査データもチェックを。〈目次〉●心室期外収縮の心電図波形の特徴は?●Lown分類で重症度を判断 記事はこちらから 1位:倫理カンファレンスの進め方 1位はこちら、「倫理カンファレンスの進め方」でした! さまざまな臨床場面で必要になる、看護倫理の知識。記事では、特に倫理カンファレンスの進め方を解説しています。倫理カンファレンスの目的や、倫理カンファレンスにおける看護師の役割とは?具体例を交えながら、効果的な倫理カンファレンスを行うポイントを実践的に学べます。〈目次〉●倫理カンファレンスの目的●臨床でよくみる具体的な場面の例●倫理カンファレンスの「グランドルール」を共有する●主体的に発言できるカンファレンス 記事はこちらから この記事を読んだ方におすすめ●「ここだけ覚えて心電図」の記事一覧●医療・看護の知っておきたいトピック●症例写真でわかる!褥瘡・創傷ケア●連載記事一覧
特集記事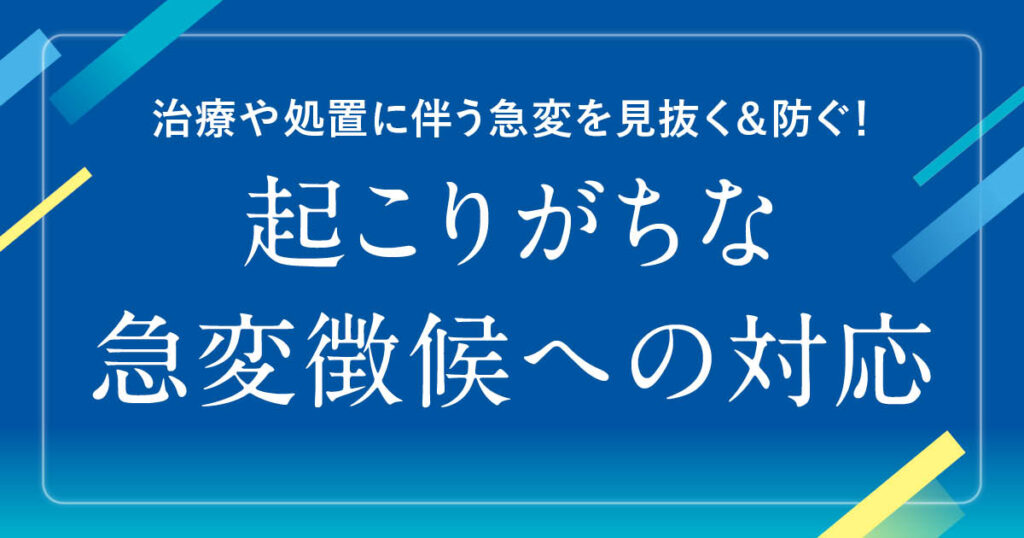
がん化学療法に伴う急変:腫瘍崩壊症候群・敗血症・間質性肺炎を見抜くには?
がん化学療法に伴う急変(オンコロジック・エマージェンシー)を解説。腫瘍崩壊症候群・敗血症・間質性肺炎の原因や早期発見のサイン、看護師が押さえておきたい対応・予防のポイントをまとめています。 〈目次〉●腫瘍崩壊症候群の原因●腫瘍崩壊症候群の早期発見・対処のポイント●腫瘍崩壊症候群の予防・予測のポイント●敗血症の原因●敗血症の早期発見・対処のポイント●敗血症の予防・予測のポイント●間質性肺炎の原因●間質性肺炎の早期発見・対処のポイント●間質性肺炎の予防・予測のポイント がんの局所浸潤や全身転移などの病状の進展と化学療法や放射線治療など治療に伴う急性反応で、時間・日の単位で急速に進行し、早急に対応しなければならない状態をオンコロジック・エマージェンシーと言います。 この章では化学療法に伴うもののなかで、「①腫瘍崩壊症候群」「②敗血症」「③間質性肺炎」について述べます。 起こりがちな急変徴候●電解質異常(尿酸、カリウム、リン、カルシウム)●尿量減少●徐脈、頻脈●テタニー(筋肉の痙攣、脱力感、しびれ)⇒急速な電解質異常で生命を脅かす腫瘍崩壊症候群を疑おう! 腫瘍崩壊症候群の原因とは? 腫瘍崩壊症候群とは、治療による腫瘍崩壊に伴って細胞内物質が大量に血中へ放出されることによって起きる、高尿酸血症、高カリウム血症、高リン血症、低カルシウム血症などの、生命を脅かす可能性がある電解質異常です(図1)。 図1 腫瘍崩壊症候群のイメージと影響 腫瘍崩壊症候群は、特に“急速に増殖し”“腫瘍量が多く”“化学療法に感受性が高い”腫瘍の治療に伴って起こりやくなります。また、化学療法の開始後12~72時間以内に発症することが多いです。発症リスクの高い疾患を表11に示します。 表1 腫瘍崩壊症候群の発症リスクの高い疾患 血液腫瘍・急性白血病(特にリンパ性)・Burkittリンパ腫*2 など 固形腫瘍・胚細胞腫瘍・小細胞肺がん など その他・LDH高値・循環血液量の減少・腎障害の存在 など (文献1より引用)*2【Burkittリンパ腫】=バーキットリンパ腫、悪性リンパ腫の一種。 腫瘍崩壊症候群の早期発見・対処のポイントは? ①観察 リスクの高い疾患(表1)の治療開始後72時間程度は、以下を重点的にチェックしながら早期発見に努めます。 ●体重●in-outバランス●バイタルサイン●検査値:血清電解質や腎機能、尿酸値など(表2)2●心電図波形:不整脈(徐脈、心室頻拍、心室細動、T波の先鋭化、QT間隔の短縮、QRS幅の増大など)●関連症状:悪心・嘔吐、脱力感、しびれ、筋肉の痙攣、徐脈、頻脈、尿量減少、浮腫など 表2 腫瘍崩壊症候群の検査データ(診断項目) 尿酸検査値:≧476μmol/L(8mg/dL)ベースラインからの変化:25%以上の上昇K検査値:≧6.0mmol/L or 6mEq/Lベースラインからの変化:25%以上の上昇P検査値:≧1.45mmol/Lベースラインからの変化:25%以上の上昇Ca検査値:≦7mg/dL(1.75mmol/L)ベースラインからの変化:25%以上の低下 (文献2より引用) ②症状への注意 患者や家族に、上記の腫瘍崩壊症候群に関連した症状を説明し、症状出現時にはすみやかに報告するよう指導します。 ③治療 治療は、電解質異常の補正を行いながら、血圧や尿量の維持を図ります。 腎不全、著しい高カリウム血症・高尿酸血症・乏尿などで、通常の治療では対処不能の場合は血液透析を行います。 腫瘍崩壊症候群の予防・予測のポイントは? 治療開始前にも、腫瘍崩壊症候群を起こしやすい疾患(表1)かどうかを評価して、起こすリスクについてアセスメントします。 また、腫瘍崩壊症候群が発症した場合は急速に悪化する可能性があるため、次の方法から発症を予防することが最も重要です(図2)1。 図2 腫瘍崩壊症候群に対する予防(治療)薬剤 (文献1を参考に作成) ①尿量の確保 十分な輸液(K・P・Caフリーの輸液)を行い、尿量は80~100mL/m2/時を維持します。必要に応じて利尿薬を用います。 ②高尿酸血症を防ぐ薬剤の投与 高尿酸血症による急性腎不全を予防するため、尿酸を低下させる以下の薬剤を使用します。なお、疾患やその悪性度やステージ、LDH値などによって発症のリスクを判断し、高リスクと考えられるときや、すでに高尿酸血症を発症している場合にはラスブリカーゼを使用します。 「低リスク」と考えられる場合は、アロプリノール(ザイロリック®)の内服投与を行います。尿酸の産生を減少させる薬剤ですが、効果が現れるまで数日かかります。 「高リスク」と考えられる場合は、ラスブリカーゼ(ラスリテック®)の静注投与を行います。尿酸を直接分解する尿酸酸化酵素であり、すでに存在する高尿酸血症に対しても効果があります。ラスブリカーゼはアロプリノールより効果発現が早く、投与4時間程度で効果が現れます。過去の投与によって中和抗体が産生された報告や、再投与にて重篤なアレルギー症状が発現したという報告があり、過去にラスブリカーゼを投与された患者への再投与は慎重投与となっています。 起こりがちな急変徴候●好中球数減少●感染頻度が高い身体部位の感染徴候●発熱⇒DIC、ARDS、MODSにつながりやすい敗血症を疑おう! 敗血症の原因とは? 敗血症は感染による全身性の炎症性反応で、化学療法後の好中球減少時期に起こりやすいです。敗血症が進行しているときは、低体温になることもあります。 毒素(エンドトキシン)によって血圧低下と末梢循環不全が起き、敗血症性ショックにつながり、播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation、DIC)、急性呼吸窮迫症候群(acute respiratory distress syndrome、ARDS)、多臓器不全症候群(multiple organ dysfunction syndrome、MODS)に進行する恐れがあり、死に至る危険性が高くなります。敗血症のリスクファクターを表3に示します。 表3 敗血症のリスクファクター ●好中球減少症とその持続*好中球数が落ちる、化学療法開始後7~14日目は特に注意!●免疫抑制状態●糖尿病・腎臓、肝臓、心血管系、肺疾患の合併症●65歳以上の高齢者●中心静脈カテーテルなど留置中●皮膚と粘膜の統合性障害 敗血症の早期発見・対処のポイントは? ①観察と症状への注意 好中球数はがん化学療法開始から7~14日目に最低値に至ることが多いため、患者や家族にその時期に感染しやすいことを説明し、症状(表4)出現時には必ず連絡するよう指導します。 また、好中球減少時には感染頻度が高い部位(口腔内、咽頭、副鼻腔、肺、腟・肛門周囲、皮膚、尿路、カテーテル刺入部)の症状や身体所見を注意深く観察することが重要です。 このブロック以降のコンテンツは非表示になります 感染が疑われる場合は、2セット以上の血液培養、また血液検査、尿培養検査、喀痰培養検査、胸部X線撮影などを行います。 表4 敗血症を疑いたい症状 感染症状・発熱 ・感冒様症状・下痢 ・化膿 敗血症初期症状・発熱 ・悪寒・倦怠感 ・頻脈 ②発熱性好中球減少(FN)に注意 発熱性好中球減少症(febrile neutro-penia、FN)にも注意が必要です。これは好中球数が500/mm3未満、または1,000/mm3未満で48時間以内に500/mm3未満に減少すると予想される状態で、腋窩温37.5℃以上、または口腔温38.0℃以上となった場合のことを言います3。 発熱性好中球減少症となった場合はリスク分類を行い、リスクに合わせた抗菌薬を選択し、敗血症への移行を防ぎます(表5)4。このリスク分類は代表的なものですが、他の分類法もあります。 表5 発熱性好中球減少症のリスク評価と対応 発熱性好中球減少症のリスク評価に関するMASCCスコア臨床症状 無症状もしくは軽症:5点 中等症:3点 重症:0点血圧低下がない(収縮期血圧>90mmHg):5点慢性閉塞性肺疾患(COPD)がない:4点原疾患:固形がん、または造血器腫瘍で真菌感染症の既往がない:4点脱水症状がない:3点外来管理中に発熱:3点60歳未満:2点点数の合計(最大26) Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis 2011;52(4):e63.より引用 合計21点以上(低リスク)●シプロフロキサシン:200mg4錠、分2、経口●アモキシシリン・クラブラン酸:250mg6~8錠、分 3~4、経口合計20点以下(高リスク)●セフェピム:1g、8 時間ごと、もしくは 2g を12時間ごと、静注●イミペネム:0.5g、6時間ごと、静注●メロペネム:1g、8時間ごと、静注●タゾバクタム・ピペラシリン:4.5g 、6時間ごと、静注 (文献4より引用、一部改変) ③敗血症への対応 発症した場合は原因菌を特定して薬剤感受性を調べ、適切な抗菌薬の投与を行います。 可能であれば、原因の元となる部分の外科的処置やカテーテル・チューブ類を抜去します。 敗血症の予防・予測のポイントは? 化学療法開始前に、 十分な好中球数が保てているかを確認します。薬剤によっては好中球減少が用量制限毒性(dose-limiting toxicity、DLT)*3となっていることもあります。 また、以下の感染予防に努めるよう指導します。なお、医療従事者は標準的感染予防を確実に行います。①手洗い、うがいの励行②外出時はマスクを着用する③毎食後と眠前に歯磨きなどの口腔ケアを行う④可能な限り毎日シャワー浴か入浴を行う⑤排便コントロールを行い、硬便による肛門の裂傷を予防する⑥身近に風邪などの感染症罹患者がいる場合は、できるだけ接触を避けるよう説明する 起こりがちな急変徴候●空咳(痰を伴わない咳)●息切れ・呼吸困難●発熱⇒重篤化・死亡につながりやすい間質性肺炎を疑おう! 間質性肺炎の原因とは? 間質性肺炎(interstitial pneumonia、IP)とは、肺間質すなわち肺胞隔壁を主とした炎症です。間質性肺炎はさまざまな薬剤で発症の可能性がありますが、化学療法はその代表的なものです。化学療法による間質性肺炎は重篤例や死亡例が報告されているため、早期発見・早期治療が重要です。 間質性肺炎の発症の可能性の高い抗がん剤を表55に示します。 表5 間質性肺炎の発症頻度の高い抗がん剤(薬剤種類別) 抗悪性腫瘍薬・イリノテカン(トポテシン®)〈頻度〉0.9%・ビンデシン(フィルデシン®)〈頻度〉0.1~5%未満・ビノレルビン(ロゼウス®)〈頻度〉1.4%・エリブリン(ハラヴェン®)〈頻度〉1.2%・イホスファミド(イホマイド®)〈頻度〉0.1~5%未満・メルファラン(アルケラン®)〈頻度〉1.9%・ベンダムスチン(トレアキシン®)〈頻度〉1.3%・ゲムシタビン(ジェムザール®)〈頻度〉1.0%・アムルビシン(カルセド®)〈頻度〉0.1~5%未満・ペメトレキセド(アリムタ®)〈頻度〉3.6% 分子標的薬・セツキシマブ(アービタックス®)〈頻度〉0.5~10%・パニツムマブ(ベクティビックス®)〈頻度〉1.3%・ゲフィチニブ(イレッサ®)〈頻度〉1~10%未満・エルロチニブ(タルセバ®)〈頻度〉4.4%※・クリゾチニブ(ザーコリ®)〈頻度〉1.6%・イマチニブ(グリベック®)〈頻度〉5%未満・ダサチニブ(スプリセル®)〈頻度〉0.9%※・ボルテゾミブ(ベルケイド®)〈頻度〉3.2%・サリドマイド(サレド®)〈頻度〉5%未満・スニチニブ(スーテント®)〈頻度〉2.2%・エベロリムス(アフィニトール®)〈頻度〉12.4%※・テムシロリムス(トーリセル®)〈頻度〉17.1%※ ※間質性肺疾患(間質性肺炎・肺臓炎・肺浸潤・胞隔炎・肺線維症等)としての頻度(文献5より引用、一部改変) 間質性肺炎の早期発見・対処のポイント ①観察と症状への注意 患者や家族に間質性肺炎の主な症状である空咳(痰を伴わない咳)、息切れ・呼吸困難、発熱について説明し、症状出現時には必ず連絡するよう指導します。また、いつでも発症する可能性があること、急性に重篤化する可能性があることを説明します。 ②身体徴候と血液データ、画像データのチェック 治療開始前には必ず主な症状の有無の確認とSpO2測定、呼吸音聴診などを行い、変化に注意します。 また、定期的な採血に(CRP、KL-6・SP-D、LDHなど)、胸部X線、胸部CT検査により肺炎徴候のチェックを行います。間質性肺炎が疑われる症状や画像上の所見が出現したときは担当医へすぐに報告し、投与の中止や呼吸器専門医へのコンサルトを検討します。 ③間質性肺炎への対応 間質性肺炎と診断された場合はステロイドによる治療を行います。 重症度によっては、検査結果を待たずに治療を開始し、必要に応じて酸素投与や人工呼吸管理など呼吸管理を行います。 間質性肺炎の予防・予測のポイント まず、間質性肺炎のリスクファクター(表6)5を知り、発症しやすい患者を把握しましょう。 予防法はありませんが、治療前に間質性肺炎と肺線維症の罹患と既往を確認して、担当医と化学療法投与の可否を相談します。 表6 間質性肺炎のリスクファクター ・高齢者(55 歳以上)・患者状態不良(PS*42以上)・間質性肺疾患の既往・合併・喫煙歴あり・正常肺占有率が低い(10~50%) *4【PS】performance status(パフォーマンスステイタス)。歩行や労働、社会活動などの全身一般状態の程度を5段階(グレード0~グレード4)で評価する指標。数値が小さいほうが活動性が高い。(文献5より引用) 引用文献1.田中喬:がん治療における救急処置-オンコロジック・エマージェンシー.国立がん研究センター内科レジデント 編,がん診療レジデントマニュアル 第6版.医学書院,東京,2013:421-422.2.杉本由香:腫瘍崩壊症候群.がん診療UP TO DATE編集委員会 編著,がん診療UP TO DATE.日経BP社,東京,2013:902-910.3.日本臨床腫瘍学会 編:発熱性好中球減少症(FN)診療ガイドライン.南江堂,東京,2012.4.沖中敬二:感染症対策.国立がん研究センター内科レジデント 編,がん診療レジデントマニュアル 第6版.医学書院,東京,2013:348-353.5.齋藤好信,弦間昭彦:肺毒性.がん診療UP TO DATE編集委員会 編著,がん診療UP TO DATE.日経BP社,東京,2013:778-786. 参考文献1.石田里美,早坂和恵:化学療法・放射線療法に伴う急性反応 敗血症性ショック.がん看護 2009;14:60-62.2.菅野雄介,木村芳子,加藤万里子:化学療法・放射線療法に伴う急性反応 間質性肺炎.がん看護 2009;14:63-66. この記事を読んだ方におすすめ●呼吸の変化で見抜く!急変未満のサイン●間質性肺炎の急性増悪を画像で見るポイント●X線画像でみるバイタルサイン・呼吸音が示す肺の変化●そのほかの連載記事 ※この記事は『エキスパートナース』2014年5月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。
- 会員限定
- 特集記事