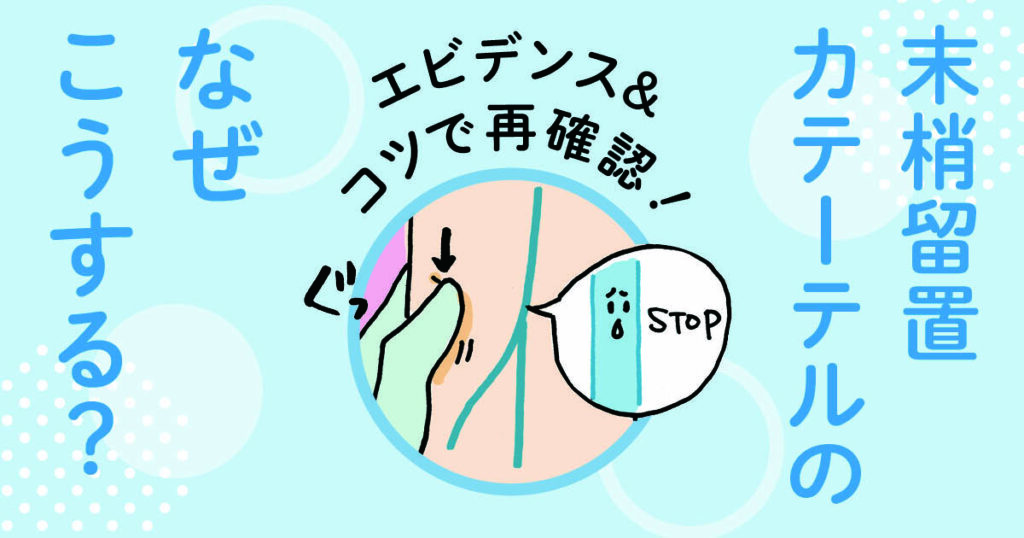日常的に行う末梢留置カテーテルの穿刺や管理について、それらを「なぜ行うのか」を解説する全13回の連載です。確実な実施のため、根拠とコツをもう1度おさえましょう!
【第1回】高齢、浮腫や肥満がある患者の末梢静脈ルート確保
〈目次〉
●高齢、浮腫や肥満がある患者では「皮膚の伸展」などを行ってから穿刺に移行する
・ルート確保のコツ①高齢患者の場合には、皮膚を固定しながら針を進める
・ルート確保のコツ②浮腫・肥満がある場合は、“血管のありそうな部位”を指で押さえる
・ルート確保のコツ③ショック状態の患者の場合は、他の投与方法も検討する
・ルート確保のコツ④血管を怒張させるための体位も重要
・ルートの固定:適切な長さを設定し、不要な三方活栓は外す
【第2回】ルート確保の基本―穿刺部位・穿刺血管の選択方法
〈目次〉
●穿刺部位の選択:患者の可動性を制限しないところを選択する
●穿刺血管の選択:「よく見え」「弾力のある」「蛇行していない」血管を選択する
●神経の分布部位を避ける
【第3回】急変場面での穿刺部位は肘正中皮静脈が第一選択
〈目次〉
●急変場面での穿刺部位は「肘正中皮静脈」が第一選択
・急変場面での選択基準は、「確実性」が最も重要
・可動性のある部位を選択せざるを得ない場合は皮膚傷害に注意
●ルート確保のキホン:“末梢が締まっている”とき、血管確保のために保温してはいけない
【第4回】末梢静脈ルートは上肢でのルート確保が基本
〈目次〉
●「どうしても」という場合以外は、上肢でルート確保できる部位をさがす
・下肢でのルート確保は、やむを得ない場合にのみ選択される
・下肢にルート確保する場合も血管・神経の走行を理解して実施する
【第5回】末梢静脈ルート確保時の駆血のポイント
〈目次〉
●ルート確保時の駆血は、「静脈は怒張、動脈は触れる」程度の圧で、1~2分をめやすに行う
・駆血は「静脈は怒張、動脈は触れる」程度の圧が最適
・駆血時間は神経傷害や皮膚傷害を避けるため、1~2分をめやすに
【第6回】末梢静脈カテーテルの固定方法のポイント
〈目次〉
●ルートは刺入部と別に固定し、追加補強を行う
・ルートが牽引されたとき、留置針まで抜けてしまうなどの恐れがある
・剥がれにくくする固定時の工夫
・不穏患者には「ルートを見えなくする方法」も有用
【第7回】末梢静脈ルートの長さのめやすと調節時の注意点
〈目次〉
●ルートの長さは患者ごとに適切に設定し、三方活栓はなるべく使用しないことが望ましい
・感染・接続外れ予防のため、接続箇所を少なくする
【第8回】末梢静脈からの薬剤投与の際に血管痛を防ぐには?
〈目次〉
●血管痛を防ぐためには、「等張液に近い浸透圧の薬剤」を「緩徐」に投与する
・血液の範囲を越える pH・高浸透圧の薬剤は、静脈炎・血管外漏出を引き起こす恐れ
・末梢からの投与に注意が必要な主な製剤(抗がん剤は除く)
●静脈炎の痛みは「薬剤の浸透圧」「投与スピード」の調整で対応する
【第9回】抗がん剤以外の血管外漏出時は冷罨法を実施する
〈目次〉
●抗がん剤以外の血管外漏出時の対応は、「温罨法」ではなく「冷罨法」で行う
・薬剤漏出時、カテーテル抜去後の対応として冷罨法を実施する
・血管外漏出を引き起こす原因と対策
①患者側の原因
②薬剤側の原因
・血管外漏出後に皮膚傷害を起こしやすい薬剤とその理由
③その他の原因
【第10回】薬液が滴下しない原因は閉塞以外にもある
〈目次〉
●薬液が滴下しなくなったときに「閉塞」と決めつけず、他の要因も検討する
・閉塞時に確認したい「5つの確認ポイント」
①患者の体位
②関節の屈曲
③ルートなどの圧迫と屈曲
④血管外漏出や留置針内腔の閉塞
⑤粘度の高い薬剤や複数のルートを同時に開放している場合
【第11回】感染管理:末梢留置カテーテルは96時間以上留置できる
〈目次〉
●留置期間を延長しても静脈炎・感染の徴候がなければ交換は必要ないと考えられる
●ルートの交換は7日以内の実施が望ましい
●カテーテル留置期間中は皮膚の状態を毎日観察する
【第12回】末梢留置カテーテル刺入部のドレッシング材の選択
〈目次〉
●刺入部が観察しやすい透明なドレッシング材を用い、滅菌されたポリウレタンフィルムで固定
【最終回】末梢留置カテーテルにおける生食ロックの選択
〈目次〉
●ヘパリン生食と生食で、ルートの開存や静脈炎発生に差はない
●陽圧ロック実施の際は、必ず「生食注入をしながら」シリンジを外す
・陽圧ロックの手順